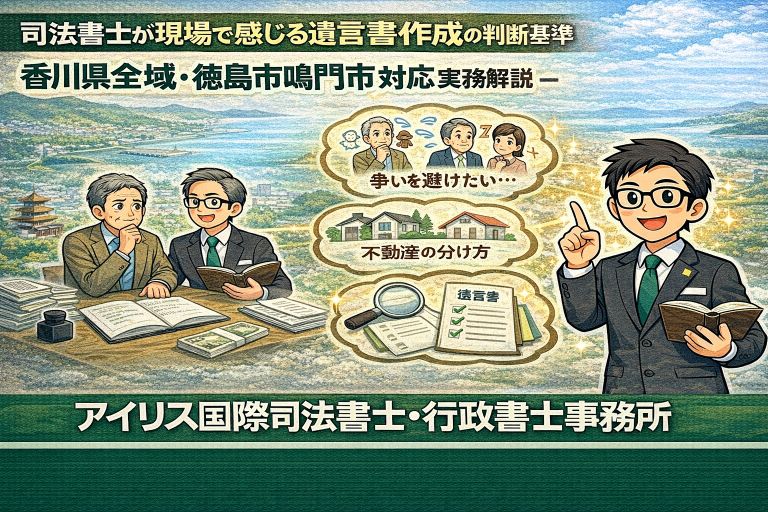遺言書の必要性は家庭の事情だけで決まるものではありません。
地域の不動産事情、家族構成、人口構造によって相続トラブルの発生パターンは明確に変わります。
【香川県・高松市・丸亀市】家族に安心を届ける生前対策の総まとめ|遺言書を活かすポイント

相続対策の要である遺言書は「作っただけ」では意味がありません。香川県・高松市・丸亀市で家族に安心を届けるために、遺言書を活かす生前対策の総まとめを司法書士が解説します。
📌目次
- これまでのおさらい|遺言書の重要性
- 遺言書を活かす3つのポイント
- 自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方
- 付言事項で家族の不安をなくす
- 定期的な見直しが家族を守る
- 家族会議を継続して信頼関係を築く
- まとめ|家族に安心を残すために司法書士ができること
1. これまでのおさらい|遺言書の重要性

このシリーズでは、相続で起こりがちな「争族」を防ぐ方法として、遺言書の基本から付言事項の活用、親子で進める生前対策の方法をお伝えしてきました。
遺言書は「自分の意思を形にする」だけではなく、「家族を守る大切な道具」です。
香川県・高松市・丸亀市でも、「遺言書があったおかげで家族が争わずに済んだ」という事例が多くあります。
しかし、作っただけで満足して放置してしまうと、せっかくの遺言書も無意味になりかねません。
大切なのは「遺言書を活かすこと」です。
2. 遺言書を活かす3つのポイント

遺言書を活かすためには、次の3つのポイントを意識しましょう。
✅ ① 家族に存在を伝える
せっかくの遺言書も、家族がその存在を知らなければ探し出せません。必ず信頼できる家族に保管場所を伝えるか、公的な保管制度を活用しましょう。
✅ ② 定期的に見直す
家族構成や財産状況は時間とともに変わります。状況が変わったら、遺言書の内容が現状と合っているかを確認し、必要なら作り直すことが重要です。
✅ ③ 家族に気持ちを伝える
付言事項などを活用し、遺言書に想いを込めることで、家族は「なぜこの内容なのか」を理解し、争いを防げます。
3. 自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
✅ 自筆証書遺言
手軽に作成できるのがメリットですが、形式不備や紛失のリスクがあります。
最近は法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を活用する方も増えています。
✅ 公正証書遺言
公証役場で作成するため、形式不備の心配がなく、原本は公証役場に保管されます。
費用はかかりますが、確実性を重視したい方におすすめです。
どちらが良いかはご家族の状況によって異なりますので、司法書士に相談してベストな方法を選びましょう。
4. 付言事項で家族の不安をなくす

法的効力を持つ内容だけでは、家族が遺産分割の背景を理解できないことがあります。
そこで役立つのが「付言事項」です。
✅ 分割の理由を説明する
「なぜ長男に家を残すのか」「なぜ次男に現金を多めにするのか」を書いておけば、相続人同士が誤解しにくくなります。
✅ 感謝の言葉を残す
長年の介護への感謝、家族への思いを残せば、遺言書が単なる財産分けの書類ではなく、家族をつなぐ手紙になります。
5. 定期的な見直しが家族を守る
一度作った遺言書も、時が経てば状況は変わります。
例えば、
- 相続人が亡くなった
- 不動産を売却した
- 孫が生まれた
- 法改正があった
こうしたタイミングで見直しをしないと、思わぬトラブルの原因になります。
香川県でも「10年前の遺言書が実情と合わなくて困った」という相談が増えています。
司法書士と一緒に定期的に内容を確認する習慣をつけましょう。
6. 家族会議を継続して信頼関係を築く
相続について家族で話し合う機会は、一度だけで終わらせないのが理想です。
✅ 生活状況に合わせて定期的に話す
家族の事情は変わります。相続の話をすること自体が信頼関係を築くきっかけになります。
✅ 司法書士など第三者を活用する
専門家が進行役になることで、感情的になりがちな話し合いもスムーズに進みます。
7. まとめ|家族に安心を残すために司法書士ができること
家族を守る相続対策は、単に遺言書を作るだけでは完成しません。
家族と想いを共有し、状況に合わせて見直し、専門家と一緒に進めることが大切です。
香川県・高松市・丸亀市での相続対策は、地域事情をよく知る司法書士にぜひご相談ください。
大切な家族に「安心」という形を残すお手伝いを、私たちは全力でサポートいたします。

最新のブログ記事
司法書士が現場で感じる遺言書作成の判断基準|香川県全域・徳島市鳴門市対応実務解説
遺言書を作るべきかどうかの判断は、形式論ではなく個別事情の整理によって決まります。相続相談の現場では、資産額よりも不動産の性質や相続人構成が難易度を左右するケースが多く見られます。本記事では香川県17市町および徳島北部を念頭に、実務経験を基に遺言書作成判断の視点を整理します。
【香川県全域と徳島市、鳴門市の生前対策】保険金と遺言書を上手に組み合わせる家族思いの方法
「生命保険があれば遺言書はいらない」と思っていませんか?実は、保険金と遺言書を上手に組み合わせることで、ご家族の生活をより確実に守ることができます。香川県高松市の司法書士が、保険金と遺言書の関係について、わかりやすく解説します。
【香川県全域と徳島市、鳴門市の生前対策】不動産の名義変更が義務に!遺言書で準備すれば安心
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産の名義変更を怠ると過料のリスクが。この記事では、遺言書を使って事前にできる安心の備えについて、やさしい言葉で司法書士が解説します。