相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年8月21日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
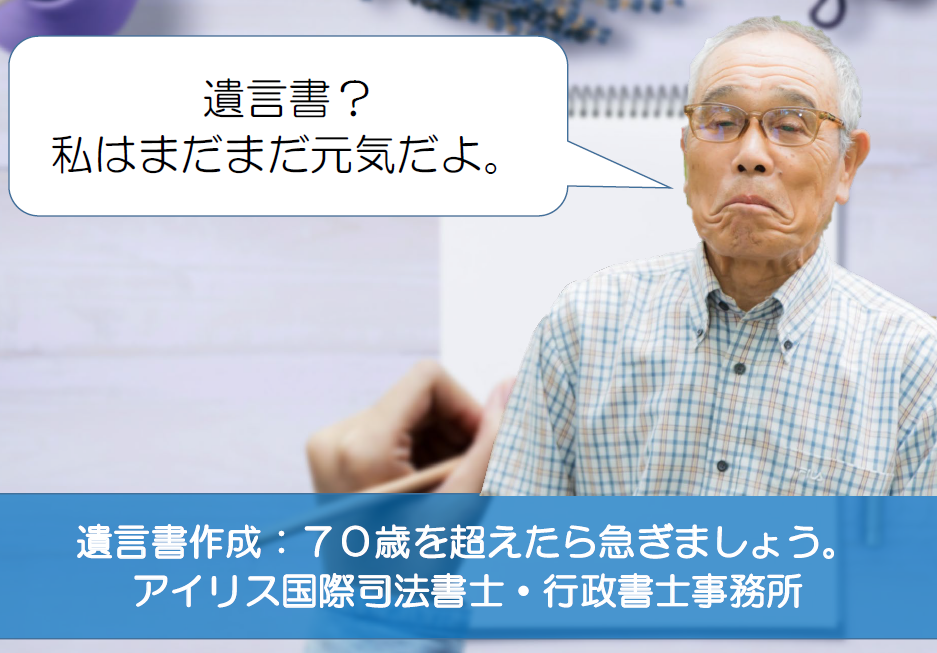
先日、ご相談に来られた方に遺言書の作成をお勧めいたしましたところ、「まだ私は大丈夫。」とおっしゃられていました。そこで、様々な資料をお見せしたところ、遺言書作成について受任いたしました。その資料の内容について、解説いたします。
目次
1.遺言書がなぜ必要
2.なぜ70歳になったら遺言書なのか
3.まとめ

1.遺言書がなぜ必要
2024年(令和6年)の相続登記義務化により、今後、相続登記に関する問題が浮上する可能性が非常に高くなっています。現に、私が市役所の無料相談会に参加した際に、相談件数は通常の倍、しかもその9割以上が相続に関連するものでした。
それでは、遺言書を作成するメリットについて解説いたします。
相続登記をする際に、遺言書がない場合、「遺産分割協議」を相続人全員で行い、その内容をまとめた遺産分割協議書に相続人全員が記名・実印で押印し全員分の印鑑証明書の添付が要求されます。生前、離婚した妻の子供や疎遠になった親族が相続人になることがあります。遺産分割協議自体が困難になるケースも多くの相談者の方で見てきました。
この遺産分割協議は、遺言書があればその遺言書の内容に応じて相続登記が可能なんです。残されたご家族の負担が大きく軽減されるといっても過言ではありません。
2.なぜ70歳になったら遺言書なのか
遺言書の作成するのは、もちろん親になります。日本人の平均寿命からすると、男性81.47歳、女性87.57歳(2021年厚生労働省)です。まだまだ大丈夫なんじゃないのと思われるかもしれません。
しかし、ご高齢者になると、司法書士や公証役場に出向くことは、それなりに負担が大きいのです。元気なうちに遺言書の作成をする必要性があるのです。
支障なく日常生活ができるとされる健康寿命は、男性72.68歳、女性75.38歳(2019年厚生労働省)です。意外と短いということがわかります。
※健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」(厚生労働省)
さらに年齢が進むと認知症発症のリスクが増加します。グラフを見ますと70歳代後半から認知症発症の割合が、それまでと比べて増加していることがわかります。

3.まとめ
このように、遺言をするにも健康状態や認知症のリスクといったことを考慮する必要性が出てきます。相談者の中にも90歳で遺言を書きたいと言って来訪される方もいますが、公正証書遺言をするにも労力と公証人の質問に的確に答えられなければ、難しいと思います。自筆証書遺言ですと、相続発生後、相続人間でもめた場合、その遺言書が判断能力を理由に無効にされるかもしれません。
早めの遺言書対策が、残されたご家族の負担を軽減いたします。ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。

令和6年8月21日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
ビジネス環境の変化に対応することは、経営者にとって不可欠な課題です。現代の経営者は、急速な技術革新、グローバル化、消費者ニーズの多様化、そして環境問題への対応など、多岐にわたる変化に直面しています。これらの変化に柔軟に対応し、企業の持続的成長を実現するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。そのポイントについて解説いたします。
ランサムウェアは、コンピュータシステムを人質に取り、復旧のための身代金を要求するサイバー攻撃です。最近では、その手口が高度化・多様化し、企業や個人に対する脅威が増しています。以下に、最近のランサムウェアの事例と、それに対する対策方法をまとめます。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書き残す形式の遺言書で、作成や変更が比較的容易であるため、多くの人に利用されています。しかし、その一方で法的効力を持たせるためには一定の要件を満たす必要があります。以下に、自筆証書遺言を作成する際に気を付けるべきポイントを詳しく説明します。
相談者の方から相続登記のご依頼があり、被相続人の不動産を特定するために「固定資産材評価証明書」の取得をお願いいたしました。被相続人は、生前離婚歴があり、離婚の際、財産分与を受けていました。しかし、ずいぶん前に亡くなっており、登記簿上の名義人の住所と、被相続人の最後の住所地が同じでしたので、住民票の除票の写しもしくは戸籍の附票の取得をお願いいたしました。
生前贈与のために相談に来られた方で、登記簿を確認すると「平成の大合併」で、地番の変更はありませんが、平成18年に○〇郡から○〇市に編入されていましたが、登記簿を確認すると平成18年以前に、相続登記がされていて、そのために旧住所で登記がされている状態でした。
先日の相談で、遺言書に「特別受益の持ち戻し免除」の条項を入れると、遺留分対策になるのかという質問を受けました。
先日、相続登記のご依頼で不動産の調査をしていたところ、土地・建物共に今回亡くなった方の名義になっていたのですが、かたくなに「土地の名義変更だけでいいです。」とおっしゃられるため、なぜそれでいいのかその理由を聞いてみました。そうすると、「知り合いの方が、相続登記義務化の対象は、土地だけだから、建物は必要ない。」とのことでした。
