司法書士が教える宇多津町の生前対策|実務チェックリストと成功事例
宇多津町の生前対策は
①不動産の名義確認 ②遺言書作成から始めるのが最優先です。
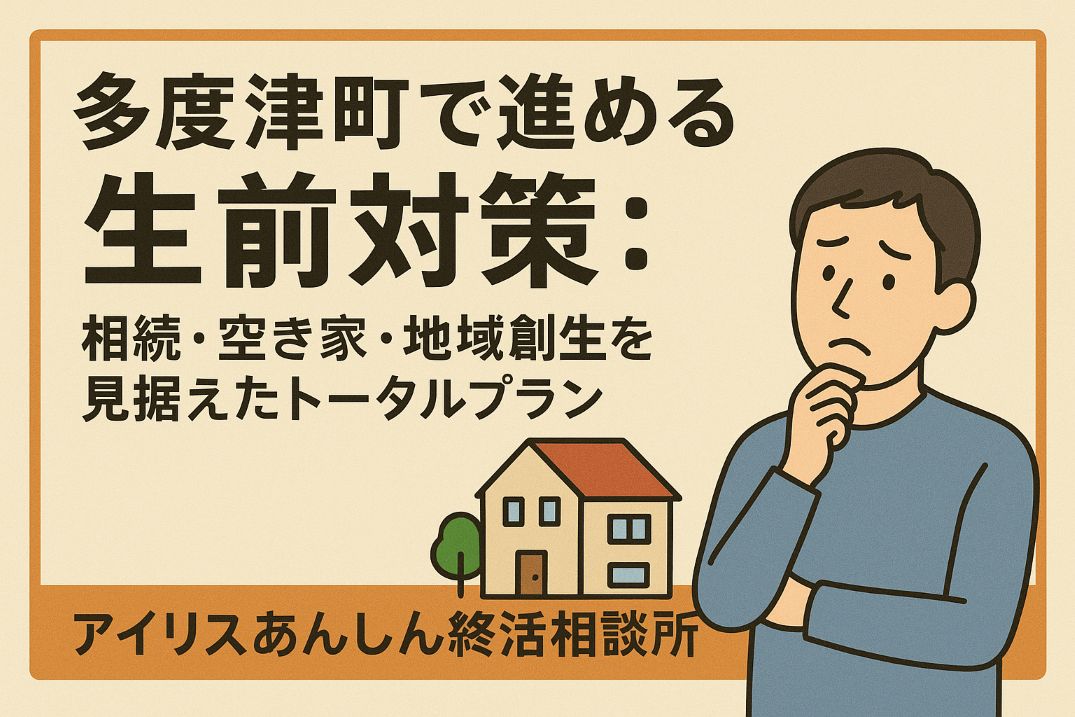
香川県・多度津町。港町として歴史ある一方で、高齢化や空き家の増加が地域の将来に影を落としています。そこで注目されるのが「生前対策」です。遺言・相続登記・家族信託などを通じて、ご自身の資産をしっかり整理するだけでなく、空き家を地域資源として活かす道もあります。本記事では、多度津町の地域特性を踏まえながら、具体的な対策とポイントをご紹介します。
目次
1. 多度津町の現状と課題

1.1 地理・人口・都市計画の特色
多度津町は香川県仲多度郡に位置し、瀬戸内海に面した港町です。歴史的には造船業や港湾関連産業もありましたが、人口減少・高齢化の波も確実に押し寄せています。町では令和7年3月に改定された「立地適正化計画」を策定し、中心部への居住誘導、多世代が集まるにぎわいあるまちづくりを掲げています。
このような背景から、将来的には商業機能や医療・福祉サービスの維持にも課題が出てくる可能性があり、資産を持つ住民の視点でも"まち全体の将来"を考えた対策が必要です。
1.2 空き家の問題と地域の取り組み
香川県全体での空き家率も高く、県内では放置空き家の割合が深刻化している地域があることが報告されています。
多度津町自身も空き家対策に力を入れており、地域創生を目的とした空き家・空き店舗の活用事業には補助金を出しています。
また、老朽化が進んだ危険な空き家については、除却費の一部を補助する制度も整備されています。
さらに、改修を条件とした空き家改修支援補助金もあり、改修によって移住や定住、交流拠点化を目指す取り組みが可能です。
こうした制度は、生前に所有不動産の将来を見据えるうえで重要な手がかりになります。
2. 生前対策がなぜ重要か

2.1 相続登記義務化の影響
2024年4月から施行された「相続登記義務化」により、不動産を相続した人は3年以内に登記をしなければなりません。義務化を放置すると過料(10万円以下)が科されるリスクがあるため、名義整理を怠ることは避けたいところです。
多度津町には、昔からの住宅が残る旧市街地や祖父母・曽祖父母の名義のままになっている不動産も多いと想定され、登記未了の問題が潜在的に存在する可能性が高いです。
2.2 空き家問題と放置リスク
放置された空き家は老朽化が進みやすく、倒壊や火災などの危険性をはらみます。また、資産価値が下がったり、管理コストや税負担が増える可能性もあります(固定資産税など)。
さらに、共有名義の建物や土地は相続人間のトラブルの火種になりやすく、適切に整理しないと売却や活用の妨げになります。
2.3 財産を整理する意味とメリット
生前対策を通じて財産を整理することは、相続人間のトラブルを回避するだけでなく、空き家を地域の資源に変えることでまちづくりに貢献できます。遺言書や家族信託を使えば、自分の意思を明確にした上で、資産を「遺す」だけでなく「使ってもらう」未来を設計できます。
3. 多度津町で活用できる制度・支援策

多度津町には、生前対策・相続対策を進めるうえで活用できる公的制度があります。
3.1 空き家改修支援補助金
多度津町では、空き家を改修する際の費用に対し「空き家改修支援補助金」があります。補助率は改修工事費の1/2、上限は100万円。
改修後は空き家バンクへの登録が条件になるため、移住や定住、賃貸・交流拠点として活用しやすくなります。
3.2 老朽危険空き家の除却支援
倒壊の恐れのある老朽化した空き家を除却する場合、多度津町では除却費の一部を補助する「老朽危険空き家除却支援事業」があります。
これにより、危険な空き家を早期に処分し、地域の安全性を高めることができます。
3.3 移住・交流型創生補助金
空き家を活用して地域内外との交流を促進する事業を行う団体への補助金もあります。
また、空き家を事業所として改修し活用する法人・個人事業主向けには、「移住促進・空き家活用型事業所設備補助金」という支援も。最大400万円まで補助されます。
これらを活用すれば、生前に所有不動産を地域創生の観点で有効活用するビジョンを描けます。
4. 生前対策の具体的方法

ここからは、生前対策として具体的に取れる手段を紹介します。
4.1 遺言書作成(公正証書遺言など)
遺言書を準備することは、自分の意思を明確にするうえで非常に重要です。公正証書遺言であれば、公証人が作成をサポートしてくれるため、法的な確実性が高まります。特に、空き家や土地が相続財産に含まれる場合、誰にどのように残すかを明記しておくことで、後の争いを防げます。
4.2 相続登記と名義整理
相続が発生した際は、できるだけ早く登記を行うべきです。2024年の義務化により、放置はリスクがあります。登記をきちんと整理することで、所有関係を明確にし、将来的な売却や活用をしやすくします。
4.3 家族信託の活用
家族信託を使えば、生存中から自分の不動産を「信頼できる家族」に託し、管理・運用してもらうことができます。たとえば、空き家になる見込みの住宅を信託財産とし、その家を地域交流施設や賃貸住宅として運営する計画を立てることも可能です。
4.4 共有名義物件とその整理
相続によって共有名義になる土地・建物はトラブルになりやすいです。共有者間で早めに話し合い、分割協議をしたり、共有持分を売買したり、信託を使ったりして整理するのが望ましいです。
5. 地域創生とリンクさせた対策戦略
生前対策を地域創生と結びつければ、自分の資産が地域の未来にも貢献します。
5.1 空き家を地域資源に変える
改修補助金を活用して空き家をリノベーションし、交流拠点や賃貸住宅として活かすことで、地域の活力創出に貢献できます。これにより空き家の所有者は固定資産を有効に使いながら、地域にも貢献できます。
5.2 相続後も地域に残す遺産設計
遺言や信託を通じて、相続後も建物を地域に残す設計をすることが可能です。たとえば、地域住民や若者向けの住居や活動拠点として活用を想定した設計を組むことで、相続財産が地域の資産にもなります。
5.3 多世代交流・まちづくりと遺産の関係
高齢者と若者、移住者との交流拠点として空き家を使えば、多世代のつながりをつくれます。所有者としては、「ただ老朽化した家を手放す」だけでなく、「まちの未来に残す資産」に変えることができます。
6. よくあるケースと相談例

それぞれのケースで、司法書士やFP(ファイナンシャルプランナー)、建築士と連携することで、最適な対策を描くことができます。
7. まとめと次のステップ
多度津町における生前対策は、「自分の財産を整理する」だけでなく、「地域の未来を見据えた資産設計」として非常に有効です。相続登記義務化や空き家対策の制度をうまく活用することで、安心の相続と地域貢献の両立が可能です。
次に取るべきステップ:

(無料相談会のご案内)
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ
香川県外からのオンライン相談(Zoom)にも対応しています。

宇多津町の生前対策は
①不動産の名義確認 ②遺言書作成から始めるのが最優先です。
生前対策は「余裕があればやる準備」ではありません。
今や"法的義務とリスク管理"の問題です。
認知症対策について相談を受ける中で、私が最も強くお伝えしていることがあります。
丸亀市で生前対策を始めるなら、
「不動産」「認知症」「空き家」の3点を最優先で整理することが成功の鍵です。