香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
令和6年4月1日相続登記義務化(抵当権の債務者の相続登記)
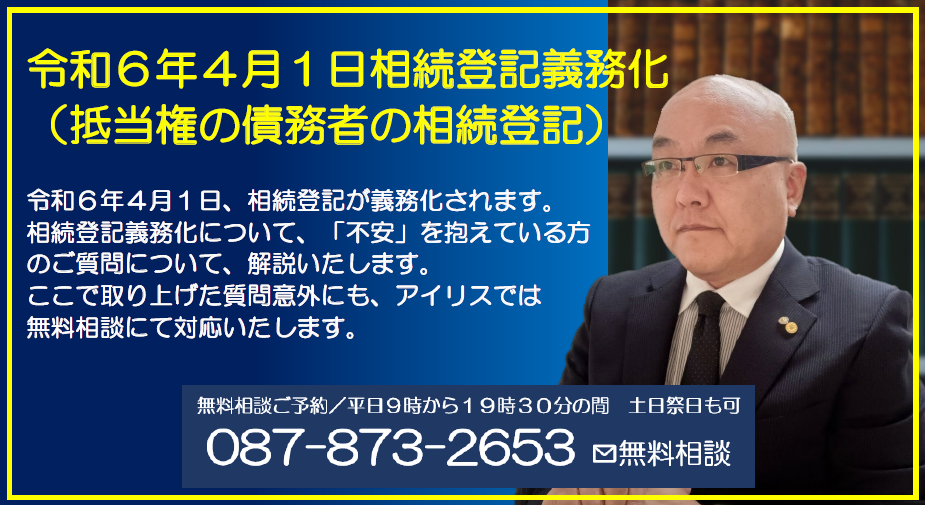
住宅ローンが残った状態で亡くなった場合の相続登記として、土地・建物の名義変更は当然なのですが、住宅ローンの借入金を担保している抵当権の債務者の変更登記も必要となります。この辺りについて解説したいと思います。
目次
1.抵当権とは
2.債務者の変更する2種類の登記
3.まとめ
1.抵当権とは

抵当権とは、住宅ローンで融資を行う金融機関が、借入を受ける人が購入する不動産などをローンの担保として設定する権利のことです。
担保となる不動産などは債務者が利用できますが、もしローンを返済できなくなった場合は、代わりに担保に設定された不動産を金融機関に差し押さえられます。
つまり、「借入金=抵当権で担保する債権」ということになります。
抵当権の債務者に相続が発生した場合には、相続による債務者の変更の登記が必要になります。この登記を実現するためには、2通りのやり方があります。ほとんどの場合、債権者である金融機関から指定があると思います。
2.債務者の変更する2種類の登記
①遺産分割協議による方法
債権者(金融機関)の承諾を得て、遺産分割協議によって相続人の一人が債務を承継する、抵当権変更登記のやり方です。登記申請書は、1件で済みます。
具体的には、「債務は、相続人全員が法定相続分によって承継し、遺産分割協議の対象とはならない」とされていますが、これは債権者保護を考えてのことなので、債権者が承諾するのであれば、債務の遺産分割協議も有効にすることができます。
遺産分割協議の効果は相続開始時にさかのぼるため(民法第909条)、債務を引き受けた相続人は、被相続人の死亡日にさかのぼって債務を承継することになります。
抵当権変更登記申請のやり方ですが、「〇年〇月〇日相続」を原因として、1件の登記申請によって、債務者を特定の一人の相続人に変更できます。
「〇年〇月〇日相続」の日付は、被相続人の死亡日です。
「変更後の事項」は、「債務者」として、債務を承継することになった相続人の住所氏名を記載します。
登記申請の添付書類としては、報告形式の登記原因証明情報があれば、相続を証する戸籍謄本や遺産分割協議書の添付は必要ありません。
➁免責的債務引受による方法
第1に、相続を原因として、債務者を共同相続人全員に変更する抵当権変更登記を行い、その次に、相続人の一人が免責的債務引受を行ったことによる抵当権変更登記を行うやり方です。登記申請書は、2件必要です。
1件目の抵当権変更登記申請で、「〇年〇月〇日 相続」を原因として、債務者を相続人全員(ここではABCの3人)に変更します。
2件目の抵当権変更登記申請で、「〇年〇月〇日 B及びCの債務引受」を原因として、債務者をAに変更します。この2件目の免責的債務引受については、債権法改正により、法務省より通達(令和2年3月31日付法務省民二第328号)が出ています。
※免責的債務引き受けをする場合には、次の4パターンが考えられます。ここでは(X債権者、Y債務者、Z引受人)とします。当然その債務の性質は、「他人が変わって履行することができる債務であること」です。住宅ローンのような金銭債務の場合は対象となります。さて、契約のパターンと、効力が生じる要件についてお話をいたします。その内容は、
(免責的債務引受契約の契約当事者と契約が有効になる要件)
①XYZの三者間の契約
問題なく有効となります。
➁X(債権者)Z(引受人)間の契約
(民法472条2項)により、Y(債務者)の意思に反しても可能です。ただし、X(債権者)からY(債務者)に対して「通知」した時に効力を生じます。
③Y(債務者)Z(引受人)間の契約
(民法472条3項)により、X(債権者)の承諾があれば有効です。
④X(債権者)Y(債務者)間の契約
Z(引受人)の意思に反してはできません。
債務を引き受ける契約はこれでいいのですが、実際に担保権(ここでは抵当権)を移転する場合の注意点は、
①引受人への担保権の移転
債権者は、免責的債務引受によって債務者が免れる債務に設定された担保権(抵当権)を移転することができます。(民法472条の4第1項)ただし、当該担保権を設定した者が引受人以外の場合の者である場合には、その者の承諾(担保権移転の意思表示)を得なければならない。(民法472条の4第1項但書)
➁引受人に対する意思表示
担保権の移転は、免責的債務引き受けを行うよりも前に又は同時に、引受人に対する意思表示によって行わなければならない。(民法472条の4第2項)
③保証人の承諾
債務者の債務に付された保証債務を引受人の債務を担保するものとして移すためには、保証人の承諾を要する。(民法472条の4第3項)保証人の承諾は、書面又は電磁的記録でしなければならない。(民法472条の4第4、5項)
※令和2年の債権法改正の論点になります。詳しくは専門家にご相談ください。
3.まとめ
このように、免責的債務引受けの場合、単純に債務を引き受けてもらうだけの契約をしてその内容を登記するだけ、とはなりません。相続が発生した場合、金融機関への相談及び専門家に相談を必ずするようにしてください。




最新のブログ記事
【2026年版】高松市の生前対策|遺言・信託・ライフプランで決める“あなたの安心設計”指南
生前対策は「相続の準備」ではなく、**これからの人生をどう生きるかという"設計図"です。
結論として、高松市の生前対策は、遺言・信託・任意後見を"ライフプランに合わせて組み合わせる"ことが最適解です。
本記事では、2026年時点の実務に基づき、安心設計の考え方をお伝えします。
【2026年版】香川県で失敗しない生前対策とは?|司法書士が実務・制度・手続きまで徹底解説
香川県で「生前対策」を考えたとき、最も重要なことは "実務として何を、いつまでに、どうすればよいか" を正確に理解することです。
2024年4月に始まった相続登記の義務化により、"対策しないことが家族の損失・リスクになる時代" になりました。
この記事では、司法書士の視点で 制度・法律・手続き・実例まで具体的に解説し、他の記事では書かれていない「失敗しない実務ライン」を整理します。
【2026年版】善通寺市で失敗しない生前対策|弁護士・司法書士が伝える実務ノウハウ
結論から言えば、生前対策の成否は「手段の選択」ではなく、「順序と専門家の関与」で決まります。
善通寺市でも、遺言・家族信託・任意後見といった制度を"部分的に"導入した結果、かえって手続きが複雑化するケースが後を絶ちません。本記事では、2026年時点の法制度を前提に、弁護士・司法書士の実務経験から、生前対策を失敗させないための考え方と具体的プロセスを整理します。




