【2026年最新版】香川県の相続登記義務化|3年期限・罰則・今すぐやるべき対策を完全解説
香川県の相続登記は「義務」です。
相続を知ってから3年以内に申請しなければなりません。
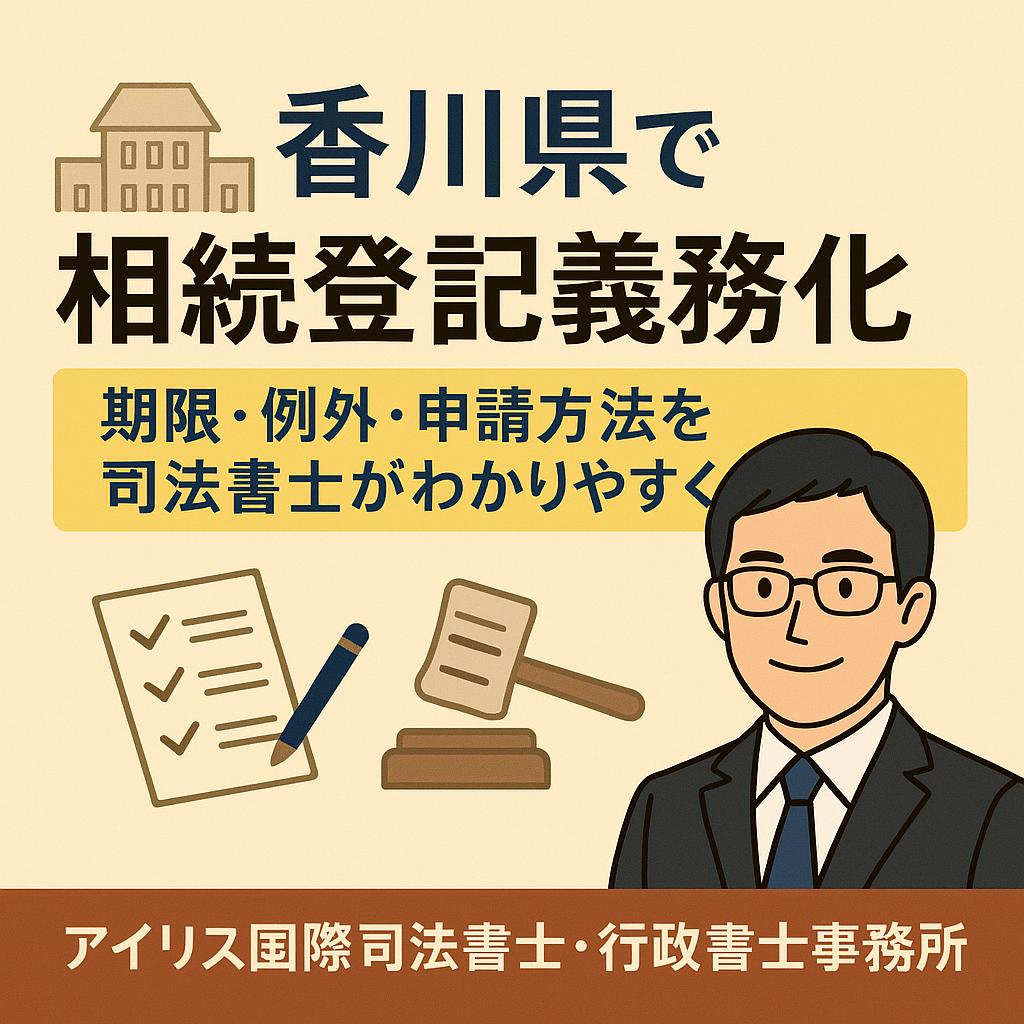
相続登記義務化が令和6年4月に施行され、香川県内の不動産も対象となりました。本記事では、期限や例外規定、申請手順、県外からの対応方法などを、司法書士が事例を交えてわかりやすく説明します。
【目次】
相続登記義務化の概要
- 制度の目的と背景
- 令和6年4月1日施行のポイント
- 香川県にも全国同様に適用される仕組み
香川県での対象範囲と事例
- 対象となる不動産の種類(住宅地・商業地・農地・別荘地など)
- 放置による過料リスクの具体例
相続登記の期限と延長が認められるケース
- 「相続を知った日から3年以内」という期限ルール
- 協議長期化や書類取得遅延など延長の可能性
- 延長可否の判断基準
相続登記の手続きステップと必要書類
1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
2. 相続人全員の戸籍・住民票取得
3. 固定資産評価証明書の用意
4. 登記申請書の作成と法務局提出
香川県外からの相続登記申請方法
- 郵送申請の流れと注意点
- オンライン申請の要件(電子証明書・専用ソフト)
- 専門家依頼による効率化のメリット
実務で多いトラブルとその防止策
- 相続人の一部が連絡不能な場合
- 遺産分割協議書の不備
- 書類不足や記載ミスの防止方法
まとめ|香川県の相続登記義務化は早めの対応が鍵
- 期限・例外規定を正しく理解する重要性
- 県外からでも対応可能な方法
- 思い立ったらすぐ動き出すべき理由
1. 相続登記義務化の概要

この制度は、不動産の相続登記を放置することで所有者不明になる問題を防ぐためのものです。施行は令和6年4月1日で、香川県も全国同様に適用されます。制度上は、相続によって不動産を取得した人が、一定期間内に所有権移転登記を行う義務を負います。
2. 香川県での対象範囲と事例

高松市の住宅地、丸亀市の商業用地、小豆島町の別荘地など、地目や利用形態を問わずすべて対象です。例えば、高松市内の実家を兄弟で相続したまま長年放置すると、義務化後は過料の可能性が生じます。
3. 期限と延長が認められるケース
期限は「相続を知った日から3年以内」です。ただし、相続人同士での協議が長引く場合や、書類取得に時間を要する場合など、やむを得ない事情があれば期限延長が認められる可能性もあります。延長の可否はケースごとの判断となります。
※一番手堅いのは「相続人申告登記」です。
4. 手続きのステップと必要書類
5. 香川県外からの相続登記の進め方

郵送やオンライン申請で対応可能です。オンラインの場合、事前に電子証明書や専用ソフトの準備が必要なため、専門家に依頼するとスムーズです。
※受任していただく場合には、必ず本人確認を実施いたします。
6. 実務で多いトラブルと防止策
7. まとめ:義務化対応は早めに
香川県の相続登記義務化は、期限や例外を正しく理解し、早めに着手することが重要です。県外在住でも対応できる方法はありますが、準備には時間がかかるため、思い立った時点で動き始めることをおすすめします。

香川県の相続登記は「義務」です。
相続を知ってから3年以内に申請しなければなりません。
宇多津町で相続登記を検討する場合、
制度理解だけでは足りません。
「登記が終われば一安心」
多くの方がそう思われますが、実はそれが落とし穴です。
結論からお伝えします。
相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から
「最初に整理すべきもの」へと変わりました。