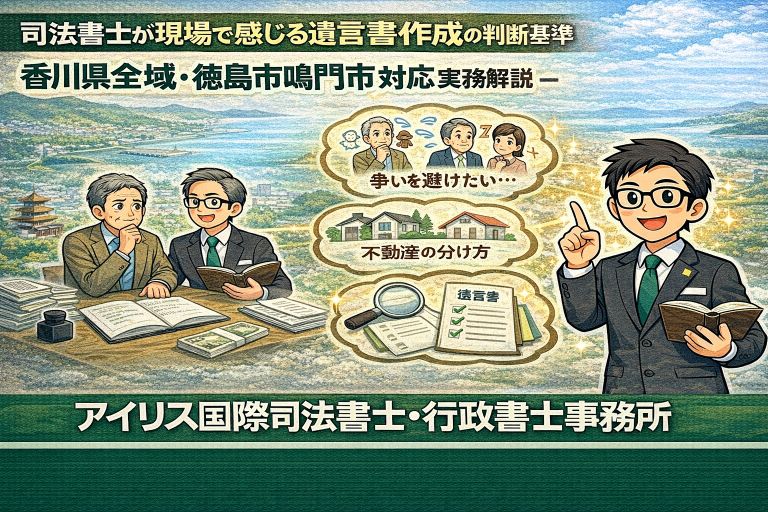遺言書の必要性は家庭の事情だけで決まるものではありません。
地域の不動産事情、家族構成、人口構造によって相続トラブルの発生パターンは明確に変わります。
【第3回】遺贈寄付をめぐる制度とビジネスの境界線~資格ビジネス化する現場の実情とは

遺贈寄付という言葉が広く知られるようになり、社会貢献の手段としての選択肢が広がる一方、制度の未整備や情報の非対称性を背景に、「囲い込みビジネス」として機能するケースも出てきています。
たとえば、一部の団体が独自に作成した「内部資格」や「研修制度」によって専門性を演出し、会員を囲い込むモデルが広がっており、その結果、相談者に不利な選択肢が提示されるおそれも否定できません。
この記事では、制度化が進む中で浮き彫りになってきた遺贈寄付をめぐる新たな問題点に焦点を当てます。公正で透明な制度運用のために、今、何が求められているのかを一緒に考えてみましょう。
■ 目次
- 遺贈寄付の制度整備とその限界
- 民間団体が設ける「資格制度」とは何か
- 会員囲い込み型モデルの実態と構造
- 想定されるリスクと相談者の不利益
- 制度の公正性を確保するために必要な視点
- まとめ:社会貢献とビジネスの境界線をどう引くか
1. 遺贈寄付の制度整備とその限界

遺贈寄付の注目度が高まる中で、国も一定の制度整備を進めています。たとえば、内閣府による「遺贈寄付に関するガイドライン」の策定、公益法人の透明化要請などです。
しかし、実際には制度が追いついておらず、特に相談者が正確な情報にアクセスしにくいことが問題となっています。
この隙間を埋める形で、民間の士業団体やNPOなどが独自のサービスを展開していますが、そのなかには、ビジネス色が強く出すぎてしまっているものもあるのが現状です。
2. 民間団体が設ける「資格制度」とは何か
近年よく見られるのが、ある団体が独自に作成した「遺贈寄付アドバイザー」や「遺言寄付カウンセラー」などといった内部資格制度です。これらの資格は法的な根拠を持つものではなく、その団体の中でしか通用しないにもかかわらず、「専門家の証」としてアピールされることがあります。
資格取得のための講座は有料で、受講料・年会費・更新料などが設定されており、営利的な構造が強い点は見逃せません。こうした内部資格の認定者を通じて遺言書作成や信託の相談を受け付け、囲い込みを図る仕組みが構築されている場合もあります。
3. 会員囲い込み型モデルの実態と構造

さらに深刻なのは、相談者の情報が団体内で回されてしまうことです。
たとえば、遺贈寄付希望者が団体に連絡をすると、内部資格を持つ会員に案件が紹介され、そこから遺言書作成や信託契約などのサービスに誘導されるケースがあります。
一見すると一貫したサポートに見えますが、その裏では「第三者のチェックが働かない」「相談者の比較検討の余地がない」といった不透明さがあります。相談者の立場からすれば、選択肢が提示されず、最初から囲い込まれている状態にあるともいえるのです。
4. 想定されるリスクと相談者の不利益
こうしたビジネスモデルに依存した仕組みには、以下のようなリスクがあります。
- 中立性の欠如:特定の団体と関係する士業が関与することで、相談者にとって最善の選択肢が排除される可能性。
- 費用の不透明性:相談の過程で複数の料金が発生するにもかかわらず、事前説明が不十分な場合がある。
- 制度の私物化:社会的意義のある遺贈寄付が、実質的に特定団体のビジネス手段として扱われてしまう。
- 信頼性の低下:業界全体に対する信用が揺らぎ、正当な活動をしている団体まで疑いの目を向けられる。
こうした不利益を防ぐためには、相談者自身が制度を理解し、必要に応じて中立な立場の専門家にセカンドオピニオンを求めることが重要です。
5. 制度の公正性を確保するために必要な視点

遺贈寄付の制度をより信頼されるものにするためには、以下のような視点が求められます。
- 資格の透明性:内部資格と国家資格の違いを明確にし、誤認を避ける。
- 利益相反の排除:団体と士業の間に一定の距離を保ち、過度な利害関係を回避する。
- 相談者の選択肢の保証:団体に相談があった場合でも、複数の専門家の情報を提示する仕組みづくり。
- 行政の関与:ガイドラインだけでなく、実務現場へのモニタリングや基準策定も視野に入れる。
6. まとめ:社会貢献とビジネスの境界線をどう引くか
遺贈寄付は、「人生の最後に社会へ恩返しをしたい」という善意に基づいた行為です。その思いを尊重するには、透明で中立的な制度設計と、相談者に寄り添う倫理観が欠かせません。
しかし、現実には制度の隙間にビジネス的な仕組みが入り込み、「遺贈寄付=囲い込み型サービス」というイメージが定着しかねない危うさも抱えています。
私たち一人ひとりが制度の仕組みを知り、良識ある判断を下すことが、遺贈寄付の信頼性を守る第一歩です。

次回(第4回)は、こうした課題の先にある「本当に信頼できる遺贈寄付の仕組み」や、今後求められる制度設計のあり方について考察していきます。
最新のブログ記事
司法書士が教える宇多津町の生前対策|実務チェックリストと成功事例
宇多津町の生前対策は
①不動産の名義確認 ②遺言書作成から始めるのが最優先です。
司法書士が現場で感じる遺言書作成の判断基準|香川県全域・徳島市鳴門市対応実務解説
遺言書を作るべきかどうかの判断は、形式論ではなく個別事情の整理によって決まります。相続相談の現場では、資産額よりも不動産の性質や相続人構成が難易度を左右するケースが多く見られます。本記事では香川県17市町および徳島北部を念頭に、実務経験を基に遺言書作成判断の視点を整理します。
司法書士が解説する宇多津町の相続登記実務|義務化・費用判断・2026制度対応チェックリスト
宇多津町で相続登記を検討する場合、
制度理解だけでは足りません。