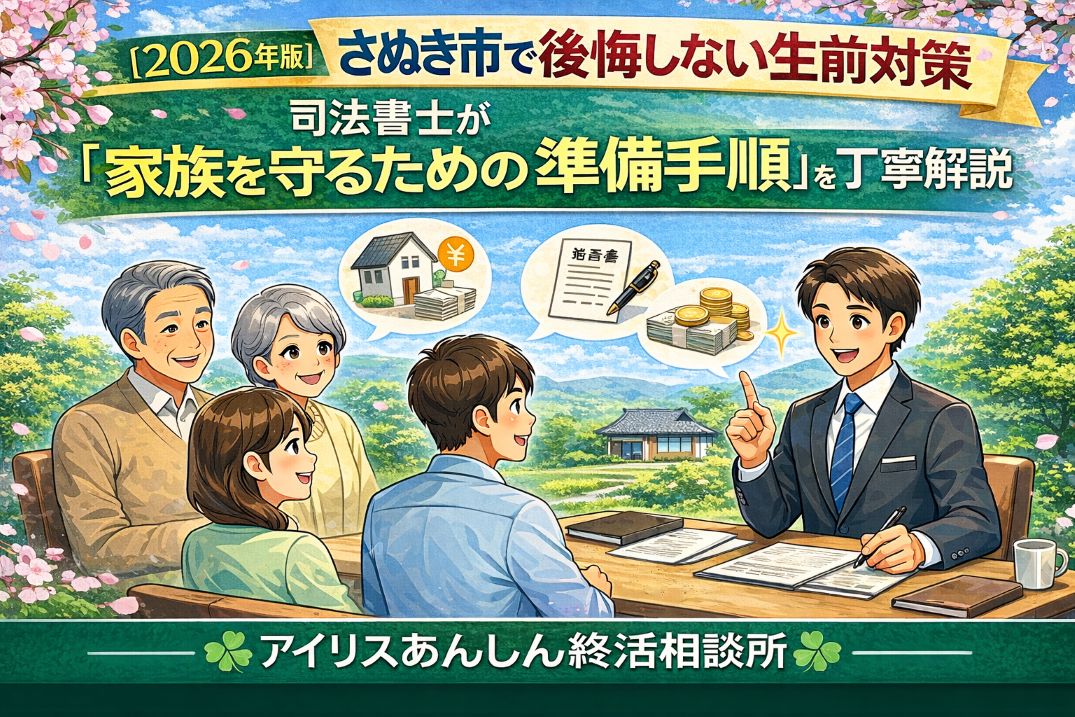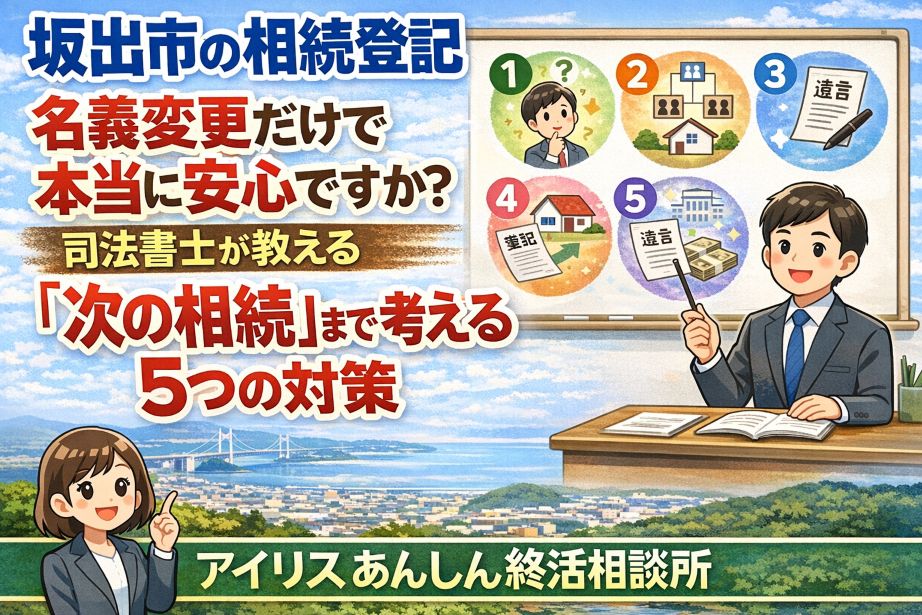香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
2024年5月3日~6日サンポート高松に「ロックをデザインする男」がやって来る

「ロックをデザインする男」ことサカグチケンさん(香川県出身)が、サンポート高松に来ます。実は、2年前のイベントでお伺いいたしました。昨年も実施されていたことは知っていたのですが、仕事が忙しくいけませんでした。今回は、サカグチケンさんのイベントに参加しようと思っています。そもそもサカグチケンさんはいったいどんな方なのかを含めて、お話をしていきたいと思います。
目次
1.サカグチケンとは?
2.ディスコグラフィー
3.2022年イベントに参加したときの様子
4.まとめ
1.サカグチケンとは?
サカグチ ケン(本名:坂口 賢、1964年1月19日 - )は、香川県出身のグラフィックデザイナー、アートディレクター。日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)会員。
1986年(昭和61年)に「年鑑日本グラフィックデザイン'86」で作品が掲載される。1990年(平成2年)6月、サカグチケンファクトリーを設立する。1991年(平成3年)6月20日にクラブチッタ川崎で個展を開催。1995年(平成7年)にリリースされたBUCK-TICKのアルバム『Six/Nine』のアートワークを担当。2015年(平成27年)にI.N.Aが中心に主催する電脳音楽塾においてアートディレクションを事例にした実践型の講義を行う。2023年(令和5年)4月、星海社新書より『ロックをデザインする男 サカグチケン dead start』を出版。
手がけたアーティストは、アナーキー、hide、BUCK-TICK、LUNA SEA、THE BLUE HEARTS、THE MAD CAPSULE MARKETS、DJ KRUSH、MUCC、人間椅子、中山美穂など。(Wiki引用)

2.ディスコグラフィー
2年前のイベントでは、CDのアルバムジャケットやポスターなどの作品を展示していました。私は主に、BUCK-TICKを中心にみていきました。
その後、私がBUCK-TICKのアルバムジャケットで衝撃を受けたのは、「in Heaven」「Taboo」「惡の華」「狂った太陽」「Six Nine」「Darker than Darkness」「ONE LIFE,ONE DEATH」「極東 I LOVE YOU」などです。
「Taboo」については、櫻井敦司氏の顔をモチーフに、赤・白・黄・青の粒のライトが当たって皮膚がまだら模様になっているデザイナのですが、リリースされたのが1989年1月18日です。つまり、WindowsもMacもグラフィックソフト的なものがない中、クオリティーも、今でこそコンピューターを使えばできますが、その当時、手書きで作成されたそうです。すごいですよね。「惡の華」のデザインも手書きだそうです。
そして、「極東 I LOVE YOU」の「愛」の文字。よく見ると何か欠けているんですよね。ご本人から、完全じゃないということを表現したかったと教えていただきました。
3.2022年イベントに参加したときの様子
当時、最終日前日ということで、あまり人もおらず、スタッフとご本人に作品の紹介をしていただきました。今考えるとあり得ないシチュエーションですよね。(笑)
私がすごく好きなアルバムジャケットの「極東 I LOVE YOU」の前でチェキで写真を撮りました。「愛」の文字の熱意を伝えていたのに、出来上がった写真は「愛」の文字が私の大きい体で隠れてしまい、サカグチケンさんに突っ込まれました。
印象的だったのが、別れ際に交わした言葉です。今まで、各作品の背景を熱をもって話していただいていたのですが、急に「俺もう58歳だよ。」とおっしゃられていました。私は、司法書士事務所開業前でしたので、「死ぬまで現役で行きましょう。一生ロックでいいじゃないですか。一度きりの人生なんですから。」と声をかけたのを思い出します。というと、今年は還暦ですね。おめでとうございます。

4.まとめ
今年のイベント、私は参加しようと思っています。今からとても楽しみです。サカグチケンさん、前回は、全く知らないことだらけで参加しましたが、今回はちゃんと受け答えできそうです。
ご興味のある方はぜひ、参加してみてはいかがでしょうか。

最新のブログ記事
【2026年版】さぬき市で後悔しない生前対策|司法書士が「家族を守るための準備手順」を丁寧解説
結論からお伝えすると、生前対策は「何かあってから」では遅いことが多いです。
さぬき市では、認知症が進んでから初めて相談に来られ、「できる手続きがほとんど残っていない」というケースを多く見てきました。生前対策は、難しい法律の話ではなく、家族が困らないように準備する"思いやりの行動"です。この記事では、司法書士が実務経験をもとに、2026年時点で本当に大切な生前対策の進め方を、専門用語を使わず丁寧に解説します。
「登記が終われば一安心」
多くの方がそう思われますが、実はそれが落とし穴です。
香川県で相続登記に悩んだら|司法書士に相談すべきケースと無料相談の活用法【2026年版】
相続登記は、すべてのケースを自分で行う必要はありません。
むしろ、無理に進めて時間と費用を失う方が多いのが実情です。
本記事では、「相談すべきかどうか」の判断基準を明確にします。