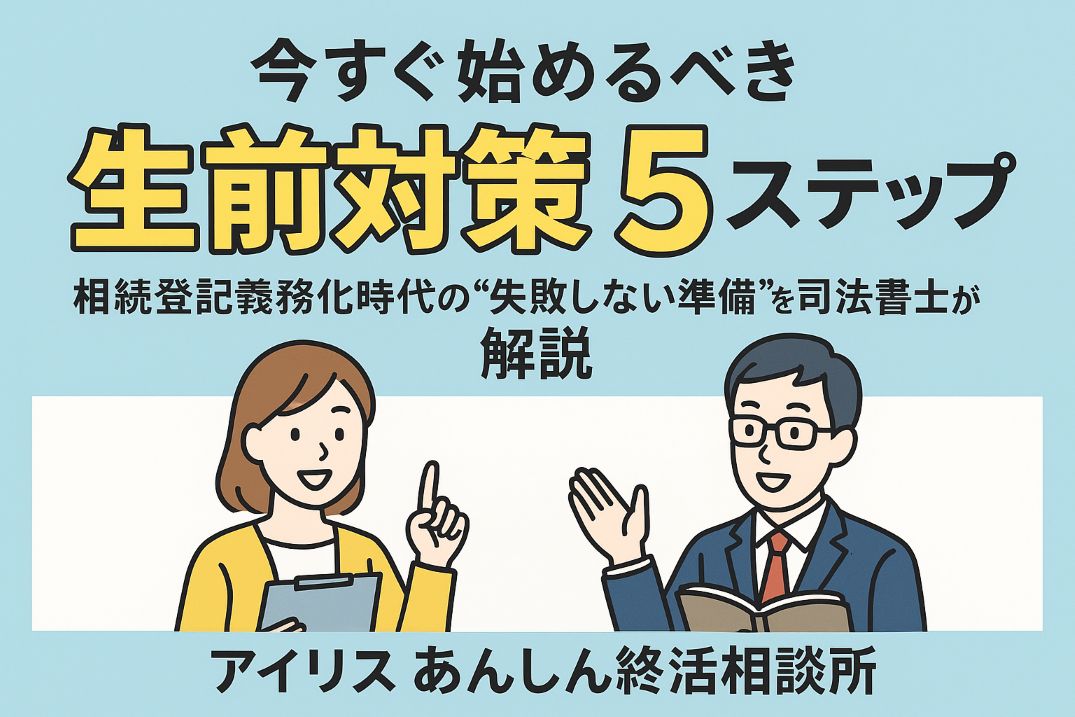香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
(論点)遺言書でできること

遺言書は、遺産分割において重要な役割を果たす文書です。法的効力を持つ遺言書を作成することで、遺産の分割に関する希望や指示を明確に示し、それを実現するための手段となります。しかし、遺言書だけで遺産分割を完全に決定できるわけではなく、いくつかの制約や条件が存在します。ここでは、遺言書が法的に効力を及ぼすことができる内容についてまとめます。
目次
1. 遺言書でできること
2. 遺言書でできないこと
3. 遺言書の作成と法的要件
4. まとめ
1. 遺言書でできること

遺言書には、以下のような事項を記載することができ、法的効力を持たせることが可能です。
1-1. 遺産分割方法の指定
遺言者は、遺産のどの部分を誰に渡すかを具体的に指定することができます。たとえば、不動産を特定の相続人に、現金や金融資産を別の相続人に渡すといった具体的な分配方法を遺言に記載することで、遺産の分割に関する意志を反映させることができます。このような遺言書は、法的に拘束力を持ち、基本的にその内容に従って遺産分割が行われます。
1-2. 遺言執行者の指定
遺言書では、遺産を実際に分割・管理する「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者は、遺言の内容に基づいて相続手続きや遺産の分配を行う役割を担います。遺言執行者が指定されている場合、その人が遺言に従って遺産分割を進める責任を負い、相続人間のトラブルを回避する助けとなります。
1-3. 相続人の廃除と認定
遺言書を通じて、特定の相続人を相続から廃除することができます。廃除の理由には、相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った場合などが該当します。廃除は家庭裁判所の審判が必要ですが、遺言書にその旨を記載することで手続きが開始されます。
1-4. 相続分の指定
遺言者は、相続人ごとの具体的な相続分を指定することができます。法定相続分に基づく分割が通常ですが、遺言書で異なる相続分を指定することで、法定相続分とは異なる分配が可能になります。ただし、相続人には遺留分(最低限の取り分)が保障されているため、遺言書がその遺留分を侵害しない範囲で効力を持ちます。
1-5. 特定の財産の処分
遺言書では、遺産の中でも特定の財産についてその処分方法を指定することが可能です。たとえば、家庭内で大切にされてきた絵画や土地などの具体的な財産を、誰に譲るかを遺言で指定することができます。このような個別の財産処分は、相続人間での不必要な争いを避けるために役立ちます。
2. 遺言書でできないこと

遺言書だけでできることには限界があります。以下は、遺言書が法的効力を及ぼさない、または制限される場合です。
2-1. 相続人全員の同意が必要な場合
遺言書に遺産分割方法が明記されていたとしても、相続人全員がその内容に同意しなければ、遺言書通りの分割が行われない場合があります。たとえば、遺言書に記載されていない財産や、遺言書が不明確な場合、相続人間で協議が必要になります。その協議の結果、遺言書とは異なる分割方法が採用されることもあり得ます。
2-2. 遺留分の侵害
遺言書によって相続人の相続分が指定された場合でも、相続人には「遺留分」という法定で保証された最低限の取り分があります。遺留分を侵害する遺言書は、その部分について無効となり、相続人が遺留分を請求することができます。特に、遺留分を侵害する場合、相続人間での争いの原因となる可能性があるため、遺留分を考慮した遺言書作成が重要です。
2-3. 共同相続における共有財産の処分
遺産が不動産などの共有財産となる場合、遺言書だけではその共有状態を解消することができません。共同相続人の合意が必要となるため、遺言書があるからといってすぐに共有物が分割できるわけではありません。この場合、遺産分割協議や裁判手続きが必要となることがあります。
3. 遺言書の作成と法的要件

遺言書が法的効力を持つためには、厳密な要件を満たす必要があります。遺言書には主に以下の形式があり、それぞれに法的な要件があります。
3-1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で記述し、署名押印することで成立します。ただし、遺言内容が不明確であったり、形式不備があった場合、無効になる可能性が高くなります。近年では、自筆証書遺言を法務局に預けることができる「法務局遺言書保管制度」が導入され、形式不備による無効リスクを低減する措置が取られています。
3-2. 公正証書遺言
公証人が作成する公正証書遺言は、もっとも安全かつ確実な方法とされています。遺言者が公証役場で遺言内容を伝え、公証人がその内容を公文書として記録します。公正証書遺言は、遺言者の死後、すぐに法的効力を持つため、相続人間での争いを回避しやすくなります。
4. まとめ
遺言書は、遺産分割に関して強力な法的手段であり、相続人間のトラブルを避け、被相続人の意思を尊重する重要な役割を果たします。ただし、遺言書だけで遺産分割がすべて完了するわけではなく、遺留分の問題や相続人間の合意が必要な場合もあります。遺言書を作成する際には、法的効力を持たせるための要件を理解し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

最新のブログ記事
多度津町で「生前対策・相続登記義務化」に備える──今すぐ始めるべきチェックリスト
2024年4月から、香川県多度津町でも不動産を相続した際の「相続登記」が義務化されました。不動産をお持ちの方は"いつまでに何をすべきか"を正しく理解しておかないと、過料や将来の管理トラブルにつながります。本記事では、多度津町の実情に合わせた生前対策と登記手続きの具体的なステップを司法書士がわかりやすく解説します。
徳島市で始める「失敗しない生前対策」―司法書士が教える“今日からできる備え方”
徳島市で生前対策を検討する方が増えています。背景には、高齢化による認知症リスク、県外在住の家族増加、空き家問題、相続登記義務化などの地域事情があります。本記事では、司法書士が「何から始めればいいか」を徳島市の実情に合わせて分かりやすく解説。今日からできるステップと失敗しない準備方法を紹介します。
鳴門市で「将来の不安を減らしたい」「家族に迷惑をかけたくない」と考えるなら、生前対策のスタートは早いほど安心です。本記事では、遺言書・家族信託・任意後見・不動産の名義整理など、鳴門市の地域事情にもとづき"いま何を準備すべきか"を5つのステップでやさしく解説します。