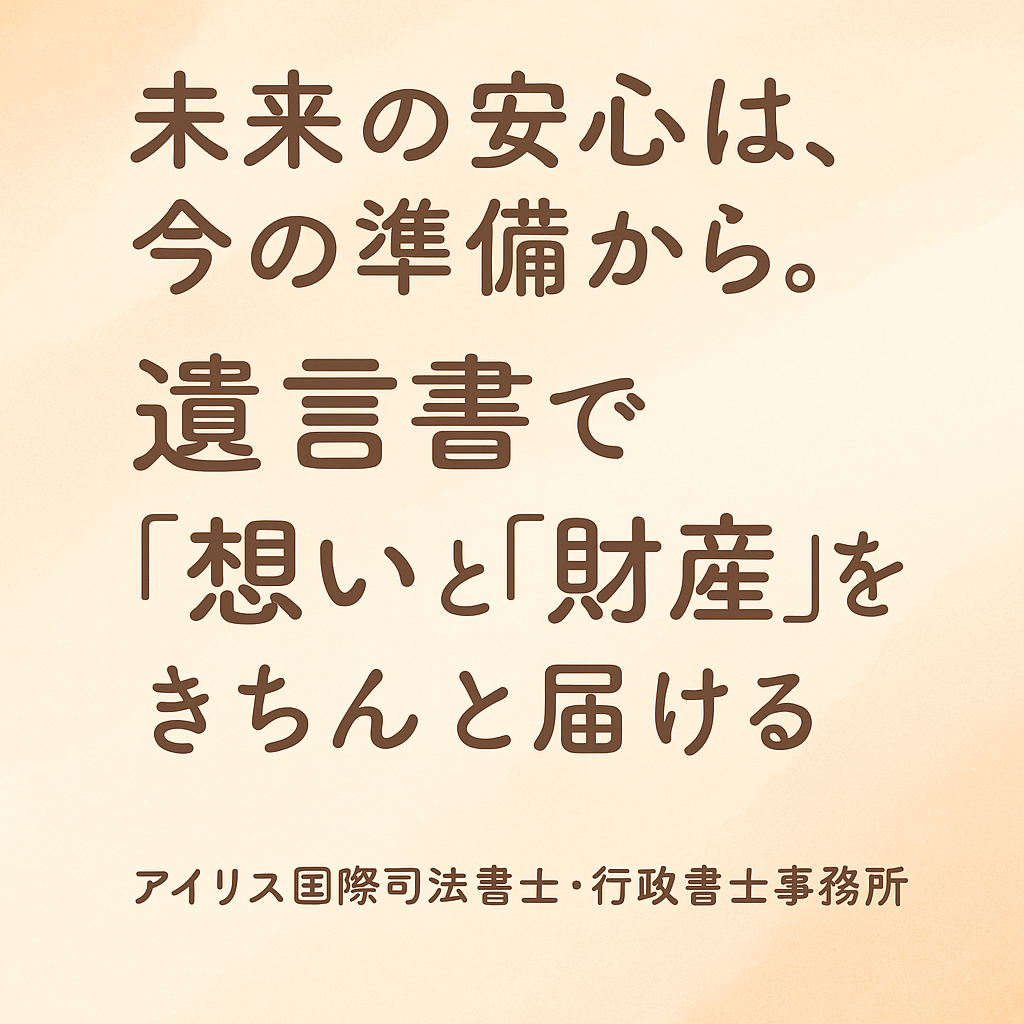香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
(論点)遺言書が必要な方

遺言書が必要な方とは、将来の相続に備え、自分の財産や遺産をどう分けるかを明確にしておきたい方のことを指します。特に以下のような状況にある方は、遺言書を作成することが重要です。
目次
1.家族構成が複雑な場合
2.配偶者や子供がいない場合
3.相続人同士の関係が悪い場合
4.事業承継が必要な場合
5.相続税対策を考えている場合
6.特定の人に財産を遺したい場合
7.遺産の分割が難しい場合
8.認知した子供がいる場合
まとめ
1.家族構成が複雑な場合

再婚や離婚を経験し、前配偶者との間に子供がいる場合や、配偶者や子供がいない場合など、家族構成が複雑な方は、遺産分割の際にトラブルが発生するリスクが高まります。遺言書がなければ、法律に基づいた相続分が適用されますが、それが必ずしも自分の意向に沿ったものとは限りません。たとえば、前妻との子供にどれくらいの遺産を分けるのか、現妻や後妻との間の子供にはどのように分配するのかを明確にすることで、家族間の争いを防ぐことができます。
2.配偶者や子供がいない場合
配偶者や子供がいない場合、法律上の相続人は兄弟姉妹や甥・姪になることが多いです。しかし、これらの相続人と疎遠な場合や、特定の人や団体に財産を残したいという希望がある場合には、遺言書を作成しておくことが必要です。遺言書がなければ、親族に自分の意向と反する形で財産が渡ることになります。
3.相続人同士の関係が悪い場合

相続人同士がすでに不仲である場合や、将来的に相続争いが起こる可能性がある場合は、遺言書を作成しておくことで、あらかじめ自分の意向を明確にしておくことができます。特に、不動産や事業の分割など、争いになりやすい財産がある場合には、遺言書を通じて具体的な分割方法を示すことが重要です。
4.事業承継が必要な場合

中小企業や自営業を営んでいる方にとって、遺言書は事業承継の重要な手段となります。会社の経営者が突然亡くなった場合、相続人間での経営権を巡る争いが起こることがあります。これを防ぐためには、遺言書で後継者を指定し、円滑な事業承継を図ることが求められます。
5.相続税対策を考えている場合
遺産の総額が大きく、相続税の課税対象になる場合、遺言書を作成しておくことで、相続税の負担を軽減するための対策を講じることができます。例えば、法定相続人に分ける以外に、財産の一部を寄付することなども有効な手段です。また、特定の相続人により多くの財産を渡す場合にも、その分の相続税をあらかじめ計算し、納税に備えておくことができます。
6.特定の人に財産を遺したい場合
法律上の相続人ではない人に財産を遺したい場合や、特定の相続人に多くの財産を残したい場合は、遺言書が必要です。例えば、内縁の配偶者や、長年面倒を見てくれた友人に財産を渡したい場合など、法律では認められない相続を実現するためには、遺言書で明確にしておく必要があります。
7.遺産の分割が難しい場合
不動産や株式、骨董品など、遺産の分割が難しい資産を持っている方は、遺言書で誰に何を相続させるのかを明示しておくことで、相続人間の争いを避けることができます。不動産を複数人で共有するのは管理が難しく、売却が必要になるケースも多いため、遺言書で適切な分配を指定しておくことが重要です。
8.認知した子供がいる場合
認知した子供がいる場合、遺言書でその子供の相続分を明確にしておくことが重要です。認知した子供には法定相続権がありますが、他の相続人との公平を図るために、遺言書で相続分を指定しておくことで、後の争いを防ぐことができます。
まとめ
総じて、遺言書を作成することで、相続に関する自分の意向を反映させ、家族間の争いを防ぐことができます。また、相続税や事業承継といった問題にも対処できるため、早めの準備が推奨されます。遺言書は、自分の死後の財産の行方を決定する重要な手段であり、適切に作成しておくことで、自身と家族の安心を確保することができます。
遺産分割協議で、結局まとまらず、その後、調停そして審判まで行くケースの原因の多くが上記の例です。該当する方は専門家に相談することをお勧めいたします。また、期限も存在します。それは、遺言者が認知症になる前です。

最新のブログ記事
【第3回】バブル期の持ち家信仰と個人債務の拡大
1980年代後半、日本は未曾有の好景気「バブル経済」に突入し、人々の間には「持ち家こそが成功の証」という信仰が広がりました。この背景には、土地神話や住宅ローンの普及、税制優遇などがありましたが、無理なローンを組んで購入した住宅は、後に多くの家庭に経済的負担を残す結果となりました。本記事では、バブル期の持ち家信仰がいかにして個人債務を拡大させ、現在の相続や空き家問題の伏線となったのかを掘り下げます。
【第3回】財産の“棚卸し”をしよう──遺言書に書くべきもの・書かない方がいいもの
遺言書を作成するうえで最も重要なのが、財産の内容を正確に把握することです。不動産や預貯金だけでなく、相続トラブルの原因となる「意外な財産」も棚卸しが必要です。この記事では、書くべき財産と書かない方がいいケース、注意点を具体例とともに解説します。
【第2回】農地改革・財閥解体と財産分散の加速
戦後の日本社会において、財産のあり方は劇的に変化しました。GHQの主導による農地改革や財閥解体は、富の集中を排し、個々人への分散を意図した施策でしたが、その結果として、かつての地主層や資産家層は急速に衰退していきました。本記事では、これらの政策がもたらした財産構造の変化と、現代の相続問題への影響について掘り下げます。