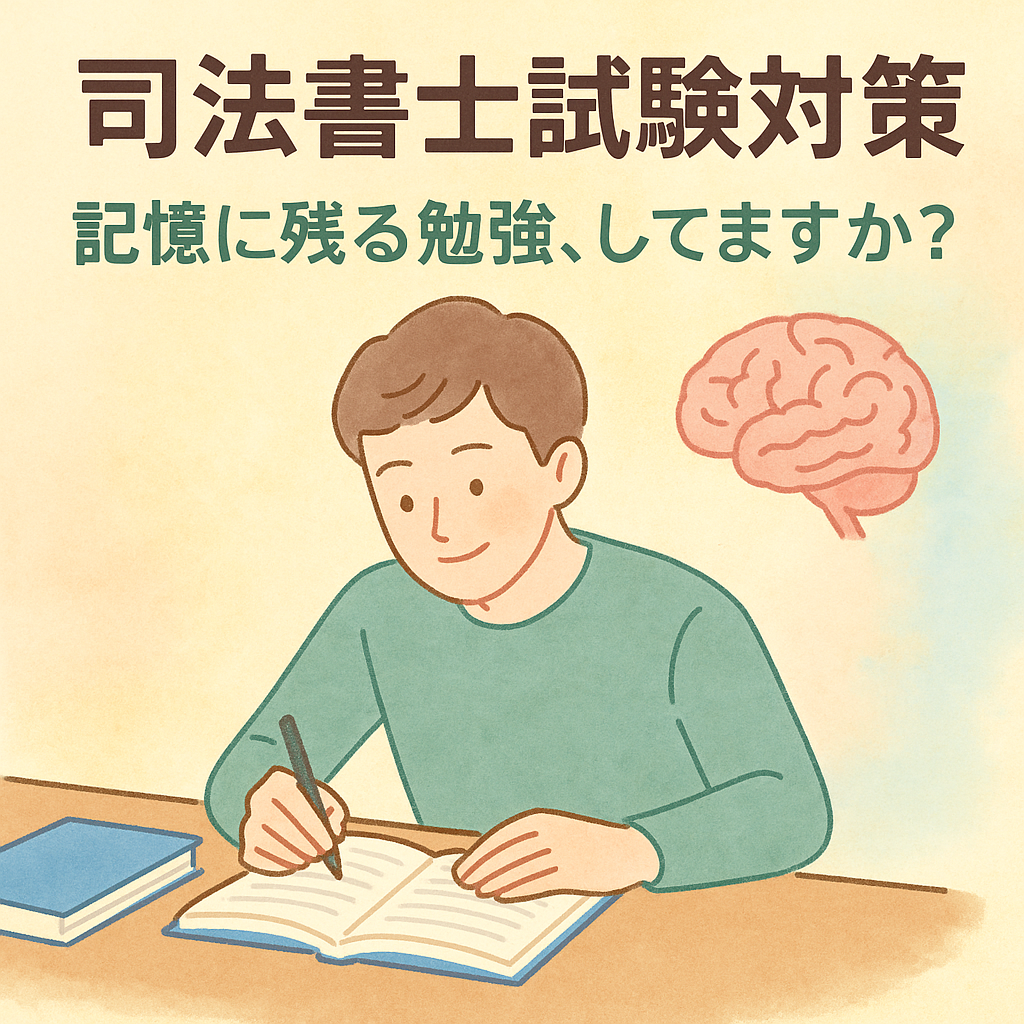香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
(論点)遺産分割協議書作成のコツ(手続き後に遺産を発見した場合の条項)

遺産分割協議を進める際には、被相続人の財産を正確に把握することが重要です。通常、遺産分割協議の前に行う「遺産調査」では、被相続人の名義となっている財産のすべてを確認することが求められます。しかし、どれだけ慎重に調査を行っても、全ての財産を網羅できないことがあります。特に、不動産に関しては、被相続人が所有している財産が思いがけない場所に存在していることがあるため、その把握が難しく、遺産として漏れてしまうこともあります。この場合、遺産分割協議書にどのような対策をしておけば、当該遺産分割協議書を用いて、後に発見された不動産の手続きもできるのかについて解説したいと思います。
目次
1. 遺産調査の重要性
2. 不動産調査の難しさ
3. 新たな財産発見に備える条項の必要性
4. 再協議の手間を省くメリット
5. 相続人間のトラブル防止
6. 条項を追加する際の注意点
まとめ
1. 遺産調査の重要性

遺産分割協議を行う前提として、被相続人の全財産を正確に把握することが必要です。遺産調査を行い、すべての財産を明らかにすることで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。しかし、どれだけ慎重に調査を行っても、財産が漏れるリスクがあります。
2. 不動産調査の難しさ
不動産の調査は特に複雑で、役場から「固定資産評価証明書」を取得することで被相続人名義の不動産を確認できますが、その役場の管轄内の不動産しか調べることができません。他市町村に不動産がある場合、その市町村で別途調査が必要です。また、被相続人が思いがけない場所に不動産を所有しているケースもあり、そうした場合には財産が漏れてしまう可能性があります。
3. 新たな財産発見に備える条項の必要性

遺産分割協議書に「すべての相続人は、個々に記載された以外の被相続人所有の不動産があった場合は、相続人〇〇が相続し、取得することに異議はないものとする」という条項を追加することで、遺産分割協議が完了した後に新たな財産が見つかった場合でも、その財産をスムーズに相続できるようになります。この条項があると、再協議の手間を省き、相続手続きが簡略化されます。
4. 再協議の手間を省くメリット
通常、遺産分割協議後に新たな財産が発見されると、再度協議を行う必要がありますが、この条項を入れておくことでその必要がなくなります。これにより、時間や労力を節約できるだけでなく、相続手続きを迅速に進めることが可能です。
5. 相続人間のトラブル防止
この条項があることで、後から発見された財産に対して相続人間での新たなトラブルを避けることができます。特に高額な不動産や希少な資産が発見された場合、その取り扱いを巡って相続人間で争いが生じることが少なくありません。事前に取り決めを設けることで、相続人間の信頼関係を守り、スムーズな相続手続きを進めることができます。
6. 条項を追加する際の注意点
条項を追加する際には、相続人全員がその内容に同意していることが重要です。相続人の中には、後から発見された財産について新たに協議を希望する者がいるかもしれません。そのため、遺産分割協議書作成時に、専門家から十分な説明を受け、相続人全員が納得した上で押印することが不可欠です。
まとめ
遺産分割協議書に「記載されていない財産が発見された場合、その取得に異議はない」とする条項を追加することで、相続手続きを円滑に進め、トラブルを未然に防ぐことができます。相続人同士の関係を守りつつ、複雑な手続きを回避するためにも、この条項の導入は効果的です。専門家と相談しながら、相続手続きをスムーズに進める準備を整えておくことが大切です。

最新のブログ記事
(司法書士試験合格への新戦略)学習の再現性を高めるアプローチ
司法書士試験は、法律系資格の中でも特に難易度が高く、合格率も低いことで知られています。多くの受験生が独学や予備校を利用して学習を進めていますが、合格への道のりは決して平坦ではありません。本記事では、従来の学習法とは異なる視点から、司法書士試験の攻略法を探ります。特に、学習の再現性を高める方法や、試験科目の本質的な理解を深める方法について解説します。これから司法書士試験を目指す方や、現在学習中の方にとって、新たな気づきや学習のヒントとなることを目指します。
【第6回】遺留分トラブルを避ける!事業承継と家族の権利をどう両立するか?
中小企業の事業承継で最も見落とされがちなのが、「遺留分」への配慮です。自社株式を後継者だけに集中させる遺言や生前贈与を行った結果、他の相続人から遺留分侵害額請求が起こるケースは後を絶ちません。
事業の継続と家族の感情のバランスをどうとるかは、承継対策において極めて重要なテーマです。本記事では、遺留分の基礎知識からトラブル事例、回避のための遺言・契約・特例制度の活用法まで、実践的な解決策を詳しく解説します。
【第5回】事業承継で株式を贈与するときに知っておくべき3つの税務ポイント
中小企業の事業承継において最も重要な資産が「株式」です。会社の経営権をスムーズに移すためには、自社株の贈与や譲渡をどう扱うかが鍵になります。しかし、株式の贈与には相続税とは異なる"贈与税"の高い壁が立ちはだかります。
この記事では、自社株式を子や後継者に贈与する際に注意すべき**税務上の3つのポイント(評価・時期・特例)**を解説しながら、節税しつつ確実に承継を進めるための実践的な対策を紹介します。