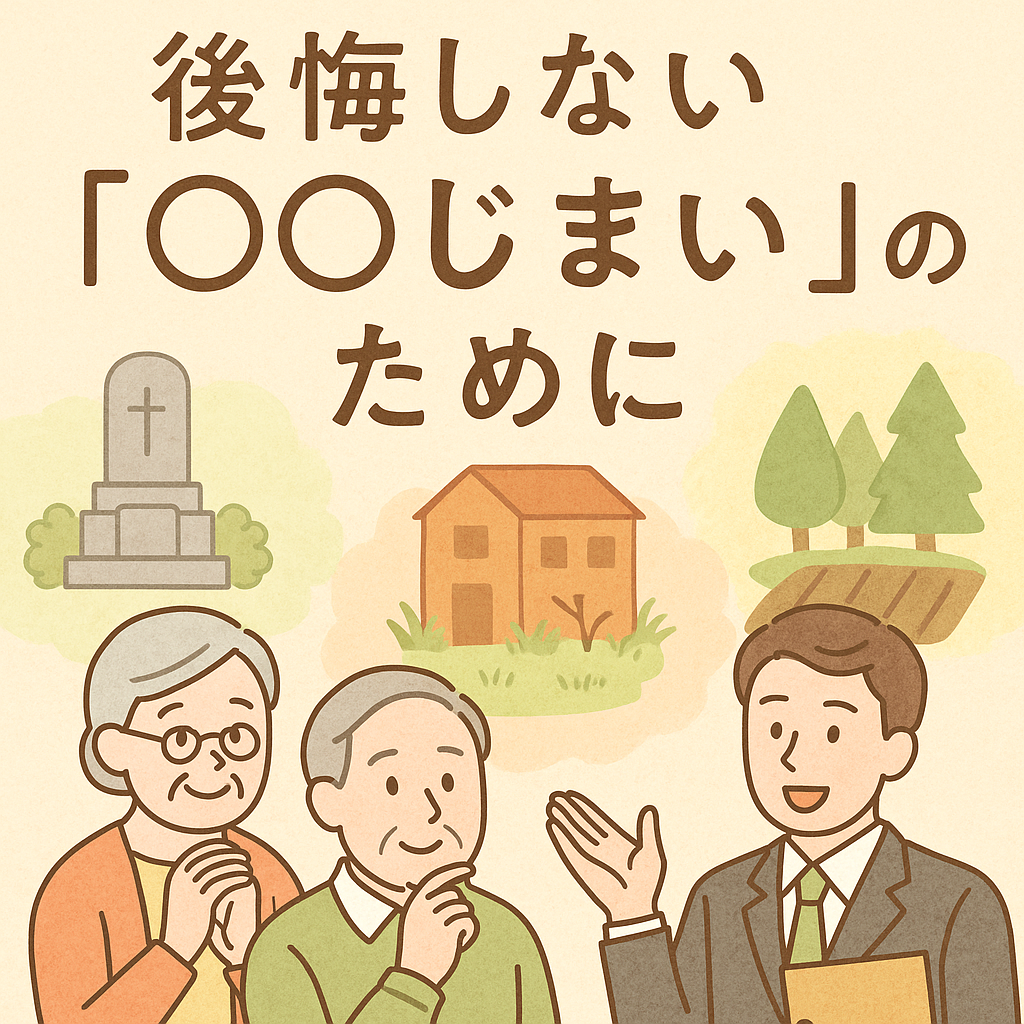香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
(論点)相続登記の可否について(遺産の農地について)

相続について、今一度確認しておきます。民法896条「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」とあります。遺産に含まれる不動産について、各ケースについて考え、相続登記の要否・可否について解説したいと思います。
目次
1.農地の売主に相続発生
2.農地法の許可を停止条件とする仮登記がある場合
3.仮登記が存在する場合で、すでに相続登記がある場合
4.それでは、農地法許可申請前に売主が死亡した場合
5.農地法の許可到達前に買主が亡くなった場合
1.農地の売主に相続発生

「農地の売主が死亡した後、農地法3条の許可があった場合には、その農地の相続登記を経た後でなければ、買主への所有権移転の登記をすることはできない。」(昭40.3.30民三309号)
①売買契約(売主甲、買主乙)
➁甲死亡(甲の子丙へ相続登記)
③乙に対する農地法3条許可発行(売買を原因とする丙から乙への所有権移転登記)
このケースでは、①から③の順序で登記をしなければなりません。なぜなら、農地法の許可が所有権移転の対抗要件である以上、その許可前に相続が発生すると、丙が当該農地をいったん取得することになるためです。しかし、丙は甲の所有権移転義務・登記移転義務を承継していますので、その後、丙から乙への所有権移転登記を行うことになります。
2.農地法の許可を停止条件とする仮登記がある場合
前の事例では、許可待ちの状態でしたが、今回の事例では、農地法の許可を条件に仮登記を実施している点が異なります。「仮登記」というキーワードが出てきましたので、説明いたします。
(仮登記)「不動産登記における所有権移転の仮登記とは、所有権の移転が未確定の段階で、将来的に所有権が移転する可能性があることを第三者に対して公示するための登記手続きです。通常、仮登記は本登記が行われるまでの一時的な措置として利用されます。たとえば、不動産売買契約が締結されたが、売買代金の全額がまだ支払われていない場合や、登記原因証明情報が未完備である場合などに、所有権移転の仮登記が行われます。仮登記をしておくことで、後日正式な登記がなされた際に、仮登記の順位に基づいて効力が発生するため、登記権利者の権利保全に役立ちます。ただし、仮登記には本登記に比べて制約があり、第三者への対抗力が限定されるため、最終的には本登記を行うことが重要です。」
それでは、今回のように農地法の知事の許可を停止条件とする仮登記がすでに登記されている場合、許可が発行され仮登記に基づく本登記をする場合、許可前に所有権登記名義人が死亡している時でも、「本登記を前提として、相続登記をすることを要しない。(昭35.5.10民三328号)
この先例は、本来は、相続登記をしてから本登記をすべきですが、その場合せっかく実施した相続登記はすぐに抹消されることになるため、便宜、相続登記の省略を認めたものです。
3.仮登記が存在する場合で、すでに相続登記がある場合
順位1番で甲が名義人となっており、順位2番で甲から乙への所有権移転仮登記の後、順位3番で甲の子丙への相続登記がある場合を考えます。
農地法の許可が到達した時点で、丙と乙が順位2番の仮登記に基づく本登記をすることになります。この本登記がなされた場合、順位3番の相続登記は、職権(登記官の権限により)で抹消されることになります。(登研576号)
4.それでは、農地法許可申請前に売主が死亡した場合
農地法の許可申請前に売主が亡くなった場合ですので、許可を申請する当事者の一方がすでにいないわけです。ですので、相続登記を行い、この相続人と買主とで、農地法の許可を申請し、手続きを進めていくことになります。
5.農地法の許可到達前に買主が亡くなった場合
この場合、すでに亡くなっている買主への許可は無効であり、買主の相続人が当該許可を証する情報を提供して所有権移転登記を申請しても受理されません。(昭51.8.3民三第4443号)。なぜなら、亡くなった買主について農業適格者としての許可証が、農地法の許可に当たり、亡くなった買主の相続人が農業適格者の判断は、当該許可証では行われていないために、無効という扱いとなります。この場合は、改めて売主と買主の相続人とで許可申請をやり直す必要があります。

最新のブログ記事
近年、「墓じまい」「家じまい」「店じまい」「土地じまい」といった"〇〇じまい"という言葉を耳にする機会が増えました。
高齢化や少子化、単身世帯の増加といった社会構造の変化により、これまで「家族が引き継ぐのが当たり前」とされていたものを、「自分の代で終わらせる」という選択をする人が増えているのです。
【第4回】「“正しさ”に振り回されないために」〜自分軸で生きるヒント〜
「何が正しいのか分からない」
「自分の意見を言うのが怖い」
「つい他人の価値観に合わせてしまう」
【第3回】「正論マウント」への対処法〜心をすり減らさないために〜
「正しいことを言っているんだから、受け入れるべき」――そんな態度に心が疲れてしまったことはありませんか?
それは、いわゆる「正論マウント」を取られている状態かもしれません。