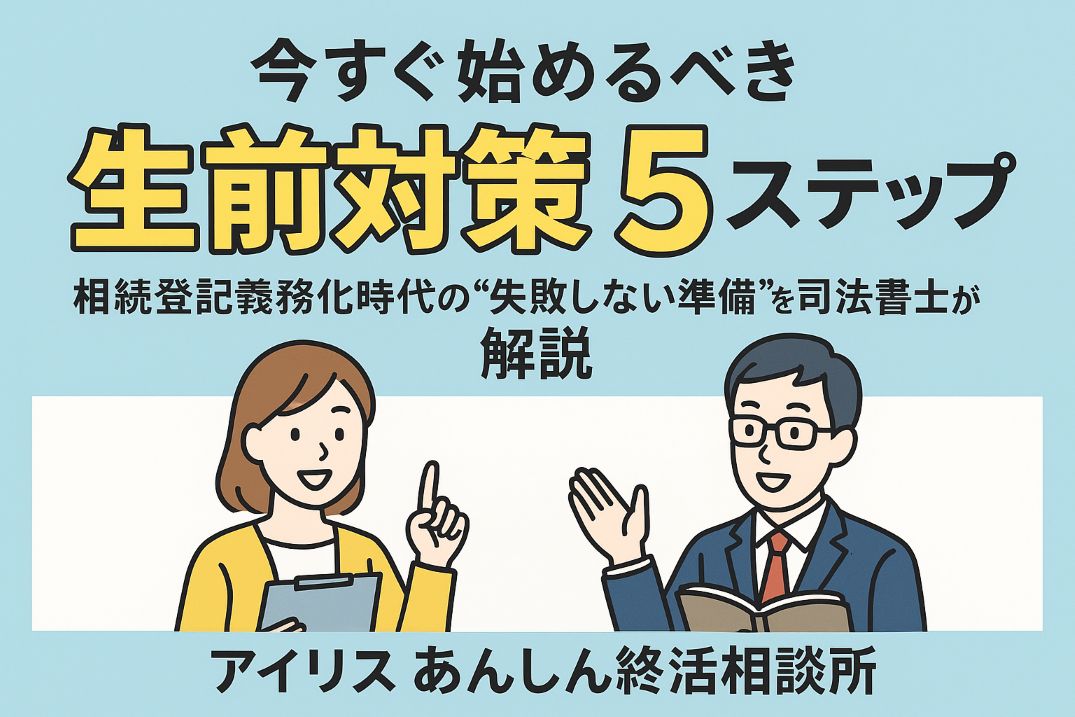香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
(論点)相続人申告登記をするには(必要書類と意外な使い方)

令和6年4月1日に相続登記が義務化されました。義務化の罰則は、最大10万円以下の過料です。この過料を免れるためには、相続登記を申請するか、正当な理由がある場合には、相続人申告登記をすることとなります。この「相続人申告登記」について、解説していきたいと思います。
目次
1.相続人申告登記とは
2.相続人申告登記に必要な書類
3.相続人申告登記の意外な使い方
4.まとめ
1.相続人申告登記とは

相続人申告登記とは、相続によって不動産の所有権が移転した場合に、法定相続人がその事実を法務局に申告し、不動産登記を行う手続きです。この制度は、2024年4月1日に施行された「不動産登記法の一部を改正する法律」により新設され、相続登記が義務化された背景のもと、登記手続きを簡便化し、相続による不動産所有権の変動を適切に記録することを目的としています。
相続人申告登記は、相続登記義務化の罰則である過料を免れることができます。過料が科せられない正当な理由とは、以下の通りです。
「(1) 相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
(2) 相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3) 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合」(法務省HP引用)
今後、遺産分割協議をする予定だが、現状もめていて話が進まないような場合、義務化の期限である3年以内に相続登記ができないような場合、申出人から「相続人申告登記」を入れておけば、当該申出人については、罰則の過料は免れます。
2.相続人申告登記に必要な書類
「一般的に、
ア.(被相続人と申出人の戸籍等)

①被相続人(死亡した方)の死亡した日が分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)
②申出人が被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書
③被相続人の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書
が必要になります。
1通の証明書で①~③を満たす場合には、その証明書の添付で足ります。」(法務省HP引用)
例えば、申出人である配偶者・子が除籍謄本に含まれている場合などです。
「イ.(登記簿上の名義人と被相続人の住所を証明する書類)
被相続人(死亡した方)の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合や被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には、被相続人が登記名義人(登記記録上の所有者)であることが分かる被相続人の本籍の記載のある住民票の除票又は戸籍の表示の記載のある戸籍の附票の写し等が必要となります。」(法務省HP引用)
※他のHPで、この書類が含まれていないケースがありました。登記システム上では、本人の特定を「氏名」と「住所」の一致で行います。そのため、最後の住所地と登記簿上の住所地が異なっている場合、住民票の除票で証明することになりますが、子の住民票の除票には「前住所」までしか記載されていません。そのため、「登記簿上の住所」と、「亡くなった住所地」とのつながりを除票では証明できない場合、「戸籍の附票」が必要となってきます。
「ウ.(申出人の住民票の写し(原本))
申出人の住民票の写し(原本)です。住民票上の申出人の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合は、提出する必要はありません。なお、住民票の写しを提出する場合は、マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを取得し提出してください。 また、申出人の現在の住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提出するか、その法定相続情報番号(法定相続情報一覧図の写しの右上に記載された番号)を申出書に記載することで、住所証明情報の添付に代えることができます。」(法務省HP引用)
※申出人も相続人申告登記の情報となりますので、申出人の住民票の写しを添付します。
3.相続人申告登記の意外な使い方

とある方から聞いた話ですが、とある相続人の方が他の相続人と遺産分割協議をすることを打診したのですが、全く連絡をよこさないといったことがあったようです。今後、態度が軟化することも期待できないため、相談に来られた相続人を申出人とする、相続人申告登記を申請し、3年後に過料徴収の通知がなされたときに、遺産分割協議を相手方が打診してくるのを待つ、という使い方をされている方がいるようでした。
ただし、相手方次第となりますので、本当に遺産分割協議ができるかどうかはわかりません。現状が膠着しているような場合なら、確率は低いと思うのですが、効果があるかもしれませんね。
4.まとめ
相続人申告登記をすることで、相続登記義務化の罰則である過料を免れることができます。相続人申告登記に必要な書類は、「被相続人の除籍謄本」「被相続人と申出人の関係を証する戸籍謄本」「被相続人の最後の住所地と登記簿謄本上の住所の一致を証する住民票の除票の写し又は戸籍の附票」「申出人の現在戸籍」「申出人の住民票の写し」となります。
アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)

また、別事務所で「相続法律・税務無料相談会」を月1回実施しております。こちらは完全予約制になっておりますので、必ず事前に電話で予約状況を確認の上、予約を確定してください。

最新のブログ記事
多度津町で「生前対策・相続登記義務化」に備える──今すぐ始めるべきチェックリスト
2024年4月から、香川県多度津町でも不動産を相続した際の「相続登記」が義務化されました。不動産をお持ちの方は"いつまでに何をすべきか"を正しく理解しておかないと、過料や将来の管理トラブルにつながります。本記事では、多度津町の実情に合わせた生前対策と登記手続きの具体的なステップを司法書士がわかりやすく解説します。
徳島市で始める「失敗しない生前対策」―司法書士が教える“今日からできる備え方”
徳島市で生前対策を検討する方が増えています。背景には、高齢化による認知症リスク、県外在住の家族増加、空き家問題、相続登記義務化などの地域事情があります。本記事では、司法書士が「何から始めればいいか」を徳島市の実情に合わせて分かりやすく解説。今日からできるステップと失敗しない準備方法を紹介します。
鳴門市で「将来の不安を減らしたい」「家族に迷惑をかけたくない」と考えるなら、生前対策のスタートは早いほど安心です。本記事では、遺言書・家族信託・任意後見・不動産の名義整理など、鳴門市の地域事情にもとづき"いま何を準備すべきか"を5つのステップでやさしく解説します。