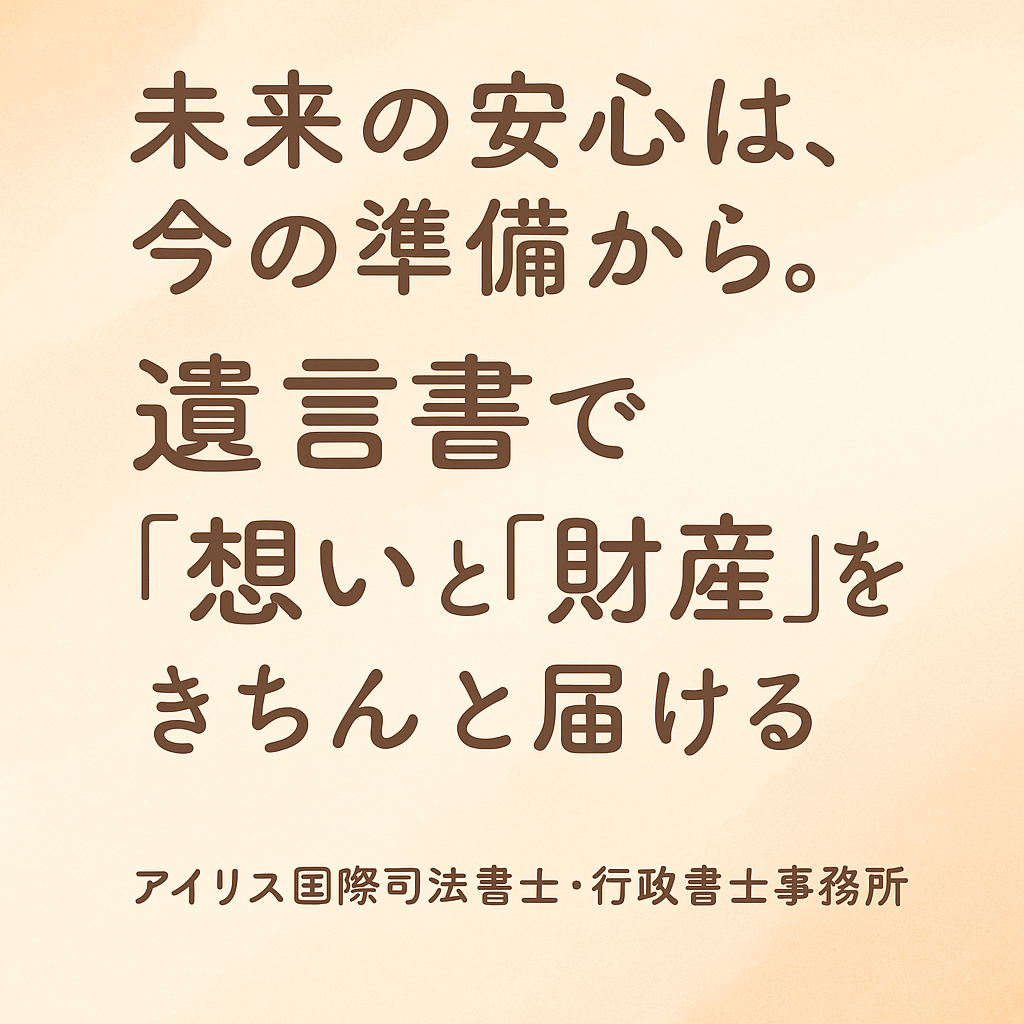香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
(論点)相続できないものとは

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や権利義務を、相続人が引き継ぐことです。一般的には、土地や建物、現金、株式などの財産を想像することが多いですが、実際には相続できるものとできないものが存在します。相続できないものについて理解しておくことは、相続手続きを円滑に進めるために重要です。本稿では、被相続人の財産の中で相続できないものについて説明します。
目次
1. 一身専属権
2. 生命保険金
3. 年金
4. 一部の損害賠償請求権
まとめ
1. 一身専属権

まず、相続できないものとして代表的なのが「一身専属権」です。これは被相続人の個人的な権利や義務であり、その人自身に密接に関連しているため、他人が引き継ぐことができないものです。一身専属権には次のようなものがあります。
※プロミュージシャンの子供が、コンサートやってもチケット買った人たちの債務履行とはなりませんよね。
(1) 身分関係に基づく権利義務
被相続人の身分に直接関連する権利や義務は、相続することができません。たとえば、親権、後見人としての権利義務、婚姻関係に基づく権利などは、一身に帰属するものであり、被相続人が亡くなった時点で消滅します。具体的には、次のようなものが該当します。
親権: 親が子供に対して有する親権は、親の死亡に伴い消滅します。親権は新たな親権者や後見人が家庭裁判所によって選任されるため、相続の対象にはなりません。
後見人としての義務: 法定後見や任意後見の後見人は、被後見人に対して責任を負いますが、後見人が死亡した場合、その義務は相続されず、新たな後見人が選任されます。
婚姻関係に基づく権利義務: 婚姻に基づく扶養義務や配偶者としての権利義務も相続の対象にはならず、被相続人の死亡により婚姻関係は終了します。
(2) 委任契約
被相続人が生前に行っていた業務委任契約や、弁護士や税理士などとの委任契約も相続されません。これらは被相続人自身の信頼に基づく契約であり、被相続人が死亡すると契約は終了します。もっとも、委任契約のうち未払いの報酬などについては相続の対象となる場合があります。
(3) 労務に基づく権利
被相続人が労働者として勤務していた場合、その労働契約も死亡によって終了します。労務の提供は個人に依存するものであり、相続の対象にはなりません。たとえば、給与や労働時間に関する権利は被相続人が持つものであり、死亡時点で契約は終了します。ただし、未払いの給与や退職金は相続財産として扱われることがあります。
2. 生命保険金
生命保険金は被相続人の死亡に伴い支払われるものですが、通常、保険金受取人が指定されている場合、生命保険金は受取人固有の権利として扱われます。そのため、生命保険金は相続財産には含まれません。具体的には次のような場合があります。
保険契約: 保険契約者(被相続人)が死亡した際、保険金受取人として指定された人が生命保険金を受け取ります。この場合、生命保険金は受取人の財産となり、相続財産には含まれません。
税務上の取扱い: 税務上は、生命保険金は相続税の課税対象となることがありますが、それでも相続財産とは区別され、受取人に直接支払われます。
ただし、生命保険金が過剰な額である場合や特定の相続人に対して偏った支給が行われた場合、他の相続人が異議を唱え、裁判所で「特別受益」として考慮されることもあります。この場合、相続財産の一部として評価される可能性があります。

3. 年金
年金も相続の対象外となります。年金は被相続人の生存に基づいて支給されるものであり、死亡した時点でその権利は消滅します。公的年金や企業年金など、被相続人が生前に受給していた年金は、基本的に死亡とともに支給が停止されます。
未支給年金: 被相続人が死亡する前に年金が支払われていなかった場合、その分は未支給年金として遺族が請求できる場合があります。この場合、相続財産とは別に遺族が直接受け取る形となり、相続の対象には含まれません。
4. 一部の損害賠償請求権
被相続人が損害賠償請求をしている場合、その請求権は相続の対象になることがありますが、例外的に相続できないものもあります。たとえば、慰謝料請求権がこれに該当します。被相続人が生前に被った精神的苦痛に対する慰謝料は、基本的にその人個人に帰属する権利であり、相続の対象とはなりません。ただし、すでに裁判が進行中で、慰謝料が確定している場合は相続されることがあります。
一方で、財産的損害に対する賠償請求権は相続されることが一般的です。たとえば、交通事故による財産的損害や、契約違反による損害賠償請求は相続財産として扱われます。
5. 公的な資格や地位
被相続人が有していた公的な資格や地位も相続の対象外です。たとえば、弁護士、医師、公認会計士などの資格は個人の能力や信頼に基づくものであり、これを相続することはできません。また、被相続人が公職に就いていた場合、その地位も死亡に伴い消滅します。
まとめ
相続できないものには、被相続人個人に強く結びついた一身専属権や、生命保険金、年金、そして公的な資格や地位などがあります。これらは個人的な権利や義務であり、他人に引き継ぐことができないため、相続財産として扱われません。また、一部の損害賠償請求権や慰謝料なども相続の対象外となる場合があります。
相続手続きを行う際には、どの財産が相続可能でどの権利が相続できないのかを理解することが重要です。

最新のブログ記事
【第2回】他人の物差しで生きない勇気──あなたの「正解」は他人とは違っていい
現代社会では、「正解」があらかじめ決まっているかのような風潮があります。学歴、収入、職業、結婚、マイホーム…。それらを満たしてこそ「成功」と見なされ、そこから外れると「負け組」とラベルを貼られる。しかし本当に、他人と同じ価値観の中で生きなければならないのでしょうか?この記事では、「他人の物差しに縛られて苦しい」と感じている方へ向けて、自分自身の価値観を取り戻すためのヒントをお伝えします。
【第1回】「世の中がおかしい」と思える自分を信じる──違和感は生きる力の証
昨今の日本社会では、政治への不信感、経済格差の拡大、将来の不安など、暗いニュースが続いています。自殺者数や失業者数の増加も深刻な社会課題となっており、もはや「自己責任」と一言で片づけられる時代ではなくなりました。この記事では、「この社会はどこかおかしい」と感じている方に向けて、その違和感こそが健全な感性であり、生きる力の根源であるという視点から、希望を持って生きていくための第一歩を探っていきます。
【第5回】遺言書があることで、こんなに変わる!実例で学ぶ“残された人の安心”
「遺言書なんて、うちには関係ない」と思っていませんか?実際には、遺言書の有無で相続手続きの手間や家族間のトラブルの発生率は大きく異なります。本記事では、遺言書があったケースとなかったケースの比較を通して、"遺された人の安心"につながる具体的な効果をご紹介します。