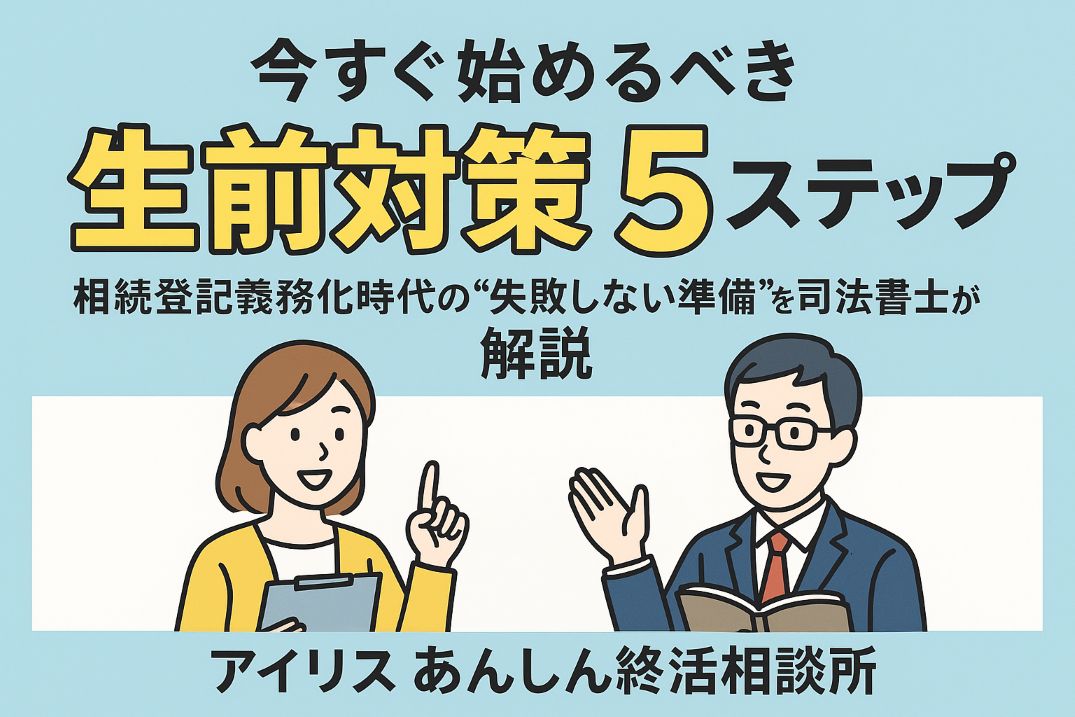香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
(論点)成年後見人の遺産分割協議への参加

相続人の中に成年後見人がついている場合、遺産分割協議について、当該相続人の法定代理人として、成年後見人が参加して行うことになります。成年後見人が遺産分割協議に参加するにあたり注意すべき点がいくつかありますので解説していきたいと思います。
目次
1.家庭裁判所の許可が必要か?
2.被後見人の利益を最優先
3.利益相反の回避
4.適切な専門家の助言
5.遺産分割協議書の作成と確認
6.透明性の確保
7.まとめ
1.家庭裁判所の許可が必要か?

成年後見人が判断能力を欠いている相続人(本人)に代わり、遺産分割協議に参加する場合は、家庭裁判所の許可は不要です。しかし、家庭裁判所と相談しながら本人の利益を守る観点から、協議内容に問題がないか判断した方が良いでしょう。判所の許可入りませんが、事前に相談等をしておいた方が、後のトラブル回避にもつながります。なにより、後見人には善管注意義務があり、被後見人の権利を守ることが職務だからです。
ただし、遺産分割を行った場合は、その結果を裁判所への定期報告の際に報告する必要があります。
2.被後見人の利益を最優先

先にも書いた通り、成年後見人には善管注意義務があります。そして、成年後見人の最も重要な役割は、被後見人の利益を保護することです。遺産分割協議においても、被後見人の権利や利益が最大限に保護されるようにする必要があります。適切な分割が行われるよう、注意深く協議内容を検討し、不利な条件を避けることが求められます。
以上のために、「後見人は被後見人の法定相続分の財産を確保しなければいけない」ことになります。法定相続分は、成年被後見人の保証された権利ですので、その確保が求められるわけです。3. 利益相反の回避
ですので、合理的な理由がない場合や、合理的な理由があっても裁判所が認めてくれない場合には、代理人として本人(被後見人)が法的に有する権利(法定相続分)を相続放棄したり、不当に少ない相続分で合意したりすることはできません。
3.利益相反の回避
遺産分割協議には複数の相続人が関与するため、利益相反の問題が生じる可能性があります。成年後見人が他の相続人の利益と被後見人の利益との間で板挟みになることがないよう、利益相反を避けるための措置が必要です。必要に応じて、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てることも考慮すべきです。
このような状況が生じるケースは、司法書士や弁護士が成年後見人ではなく、親族(相続人の一人)が、成年後見人になっている場合です。親族成年後見人の場合には、利益相反の注意が必要です。
4.適切な専門家の助言

専門家が成年後見になっている場合には、問題となることは少ないと思いますが、親族成年後見人の場合ですと、法律の知識が乏しいため、専門家のサポートを要することがあります。遺産分割の手続きは法的に複雑であるため、弁護士や司法書士などの専門家の助言を受けることが重要です。成年後見人が正確かつ適切に手続きを進めるためには、専門家のサポートが不可欠です。
5.遺産分割協議書の作成と確認
遺産分割協議がまとまった場合、その内容を遺産分割協議書として文書化する必要があります。この文書には全相続人の署名と捺印が必要です。成年後見人は被後見人に代わって署名を行いますが、内容をしっかり確認し、被後見人に不利益がないようにすることが重要です。
6.透明性の確保
遺産分割協議の過程および結果は、透明性を保つことが重要です。成年後見人は、被後見人や関係者に対して適切な説明を行い、協議内容が明確かつ公正であることを示す必要があります。
7.まとめ
成年後見人が遺産分割協議に参加する際には、被後見人の利益を最優先ることが不可欠です。また、利益相反の回避、専門家の助言の活用、協議書の適切な作成、透明性の確保が求められます。これらの注意点を踏まえ、慎重に手続きを進めることが重要です。

最新のブログ記事
多度津町で「生前対策・相続登記義務化」に備える──今すぐ始めるべきチェックリスト
2024年4月から、香川県多度津町でも不動産を相続した際の「相続登記」が義務化されました。不動産をお持ちの方は"いつまでに何をすべきか"を正しく理解しておかないと、過料や将来の管理トラブルにつながります。本記事では、多度津町の実情に合わせた生前対策と登記手続きの具体的なステップを司法書士がわかりやすく解説します。
徳島市で始める「失敗しない生前対策」―司法書士が教える“今日からできる備え方”
徳島市で生前対策を検討する方が増えています。背景には、高齢化による認知症リスク、県外在住の家族増加、空き家問題、相続登記義務化などの地域事情があります。本記事では、司法書士が「何から始めればいいか」を徳島市の実情に合わせて分かりやすく解説。今日からできるステップと失敗しない準備方法を紹介します。
鳴門市で「将来の不安を減らしたい」「家族に迷惑をかけたくない」と考えるなら、生前対策のスタートは早いほど安心です。本記事では、遺言書・家族信託・任意後見・不動産の名義整理など、鳴門市の地域事情にもとづき"いま何を準備すべきか"を5つのステップでやさしく解説します。