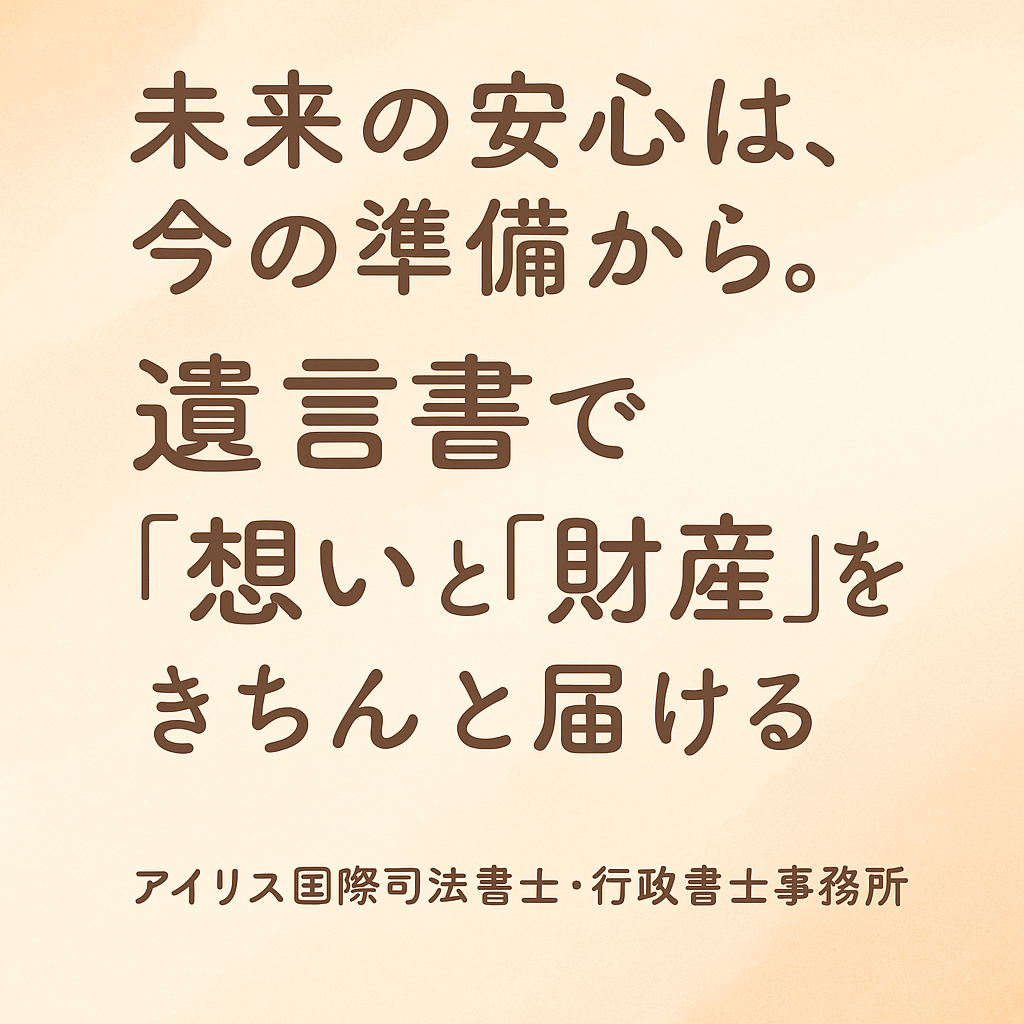香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
(論点)家族信託が利用されなくなってきた理由

家族信託が出始めたころには、夢のような制度として脚光を浴びましたが、利用が進むにつれて、その問題点も浮き彫りになってきて、「後見制度に代わる」制度ではないことが明らかになってきました。そもそも、財産管理の方法を契約で当事者同士でするものが家族信託で、家庭裁判所の管理下で行うものが後見制度です。その目的も財産管理という名目は同じでも内容は全く違うものです。現状、家族信託はそこまで浸透していない様に見えます。その原因を紐解いてみました。
目次
1. 家族信託の概要
2. 受託財産の管理が大変(信託口口座による管理)
3. 委託者への報告を怠っているケースが多い
4. 税務署に対する報告ができていないケースが多い
5. どこからクレームが来るのか
6. 家族信託に対する誤解や過信
1. 家族信託の概要

家族信託とは、委託者(通常は親)が受託者(通常は子供)に財産を信託し、将来、委託者が認知症などで判断能力を失った場合でも、信託契約に基づいて財産を管理・運用する仕組みです。この制度は、特に高齢者の認知症対策として広く利用されていました。信託契約によって、受託者が委託者の代わりに財産を管理できるため、親族間の紛争を防ぐことが期待されていました。
2. 受託財産の管理が大変(信託口口座による管理)

家族信託の利用が減少している理由の一つとして、受託財産の管理の煩雑さが挙げられます。信託財産を管理するためには、信託専用の口座(信託口口座)を開設する必要がありますが、金融機関によってはこの信託口口座を開設してくれない場合があります。このような場合、受託者は信託財産の管理が難しくなり、管理業務が大きな負担となります。特に高齢の受託者にとっては、この管理作業が複雑で負担が大きいため、家族信託の利用を敬遠する要因となっています。
3. 委託者への報告を怠っているケースが多い

信託契約では、受託者が委託者に対して定期的に財産の管理状況を報告する義務がありますが、現実にはこれが十分に行われていないケースが多いです。家族間での信頼関係があるために、受託者が報告を怠りがちで、信託の透明性が損なわれるリスクがあります。このような状況では、信託が適切に機能していないと見なされる可能性があり、家族信託の効果が十分に発揮されないことがあります。
4. 税務署に対する報告ができていないケースが多い
家族信託を利用する場合、信託財産に関する税務申告が必要ですが、多くの受託者がこの義務を十分に理解していません。そのため、確定申告時に信託財産を正しく申告できていないケースが多く見られます。税務署への報告が不十分な場合、後に税務署から指摘を受けたり、追徴課税が発生したりするリスクがあります。信託財産が大規模であるほど、税務管理が重要となり、適切な申告がなされていないことで、信託制度全体の信頼性が損なわれる結果となっています。
5. どこからクレームが来るのか
家族信託は、委託者と受託者の間で締結される契約ですが、管理される財産は最終的に相続人の遺産となります。そのため、他の相続人が受託者の管理方法に疑義を抱いた場合、クレームが発生することが多くあります。特に信託財産が大きい場合や、相続人間で利害関係が複雑な場合には、これが紛争に発展することもあります。受託者が信託の内容を適切に管理し、透明性を確保していないと、家族間の関係が悪化するリスクが増加します。
6. 家族信託に対する誤解や過信
家族信託が普及し始めた当初、一部の専門家や業者が「家族信託を利用すれば、後見制度は不要になる」といった誤った情報を提供していたケースがありました。しかし、家族信託と後見制度は異なる制度であり、家族信託を利用しても後見制度が不要になるわけではありません。このような誤解が広まった結果、家族信託に対する過信が生まれ、制度の限界に直面する利用者が増えました。これにより、家族信託の利用が見直され、結果として利用者が減少する要因となっています。
これらの理由により、最近では家族信託の利用が減少しています。家族信託は有用な制度ですが、その管理の煩雑さや税務管理の重要性、そして相続人間の関係に注意しながら慎重に利用することが求められます。

最新のブログ記事
【第2回】他人の物差しで生きない勇気──あなたの「正解」は他人とは違っていい
現代社会では、「正解」があらかじめ決まっているかのような風潮があります。学歴、収入、職業、結婚、マイホーム…。それらを満たしてこそ「成功」と見なされ、そこから外れると「負け組」とラベルを貼られる。しかし本当に、他人と同じ価値観の中で生きなければならないのでしょうか?この記事では、「他人の物差しに縛られて苦しい」と感じている方へ向けて、自分自身の価値観を取り戻すためのヒントをお伝えします。
【第1回】「世の中がおかしい」と思える自分を信じる──違和感は生きる力の証
昨今の日本社会では、政治への不信感、経済格差の拡大、将来の不安など、暗いニュースが続いています。自殺者数や失業者数の増加も深刻な社会課題となっており、もはや「自己責任」と一言で片づけられる時代ではなくなりました。この記事では、「この社会はどこかおかしい」と感じている方に向けて、その違和感こそが健全な感性であり、生きる力の根源であるという視点から、希望を持って生きていくための第一歩を探っていきます。
【第5回】遺言書があることで、こんなに変わる!実例で学ぶ“残された人の安心”
「遺言書なんて、うちには関係ない」と思っていませんか?実際には、遺言書の有無で相続手続きの手間や家族間のトラブルの発生率は大きく異なります。本記事では、遺言書があったケースとなかったケースの比較を通して、"遺された人の安心"につながる具体的な効果をご紹介します。