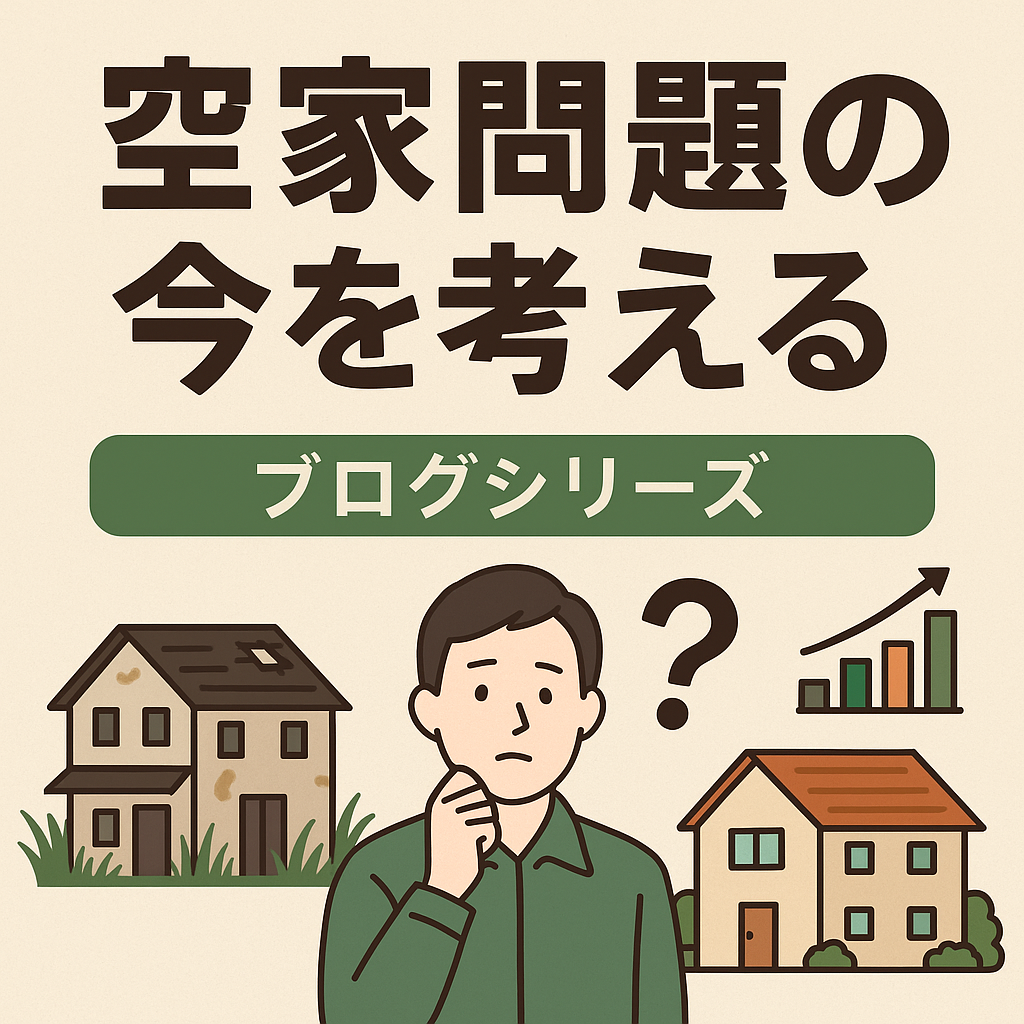香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
(論点)「全財産を愛人に遺贈する」と書かれた遺言書が発見!

遺言書が見つかり、その内容が「全財産を愛人に遺贈する」と記載されていた場合、相続人としてはショックを受けることでしょう。しかし、このような場合でも適切に対処する方法があります。以下に、その手順とポイントを詳しく説明します。
目次
1. 遺言書の確認と検認
2. 遺留分の確認と請求
3. 遺留分侵害額請求の手続き
4. その他の対応策
まとめ
1. 遺言書の確認と検認

まず、遺言書が正式なものであるかを確認します。遺言書の種類に応じて、検認が必要な場合があります。
公正証書遺言:公証人によって作成された遺言書であれば、検認は不要です。
自筆証書遺言・秘密証書遺言:これらの場合、家庭裁判所での検認が必要です。検認は遺言書の形式的な有効性を確認する手続きであり、内容の有効性を判断するものではありません。
2. 遺留分の確認と請求
民法には「遺留分」という制度があります。遺留分は、一定の相続人(配偶者、子供、直系尊属など)が最低限相続できる財産の割合を保障するものです。遺留分の割合は以下の通りです:
配偶者と子供がいる場合:配偶者と子供それぞれが相続財産の1/4を遺留分として持つ。
配偶者と直系尊属がいる場合:配偶者が1/3、直系尊属が1/6。
子供のみの場合:子供が相続財産の1/2を遺留分として持つ。
「全財産を愛人に遺贈する」という遺言書が見つかった場合、遺留分を侵害している可能性が高いです。この場合、相続人は遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を行うことができます 。
3. 遺留分侵害額請求の手続き
遺留分侵害額請求を行うためには、以下の手順を踏みます。
3.1 請求の意思表示
遺留分を侵害された相続人は、相手方(愛人)に対して遺留分侵害額請求の意思表示を行います。この意思表示は、口頭でも書面でも可能ですが、証拠を残すために書面で行うのが一般的です。内容証明郵便を利用することで、意思表示の事実と日時を明確に証明できます。
※裁判をしないと主張できないという方がいらっしゃいますが、遺留分侵害額請求権の行使は、裁判上でも裁判外でも可能です。
3.2 調停・仲裁
意思表示後、当事者間で話し合いが行われますが、合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停では中立的な第三者が介入し、合意に向けた調整が行われます 。
3.3 裁判
調停が不成立の場合、最終的には裁判に進むことになります。裁判では、遺留分の具体的な金額や支払い方法について判決が下されます 。
4. その他の対応策

4.1 遺言無効訴訟
遺言書の内容や作成過程に不正があった場合(例えば、遺言者が精神的に不安定な状態であった、あるいは脅迫や詐欺によって作成された場合)、遺言無効訴訟を提起することができます。この訴訟では、遺言の無効を証明するための証拠を提出する必要があります。
4.2 和解
愛人との間で話し合いが可能であれば、相続人の遺留分を尊重しつつ、遺産の一部を愛人に分与する形で和解を図ることも考えられます。これにより、法的手続きにかかる時間と費用を節約することができます。
5. 専門家への相談
相続問題は複雑で感情的なものが多いため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家は法的なアドバイスを提供し、適切な手続きをサポートしてくれます。
まとめ
「全財産を愛人に遺贈する」という遺言書が見つかった場合、遺留分を侵害している可能性が高いです。相続人は遺留分侵害額請求を行うことで、自身の権利を守ることができます。適切な手続きを踏み、必要に応じて専門家に相談することで、相続問題を円滑に解決することが可能です。
まずは、争いも想定されますので、はじめから弁護士と相談の上、手を打って行った方がいいと思います。

最新のブログ記事
【第2回】空き家を放置するとどうなる?〜法的・経済的リスクを徹底解説〜
「空き家を放置しているとどうなるの?」「相続した実家が空き家のままになっているけど、何か問題ある?」
そんな声が最近増えています。実は、空き家を放置していると、法律上の責任や税金の増加、売却の困難化など、さまざまなリスクに直面する可能性があります。
遺言書って必要?残された家族がもめないために
「うちには大した財産がないから遺言なんていらない」と思っていませんか?実は遺言書がないことで、家族がもめるケースは香川県でも多くあります。本記事では、遺言書の役割や必要性、香川県でよくある事例を司法書士がやさしく解説します。
【第1回】なぜ空き家が増えるのか? 〜現状と背景を読み解く〜
「空き家問題」「空き家の増加」「空き家のリスク」といったキーワードが、ニュースや自治体の広報紙などで頻繁に登場するようになりました。
日本全国で年々増加している空き家は、地域の景観悪化や防災・防犯の面でも深刻な問題を引き起こしています。では、なぜこれほどまでに空き家が増え続けているのでしょうか?