香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
(マーケティング)漠然とした不安を具体的な課題に変える「問題の重心」アプローチ
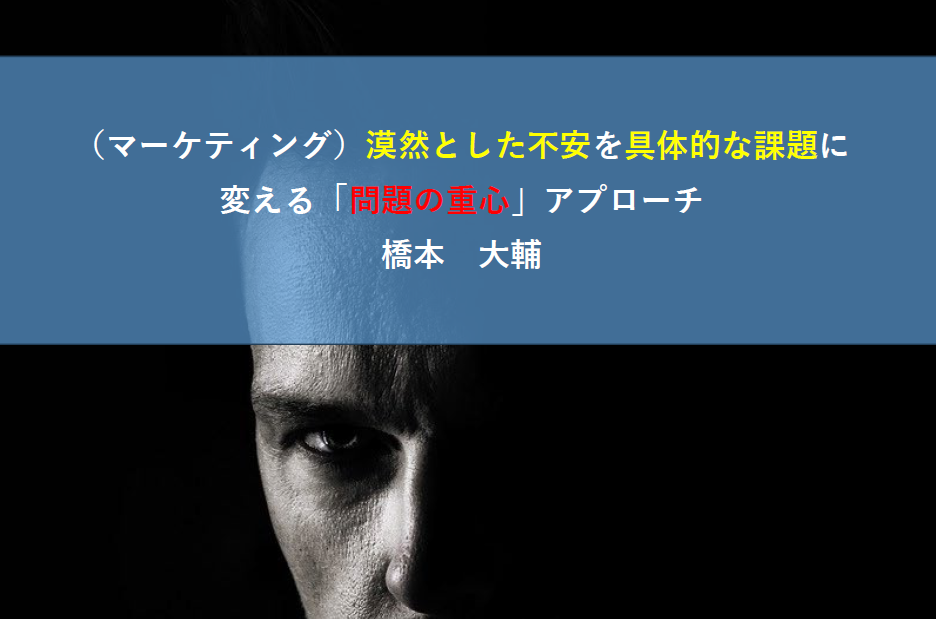
私たちは日々、漠然とした不安や悩みに直面します。将来への漠然とした不安、仕事や人間関係の悩み、具体的な解決策が見えないまま抱え込んでしまう問題──これらは誰もが経験するものです。しかし、これらの不安をそのままにしていても、状況は改善されません。大切なのは、不安を具体的な課題へと変換し、解決に向けたアプローチを見出すことです。ここでは、どのようにして漠然とした不安を課題に落とし込み解決に導くのかについて述べたいと思います。
目次
- はじめに
- 漠然とした不安を具体的な課題に変換する方法
- 2.1. 不安の棚卸し
- 2.2. 課題の明確化
- 「問題の重心」の特定とその重要性
- 3.1. 問題の重心とは
- 3.2. 重心を見つけるためのアプローチ
- 行動計画の策定と実行
- 4.1. SMART目標の設定
- 4.2. PDCAサイクルの活用
- ケーススタディ:森岡毅氏の実践例
- 結論
1. はじめに

現代社会において、多くの人が漠然とした不安や悩みを抱えています。これらの不安は抽象的であるため、具体的な解決策を見出すことが難しいことがあります。そこで、これらの不安を明確な課題として捉え、効果的に解決するための手法が求められています。
2. 漠然とした不安を具体的な課題に変換する方法
2.1. 不安の棚卸し
まず、自身が抱える不安や悩みをリストアップします。この作業は、自分の感情や思考を客観的に見つめ直すための第一歩です。書き出すことで、不安の全体像が明確になり、次のステップへと進みやすくなります。
2.2. 課題の明確化

リストアップした不安の中から、解決可能なものや優先度の高いものを選別します。各不安に対して、「なぜそれが不安なのか」「どのように解決すれば安心できるのか」を深掘りし、具体的な課題として定義します。
3. 「問題の重心」の特定とその重要性

3.1. 問題の重心とは
「問題の重心」とは、多くの問題が関連し合う中で、一つの問題を解決することで他の多くの問題も同時に解決できる、核心となる問題のことを指します。この重心を特定することで、効率的かつ効果的な問題解決が可能となります。
3.2. 重心を見つけるためのアプローチ
- 因果関係の分析: 問題間の因果関係を明確にし、どの問題が他の問題に影響を与えているかを把握します。
- フィッシュボーンダイアグラムの活用: 問題の原因を視覚的に整理し、重心となる問題を特定します。
- 5W1Hの適用: 問題に対して「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どのように」の視点で問いかけ、核心に迫ります。
4. 行動計画の策定と実行
4.1. SMART目標の設定
問題の重心を特定した後は、その解決に向けた具体的な目標を設定します。SMART目標とは、以下の5つの要素を持つ目標設定法です。
- Specific(具体的): 目標が明確で具体的であること。
- Measurable(測定可能): 進捗や成果が測定できること。
- Achievable(達成可能): 現実的に達成可能な範囲であること。
- Relevant(関連性): 自身の価値観や長期的目標と関連していること。
- Time-bound(期限設定): 達成までの期限が明確であること。
4.2. PDCAサイクルの活用
行動計画を実行する際は、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回すことで、継続的な改善を図ります。計画を立て、実行し、結果を評価し、必要な改善策を講じることで、目標達成に向けた効果的な行動が可能となります。
5. ケーススタディ:森岡毅氏の実践例
森岡毅氏は、マーケティング戦略家として数多くの成功事例を持ちます。彼のアプローチでは、漠然とした市場の不安やニーズを具体的なデータと分析で明確化し、その中から「問題の重心」を特定して戦略を立案します。例えば、新商品の販売戦略を策定する際、市場調査データから消費者の核心的なニーズを抽出し、そのニーズに応える商品特性を開発することで、他の関連する問題も同時に解決する戦略を展開しています。
6. 結論
漠然とした不安を具体的な課題に変換し、その中から「問題の重心」を特定して行動することで、効率的かつ効果的な問題解決が可能となります。森岡毅氏のアプローチは、ビジネス戦略だけでなく、個人の問題解決にも応用できる有用な手法と言えるでしょう。

最新のブログ記事
【2026年版】高松市の生前対策|遺言・信託・ライフプランで決める“あなたの安心設計”指南
生前対策は「相続の準備」ではなく、**これからの人生をどう生きるかという"設計図"です。
結論として、高松市の生前対策は、遺言・信託・任意後見を"ライフプランに合わせて組み合わせる"ことが最適解です。
本記事では、2026年時点の実務に基づき、安心設計の考え方をお伝えします。
【2026年版】香川県で失敗しない生前対策とは?|司法書士が実務・制度・手続きまで徹底解説
香川県で「生前対策」を考えたとき、最も重要なことは "実務として何を、いつまでに、どうすればよいか" を正確に理解することです。
2024年4月に始まった相続登記の義務化により、"対策しないことが家族の損失・リスクになる時代" になりました。
この記事では、司法書士の視点で 制度・法律・手続き・実例まで具体的に解説し、他の記事では書かれていない「失敗しない実務ライン」を整理します。
【2026年版】善通寺市で失敗しない生前対策|弁護士・司法書士が伝える実務ノウハウ
結論から言えば、生前対策の成否は「手段の選択」ではなく、「順序と専門家の関与」で決まります。
善通寺市でも、遺言・家族信託・任意後見といった制度を"部分的に"導入した結果、かえって手続きが複雑化するケースが後を絶ちません。本記事では、2026年時点の法制度を前提に、弁護士・司法書士の実務経験から、生前対策を失敗させないための考え方と具体的プロセスを整理します。




