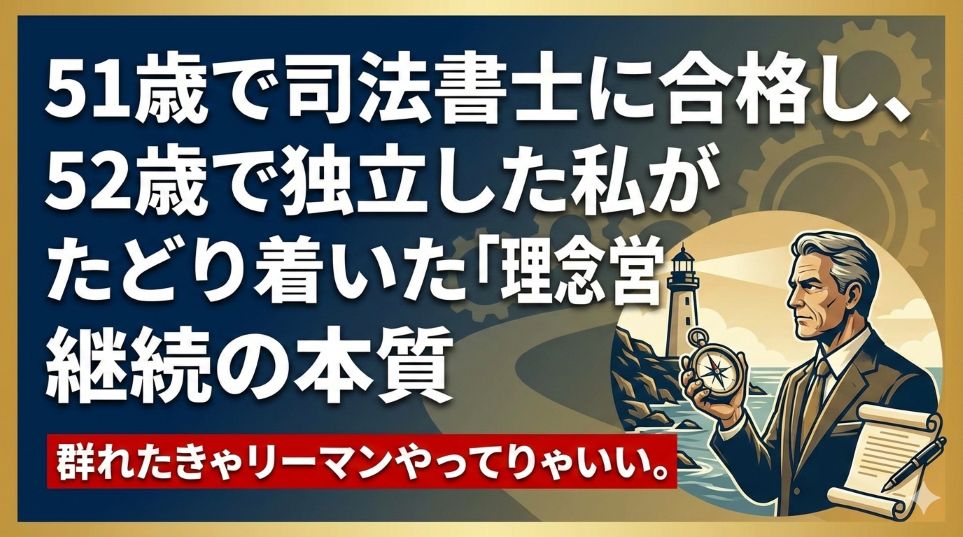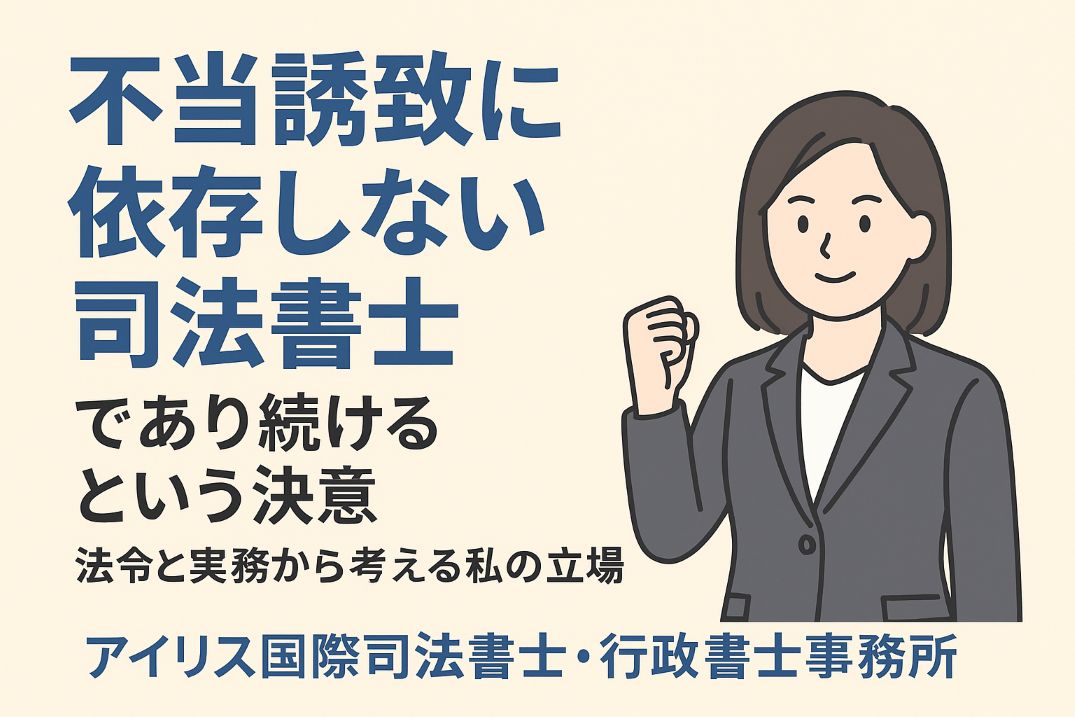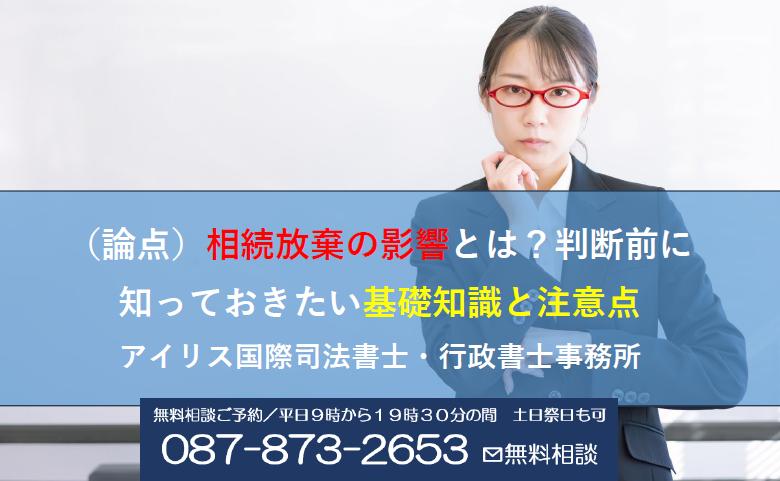香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
遺言書作成のススメ(平均寿命と健康寿命)
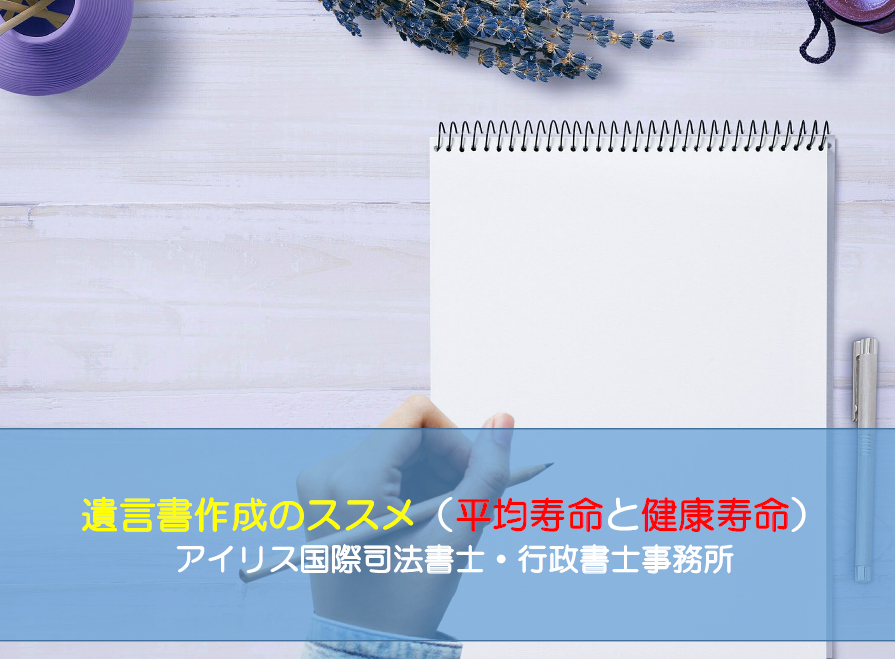
自筆証書遺言で自宅保管である場合にはそれほど体力を使いませんが、法務局保管をしたり、公正証書遺言をする場合には、法務局、公証役場に出向くのに体力が必要となります。元気なうちに対策をしていただきたいのですが、その年齢って何歳なのでしょうか。解説していきます。
目次
1.遺言書がなぜ必要
2.なぜ70歳になったら遺言書なのか
3.まとめ
1.遺言書がなぜ必要
2024年(令和6年)の相続登記義務化により、今後、相続登記に関する問題が浮上する可能性が非常に高くなっています。現に、私が市役所の無料相談会に参加した際に、相談件数は通常の倍、しかもその9割以上が相続に関連するものでした。
それでは、遺言書を作成するメリットについて解説いたします。
相続登記をする際に、遺言書がない場合、「遺産分割協議」を相続人全員で行い、その内容をまとめた遺産分割協議書に相続人全員が記名・実印で押印し全員分の印鑑証明書の添付が要求されます。生前、離婚した妻の子供や疎遠になった親族が相続人になることがあります。遺産分割協議自体が困難になるケースも多くの相談者の方で見てきました。
この遺産分割協議は、遺言書があればその遺言書の内容に応じて相続登記が可能なんです。残されたご家族の負担が大きく軽減されるといっても過言ではありません。
2.なぜ70歳になったら遺言書なのか
遺言書の作成するのは、もちろん親になります。日本人の平均寿命からすると、男性81.47歳、女性87.57歳(2021年厚生労働省)です。まだまだ大丈夫なんじゃないのと思われるかもしれません。
しかし、ご高齢者になると、司法書士や公証役場に出向くことは、それなりに負担が大きいのです。元気なうちに遺言書の作成をする必要性があるのです。
支障なく日常生活ができるとされる健康寿命は、男性72.68歳、女性75.38歳(2019年厚生労働省)です。意外と短いということがわかります。
※健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」(厚生労働省)
さらに年齢が進むと認知症発症のリスクが増加します。グラフを見ますと70歳代後半から認知症発症の割合が、それまでと比べて増加していることがわかります。

3.まとめ
このように、遺言をするにも健康状態や認知症のリスクといったことを考慮する必要性が出てきます。相談者の中にも90歳で遺言を書きたいと言って来訪される方もいますが、公正証書遺言をするにも労力と公証人の質問に的確に答えられなければ、難しいと思います。自筆証書遺言ですと、相続発生後、相続人間でもめた場合、その遺言書が判断能力を理由に無効にされるかもしれません。
早めの遺言書対策が、残されたご家族の負担を軽減いたします。ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。

最新のブログ記事
51歳で司法書士に合格し、52歳で独立した私がたどり着いた「理念経営」と継続の本質
私は51歳で司法書士試験に合格し、52歳で自分の事務所を構えました。
人生初の経営者。仕事は来ない、正解は分からない、不安と焦りの連続。
それでも今日まで事務所を継続できているのは、**「理念を明文化し、昨日の自分と比較し続けてきた」**からです。
この記事では、私自身の受験・独立・経営の実体験を通して、「継続できる経営」とは何かを正直にお伝えします。
「不当誘致に依存しない司法書士」であり続けるという決意——法令と実務から考える私の立場
司法書士業界では以前から「誘致」に関する問題が指摘されてきました。最近では、弁護士向けの違法な集客スキームが摘発されるニュースもあり、法曹業界全体で"外部業者による不当な関与"が注目されています。
私が運営するアイリス国際司法書士・行政書士事務所では、開業以来、外部の広告サービスや案件紹介を一切利用していません。本記事では、その背景と私自身の考え方を、司法書士法施行規則および行為規範の趣旨と照らしながら整理します。
(論点)相続放棄の影響とは?判断前に知っておきたい基礎知識と注意点
相続が発生した際、借金や負の財産が多い場合に「相続放棄」という選択肢を検討する方も少なくありません。しかし、相続放棄は一度手続きを行うと取り消すことができず、また他の相続人や周囲の人間関係にも思わぬ影響を及ぼすことがあります。この記事では、「相続放棄の影響」について、制度の概要から、判断に迷いやすいポイント、放棄後の生活や他の相続人への影響まで、分かりやすく解説します。相続放棄を検討している方、親族の死後に借金の請求を受けた方、または司法書士・弁護士に相談する前に基本知識を整理したい方におすすめの内容です。