相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年8月21日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
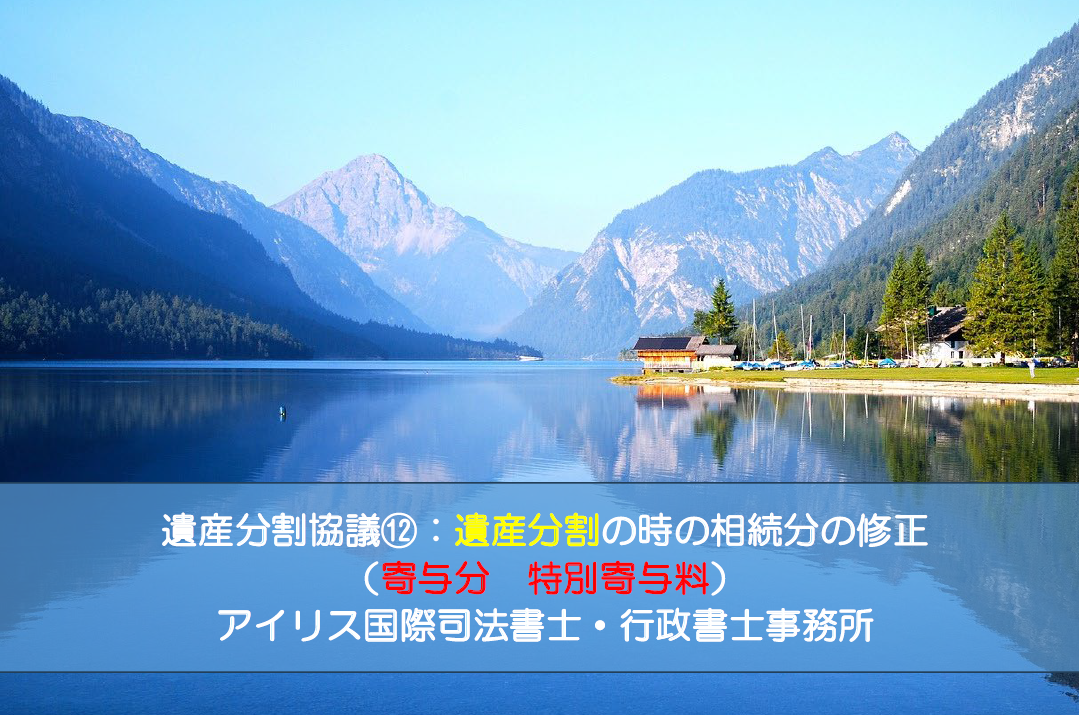
今まで遺産分割時の相続分の修正として、特別受益についてお話をしてきましたが、今回は寄与分・特別寄与料について解説いたします。こちらも、遺産分割を公平にするための規定です。算出方法については、特別受益と比較してお話をいたします。
目次
1.寄与分とは
2.特別寄与料とは
3.特別受益と寄与分の算出方法の比較
4.まとめ
1.寄与分とは
被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした共同相続人(寄与分権利者)があるとき、その者の本来の相続分(法定相続分又は推定相続分)に一定の加算をして、相続人間の実質的衡平を測ろうとする制度です。要件は以下の通りです。
①共同相続人であること。
※内縁の妻、相続欠格者、非廃除者については、該当しません。
➁被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者であること。
※通常の寄与(一緒に生活をして身の回りの世話をすること)では足りず、特別の寄与(本来施設で介護をすべきところ、自宅で介護をすることなど)。こうすることで、本来、被相続人が支払うべき施設利用料を払わなくてよくなっているので、その分、特別の寄与をしたということになります。
寄与分の確定手続きについては、原則として、共同相続人間の協議で行われます。(民法904条の2第1項)
そして協議が整わない場合又は協議をすることができない場合には、家庭裁判所が、寄与者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めることになります。(民法904条の2第2項)
2.特別寄与料とは
被相続人に対して無償で療養看護等をした特別受益者は、その貢献を考慮するために方策として、相続人に対して寄与に応じた金銭の支払いを請求することができます。この金銭のことを特別寄与料と言います。ただし、誰でも特別寄与者になることはできず要件があります。
①被相続人の親族であること。
※相続人、相続放棄者、相続欠格者、非廃除者は該当しません。
(長男の配偶者などが該当します。)
➁無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと。
特別寄与料の価額の確定は、原則として、特別寄与者と相続人間の協議により行われます。(民法1050条第2項)
協議が整わないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、特別寄与者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料を定めることになります。(民法1050条第3項)
※寄与分の請求と特別寄与料の請求の相違点の一つとして、「請求に期間制限」がある点があります。寄与分には期間制限は設けられていないのですが、特別寄与料には期間制限があります。
①特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6か月を経過
➁相続開始の時から1年を経過したとき
この時を経過してしまいましたら、特別寄与料の請求をすることはできません。
ただし、寄与分も遺産分割協議の期間制限(5年・10年)ができましたので、こちらを過ぎた場合、相続人全員の合意がない限り請求できないことになります。
3.特別受益と寄与分の算出方法の比較
(特別受益)

※「足して引く」
(寄与分)

※「あらかじめ財産をよけておいて、あとで足す」
4.まとめ
このように、遺産分割協議において相続分の修正には「特別受益」と「寄与分」があることを解説してきました。今まで制限がなかった遺産分割協議の期間が2023年4月1日より以下の内容で変更されましたので、特別受益・寄与分を考慮した遺産分割ができる期間が制限されます。

また、2020年4月1日の民法改正で新たに規定されました「特別寄与料」は、相続人以外の被相続人の親族対象で、被相続人の寄与をした方にも、その請求権を認めるものですが、相続及び相続人を知ったときから6か月、相続発生から1年と比較的短期間の請求が認められていますので、該当する方は請求を検討することができるようになりました。分からない場合には、専門家の無料相談を活用することをお勧めいたします。

令和6年8月21日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
ランサムウェアは、コンピュータシステムを人質に取り、復旧のための身代金を要求するサイバー攻撃です。最近では、その手口が高度化・多様化し、企業や個人に対する脅威が増しています。以下に、最近のランサムウェアの事例と、それに対する対策方法をまとめます。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書き残す形式の遺言書で、作成や変更が比較的容易であるため、多くの人に利用されています。しかし、その一方で法的効力を持たせるためには一定の要件を満たす必要があります。以下に、自筆証書遺言を作成する際に気を付けるべきポイントを詳しく説明します。
不動産は、生前対策として非常に有効な手段です。相続税の負担を軽減し、遺産分割をスムーズに行うために不動産を活用することは、多くのメリットがあります。以下に、不動産を利用した生前対策のメリットを詳しく説明します。