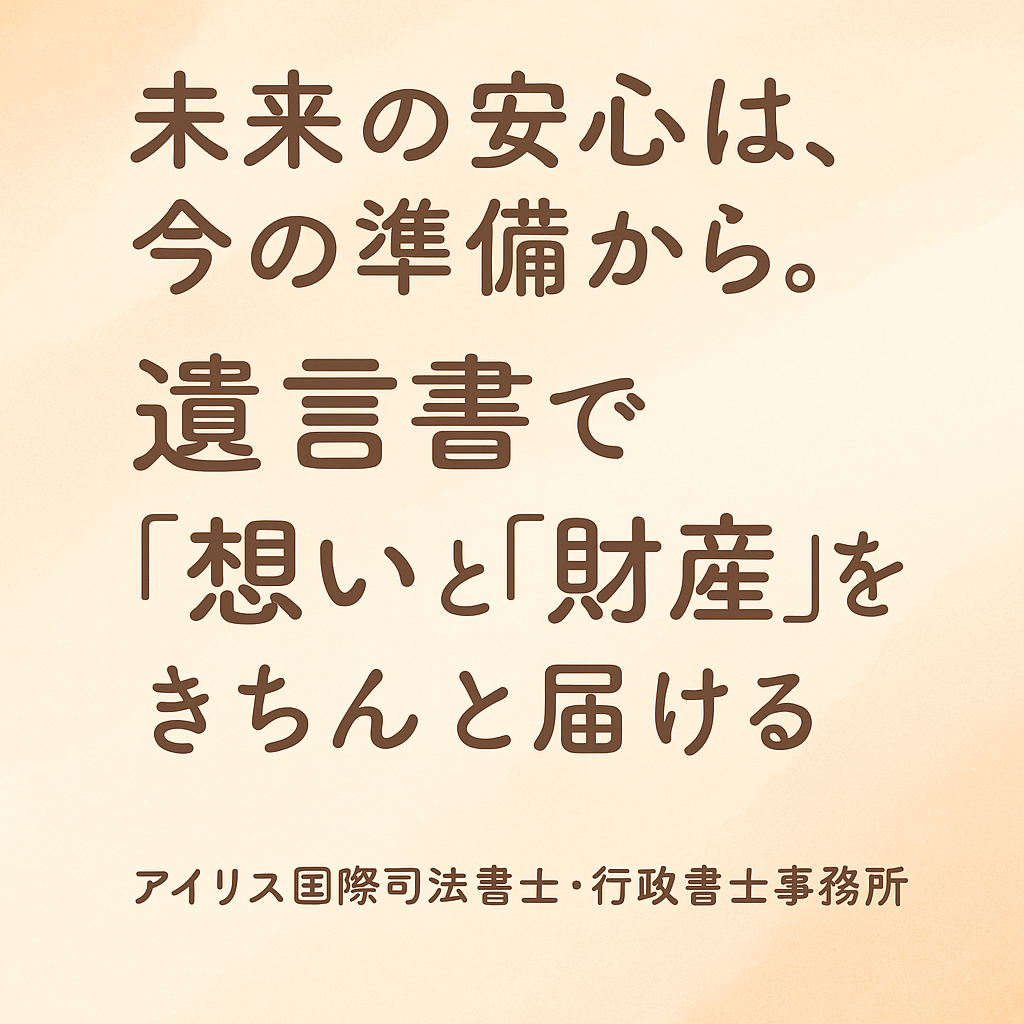香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
令和6年4月1日相続登記義務化(相続放棄をしたから、もう関係ないよ?)

令和6年4月1日に開始する相続登記義務化ですが、法定されている制度として「相続放棄」があります。自分が相続人であること、相続財産があることを知ったときから、3か月以内という期限付きの制度なのですが、果たして相続放棄をすれば遺産の不動産について放棄するわけなので、関係なくなるのか?その点について、解説していきたいと思います。
目次
1.相続放棄とは
2.相続放棄のデメリット
3.相続財産の管理義務が残る場合
4.まとめ
1.相続放棄とは
相続放棄(そうぞくほうき)とは、ある遺産や相続財産に対して、法定相続人が自らその相続権を放棄することを指します。相続放棄をすることで、その人は相続人としての権利や義務を放棄し、遺産を受け継がないことを意味します。
相続放棄をする場合、法定相続人が法定の手続きを踏む必要があります。通常は、裁判所に届出を経て、相続放棄の手続きが完了します。相続放棄が認められると、その人は相続人としての地位を喪失(初めから相続人ではなかったこととなる)し、他の相続人だけが法定相続人となります。その分の遺産は法定相続人の次の順位の者に分割相続されることとなります。
相続放棄の理由としては、債務超過による負担を避けるため、相続財産に対する不安定なリスクを回避するため、または家族や他の相続人との関係を考慮しての決断などが挙げられます。

2.相続放棄のデメリット
①資産を相続できない
➁全員が相続放棄をすると、先祖代々の資産が失われる
③後順位の相続人に迷惑がかかることがある
④相続財産の管理義務が残る場合もある
➄相続放棄は原則として撤回できない
⑥死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が使えない
などが挙げられていました。どの項目も、当然相続人ではなくなる制度なので相続人であることのメリットは失われます。ここで着目したいのは、相続財産の管理義務が残る場合がある点です。➁相続人全員が相続放棄をした場合と密接に関係するのですが、いったいどのようになっていくのでしょうか。
3.相続財産の管理義務が残る場合
それでは、相続放棄の民法の条文を確認していきましょう。
「第三節 相続の放棄
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。」
民法938条では、相続放棄の申述する先が家庭裁判所であること、民法939条では、相続放棄をした者は、初めから相続人ではなかったとみなされ、民法940条では、相続放棄したものが占有する相続財産を自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない、とあります。
つまり、自分が抱えている相続財産を引き渡すまでは、善管注意義務ほど厳格ではないですが、自分の財産と同じくらいの管理責任を負うことになります。
そして、相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産はすべての相続人のものではなくなります。民法では、清算人に引き継ぐまでは、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければなりません。相続人全員が相続放棄をしているので、この場合、「相続財産清算人」に引き渡すまでは、管理義務を負うことになるのです。ところが、「相続財産清算人」は、だれがどのように申請して、そしてその費用はいくらぐらいかかるのでしょうか?
被相続人に債務が多い場合だと、奇特な債権者の方が、わざわざ家庭裁判所に清算人の申し立てをしてくれて、予納金数十万円から百万円ぐらいをポンと出してくれるかもしれません。しかし、債務がなかったり、その額が少なかった場合、このような方が現れることはまずはありませんので、管理責任を逃れたい相続人の方が申立てをし、予納金を支払うことになります。

4.まとめ
以上のように、相続人が全員相続放棄した場合など、清算人を申し立てない限り、被相続人の財産の管理義務をずっと負うことになります。
相続放棄の手続き自体は、それほど難しいものではありませんし、家庭裁判所に出向くこともほぼありません。郵送のみの手続きが一般的です。
ただし、相続放棄をするにしても、すでに遺産分割協議に参加していた場合、自分の相続人としての権利を処分したということで、相続放棄自体出来なくなる場合があります。被相続人に多額の借金がある場合など、特に注意が必要です。
相続が発生して、相続放棄を検討されている方は、専門家に相談して、相続放棄制度の利用に可否や、その後に管理義務が生じるかどうか確認することをお勧めいたします。


最新のブログ記事
【第2回】他人の物差しで生きない勇気──あなたの「正解」は他人とは違っていい
現代社会では、「正解」があらかじめ決まっているかのような風潮があります。学歴、収入、職業、結婚、マイホーム…。それらを満たしてこそ「成功」と見なされ、そこから外れると「負け組」とラベルを貼られる。しかし本当に、他人と同じ価値観の中で生きなければならないのでしょうか?この記事では、「他人の物差しに縛られて苦しい」と感じている方へ向けて、自分自身の価値観を取り戻すためのヒントをお伝えします。
【第1回】「世の中がおかしい」と思える自分を信じる──違和感は生きる力の証
昨今の日本社会では、政治への不信感、経済格差の拡大、将来の不安など、暗いニュースが続いています。自殺者数や失業者数の増加も深刻な社会課題となっており、もはや「自己責任」と一言で片づけられる時代ではなくなりました。この記事では、「この社会はどこかおかしい」と感じている方に向けて、その違和感こそが健全な感性であり、生きる力の根源であるという視点から、希望を持って生きていくための第一歩を探っていきます。
【第5回】遺言書があることで、こんなに変わる!実例で学ぶ“残された人の安心”
「遺言書なんて、うちには関係ない」と思っていませんか?実際には、遺言書の有無で相続手続きの手間や家族間のトラブルの発生率は大きく異なります。本記事では、遺言書があったケースとなかったケースの比較を通して、"遺された人の安心"につながる具体的な効果をご紹介します。