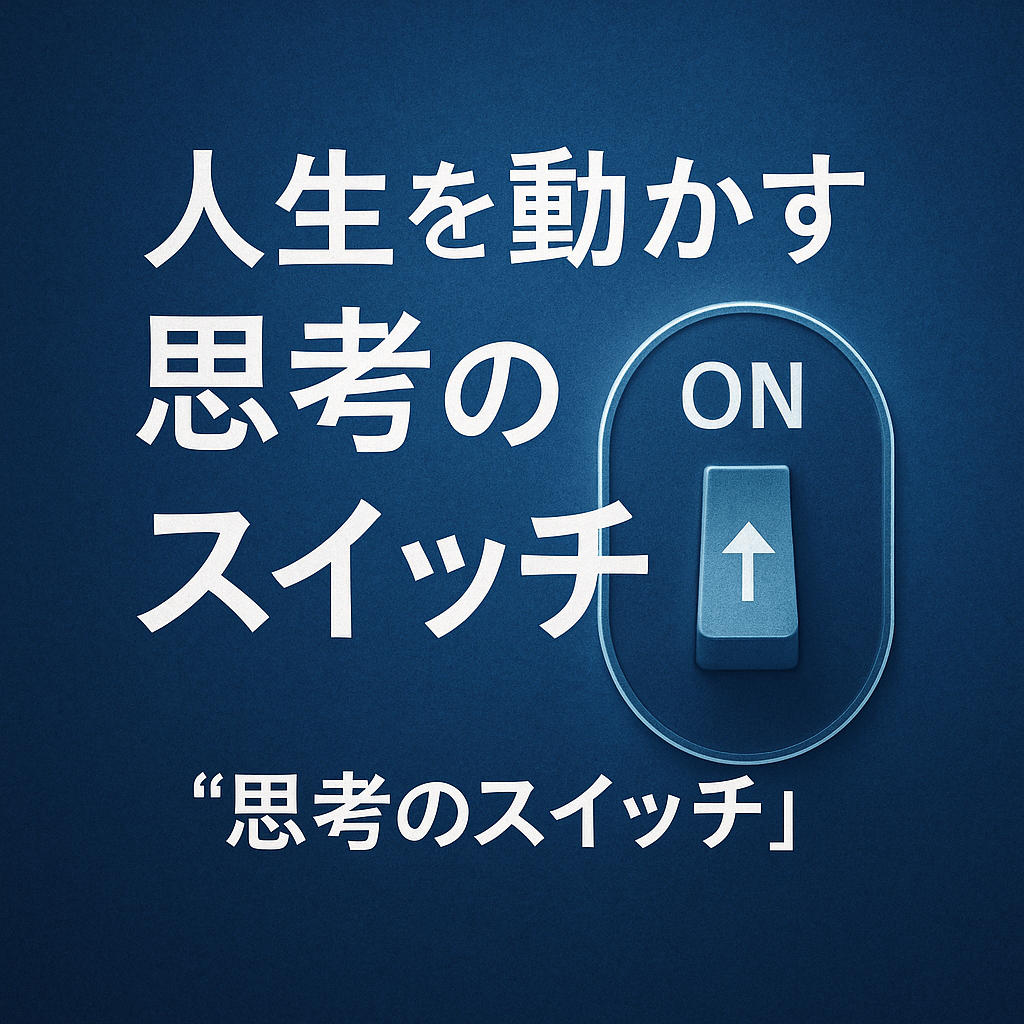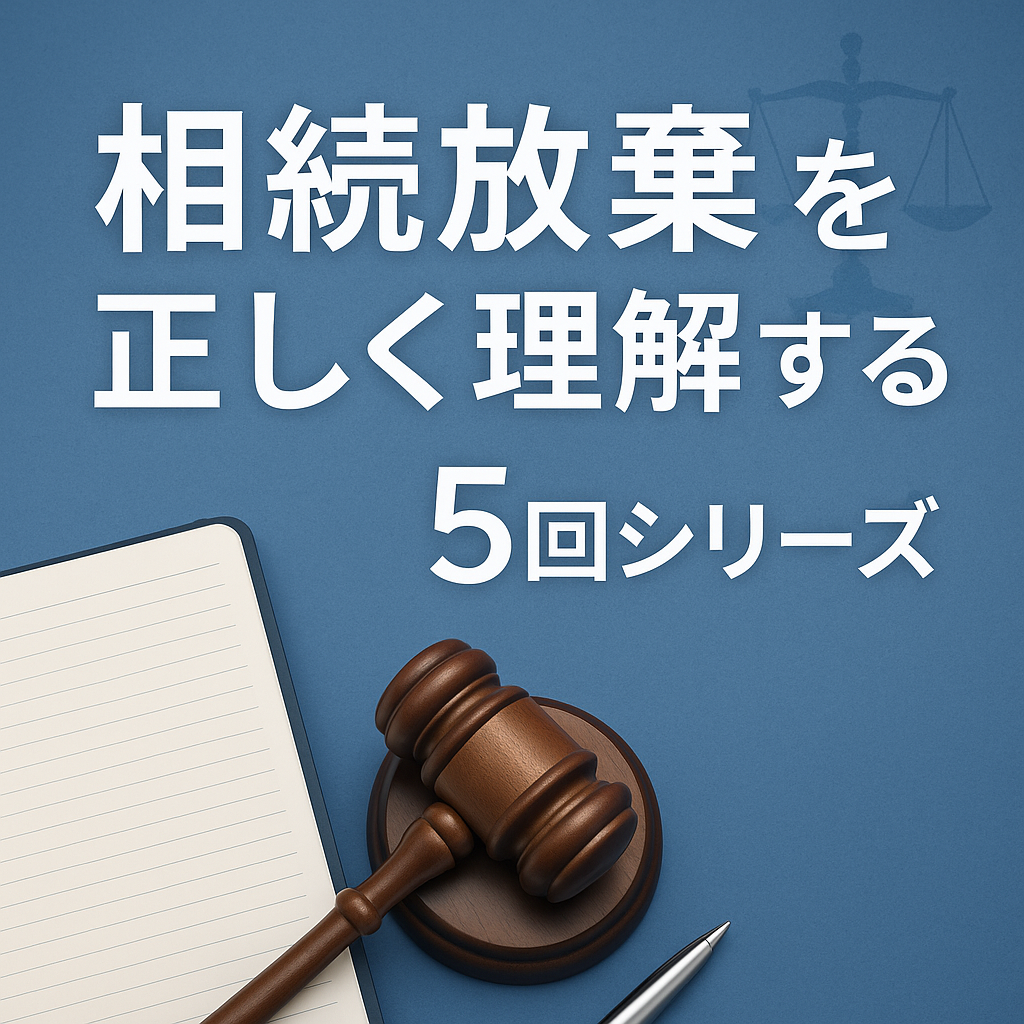香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
令和6年4月1日相続登記義務化(市町村が発行する名寄帳・評価証明書について)

名寄帳(なよせちょう)とは、固定資産税を課税するために市区町村が作成している固定資産課税台帳を所有者別にまとめたものです。固定資産評価証明書も同じくる固定資産課税台帳を所有者別にまとめたものとなります。売買などで使用される「納税通知書」の「課税明細表」と何が異なるのでしょうか。相続登記義務化に対応するために、どのように相続財産を調査すればいいのか、解説をしたいと思います。
目次
1.名寄帳・固定資産評価証明書とは
2.相続登記の場合で納税通知書の課税明細表は使えるの?
3.まとめ
1.名寄帳・固定資産評価証明書とは
名寄帳(なよせちょう)とは、固定資産税を課税するために市区町村が作成している固定資産課税台帳を所有者別にまとめたものです。固定資産評価証明書も同じくる固定資産課税台帳を所有者別にまとめたものとなります。
特に、固定資産評価証明書に記載されている「価格」が、相続登記の「登録免許税(名義変更する場合にかかる税金)」の計算の基準となる価格になりますので、とても重要になってきます。
2.相続登記の場合で納税通知書の課税明細表は使えるの?
名寄帳・固定資産評価証明書に記載されている価格は、毎年1月1日現在に所有者を基準に、所有している不動産の価格を記載しています。そして、納税通知書の課税明細表に記載されている価格と同じです。所有者の名義を変更する場合、対象の不動産が特定されている「売買等」については、課税明細表を提出すればいいのですが、相続では「?」となります。「売買等」においても、公衆用道路など主たる土地建物に付随した形で物件が存在する可能性もあります。それでは、どうすれば物件の漏れを防ぐことができるのでしょうか?
納税通知書は、固定資産税が課税対象となる不動産しか記載されていないのに対し、名寄帳・固定資産評価証明書には、課税対象外の不動産を含め記載されています。価値の低い「山林」「田・畑」や「公衆用道路」「用悪水路」なども、市町村役場単位にはなりますが、その年の1月1日現在の所有されている不動産は、すべて記載されていますので、相続登記での物件の漏れを防止することができます。
相続のヒアリングをする際に、気を付けているのが、その年(1月1日以降)に、不動産の取引をしているかどうかです。仮に取引をしている場合ですと、その物件は、評価証明書には記載されませんので漏れてしまうことになります。その場合には、取引をした時の資料を基に固定資産評価挌を調査いたします。ここまですれば、まず物件が漏れることはないでしょう。
3.まとめ
以前、「【日司連常発第96号】不動産登記申請時における課税明細書の活用の促進について(お知らせとお願い)」という通知が来ていましたが、相続登記において、物件の漏れがあったのでは、令和6年4月1日に始まる相続登記義務化に対応した適切な登記を実現することは難しいため、固定資産評価証明書を取得しております。
また、その評価証明書の物件で「0円」のものについては、高松市の場合、法務局で「近傍宅地、隣接地など」の価格から物件価格を確定して、その価格に対して「登録免許税」の計算が必要となります。
※土地を相続する場合、「租税特別措置法第84条の2の3」により、土地の評価額が100万円以下の場合には、非課税となる優遇措置があります。この登録免許税の税率の軽減措置の適用期限は、令和7年3月31日(法務省HPhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html)までとなっています。
すでに発生している相続登記の手続きが未了の方は、早めに専門家に相談されることをお勧めいたします。
アイリスでは、相続の無料相談を要予約で受け付けております。ぜひご活用ください。



最新のブログ記事
【第1回】「正解探し」をやめると人生が動き出す 〜小さな実験のすすめ〜
「人生が動かない」「現状を変えたいけど何をすればいいか分からない」と感じている人は少なくありません。その背景には、"正解を探しすぎる思考"があることが多いのです。正解を探すこと自体は悪いことではありませんが、それが過剰になると、行動のハードルを自ら高くしてしまい、一歩を踏み出せなくなってしまいます。本記事では、「正解探し」を手放すことの意味と、その代わりに取り入れたい"人生を前に進める小さな実験思考"について解説します。人生を変えたい、現状を突破したいと感じている方に向けた第一歩として、ぜひ参考にしてください。
【第5回・最終回】相続放棄の影響とは?次順位相続人・遺産分割への影響を解説
相続放棄は、相続人自身の財産管理を守る有効な手段ですが、その選択が他の相続人にどのような影響を与えるかご存知ですか?
「自分は放棄すれば関係ない」と思っていると、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
【香川県・土庄町】相続登記義務化の完全ガイド|罰則・手続き・空き家補助金を司法書士が解説
2024年4月から相続登記が義務化され、土庄町でも空き家や農地の相続に大きな影響が出ています。義務内容や罰則、放置リスクに加え、町独自の「空き家相続登記支援補助金」も解説。県外在住の方も安心して手続きが進められる方法をご紹介します。