香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
令和6年4月1日相続登記義務化(実印に関する話)
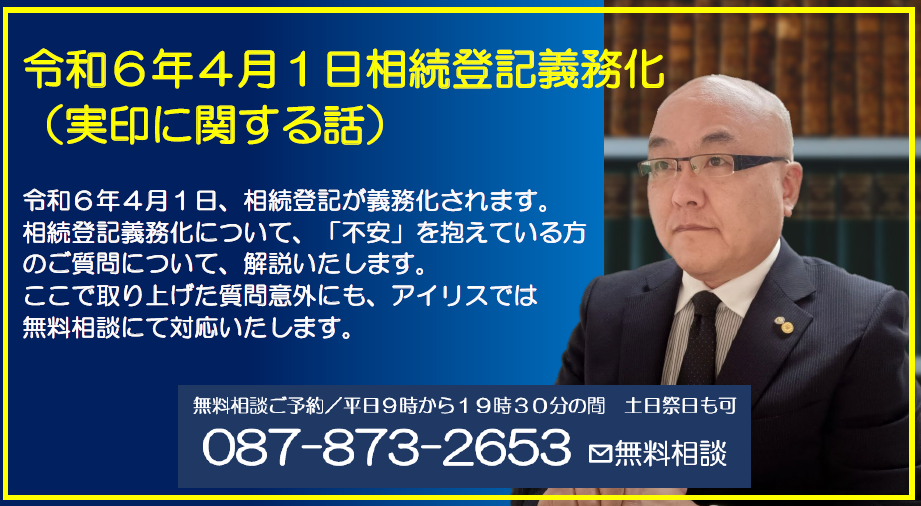
先日、遺産分割協議書を作成し署名と実印による押印を実施したのですが、印鑑証明書と照合すると、明らかに印影がかけた状態のものがありました。他の書類も確認したのですが、すべて印影の丸枠のほとんどが出ていない状態でしたので、実印の現物を確認すると、完全に欠けている状態でした。このような場合、どのような対応をすればいいのか、実体験をもとにお話をいたします。
目次
1.登録する印鑑の印影の制限(香川県高松市役所)
2.印鑑がかけている場合の対応
3.まとめ
1.登録する印鑑の印影の制限(香川県高松市役所)

これは、私が香川県の高松市役所HPの内容と、今回の事案の問い合わせについての話をしたいと思います。
香川県高松市役所での取り扱い
まずは印鑑を登録できるのは、高松市に住民登録がある15歳以上の方
※意思能力のない方は、印鑑登録をすることができません。
※成年被後見人の方は、本人が窓口にお越しになり、法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限り、申請することができます。
そして、登録できる印鑑は一人1つです。
住民票に旧姓(旧氏)併記を申請し、記載された方は、旧姓(旧氏)でも印鑑登録ができます。
一方で、登録できない印鑑については、
①住民登録している氏名と異なるもの
➁職業、資格など、氏名以外の事項を表しているもの
③自己流のくずし文字、極端な図案化などで、本人の氏名を表してないもの
④印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まる小さなもの
➄印影の大きさが、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらない大きなもの
⑥ゴム印など変形しやすいもの
⑦輪郭がないもの又は30%以上欠損しているもの
⑧竜紋や唐草模様等を外郭としたもの
⑨押印すると文字が白くなるもの(逆さ彫り印)
⑩同一世帯内の方が既に登録しているもの
※⑦輪郭が仮に20%あれば登録できるのかと言いますと、高松市役所では、登録を控えていただくように話をしているようです。(問い合わせで確認)
2.印鑑がかけている場合の対応
高松市への問い合わせで、輪郭部分がかなりかけた印鑑でしたので、かけた状態での登録はできないと言われました。そこで、印鑑屋に同行し、新たに印鑑を購入いただき、その足で市役所窓口に行き、買った印鑑を登録し印鑑証明書を取得しました。
本人が行った場合、数十分で印鑑証明書まで発行されますが、本人以外の代理人の場合、
「登録者ご本人宛に郵送による照会をしますので、登録までに1週間程度かかります。
窓口には、申請時と回答書持参時の2回、お越しいただくことになります。」とのことで、すぐに印鑑証明書を取得することはできません。注意が必要です。
3.まとめ
相続で必要となる添付書類である遺産分割協議書には、実印で押印の上、印鑑証明書を添付します。もちろん、印影と実印が異なる場合には、相続登記はできません。
ご高齢になられ、「もう必要ないだろう」と、実印がかけたままにされている方もいらっしゃるようですが、相続は、いつ発生するかわかりません。かけた実印を所有されている方は、今のうちに印鑑登録のやり直しをすることをお勧めいたします。



最新のブログ記事
【2026年版】高松市の生前対策|遺言・信託・ライフプランで決める“あなたの安心設計”指南
生前対策は「相続の準備」ではなく、**これからの人生をどう生きるかという"設計図"です。
結論として、高松市の生前対策は、遺言・信託・任意後見を"ライフプランに合わせて組み合わせる"ことが最適解です。
本記事では、2026年時点の実務に基づき、安心設計の考え方をお伝えします。
【2026年版】香川県で失敗しない生前対策とは?|司法書士が実務・制度・手続きまで徹底解説
香川県で「生前対策」を考えたとき、最も重要なことは "実務として何を、いつまでに、どうすればよいか" を正確に理解することです。
2024年4月に始まった相続登記の義務化により、"対策しないことが家族の損失・リスクになる時代" になりました。
この記事では、司法書士の視点で 制度・法律・手続き・実例まで具体的に解説し、他の記事では書かれていない「失敗しない実務ライン」を整理します。
【2026年版】善通寺市で失敗しない生前対策|弁護士・司法書士が伝える実務ノウハウ
結論から言えば、生前対策の成否は「手段の選択」ではなく、「順序と専門家の関与」で決まります。
善通寺市でも、遺言・家族信託・任意後見といった制度を"部分的に"導入した結果、かえって手続きが複雑化するケースが後を絶ちません。本記事では、2026年時点の法制度を前提に、弁護士・司法書士の実務経験から、生前対策を失敗させないための考え方と具体的プロセスを整理します。




