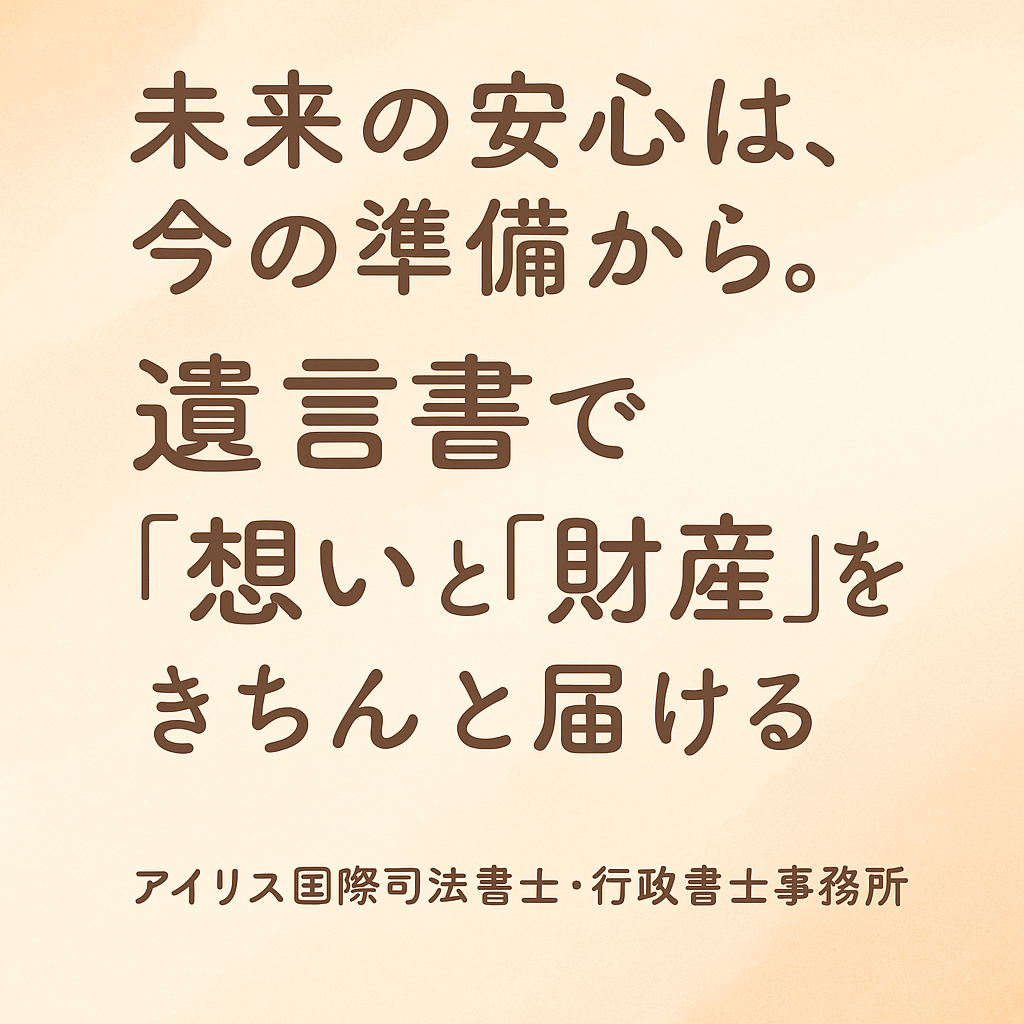香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
令和6年3月1日施行「戸籍の一部を改正する法律」(戸籍が最寄の役場で取得できるようになる)

現状、本籍地の役場でなければ取得できない戸籍ですが、令和6年3月1日より、コンピュータ化されている戸籍については、最寄りの役場、例えば本籍地は東京にあり、住所は香川県だった場合、香川県の最寄りの役場で自身の東京の戸籍を取得できます。これを「広域交付制度」と呼ばれています。
目次
1.広域交付制度とは
2.広域交付で請求できる方
3.広域交付で取得できる戸籍の種類
4.まとめ
1.広域交付制度とは
「令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。」(法務省HP引用)
例えば、本籍地が婚姻や転籍で変わっていった場合、それぞれの市町村で戸籍が作成されています。今までですと、それぞれの戸籍を取得しようと思った場合、それぞれの市町村役場の窓口又は郵送請求でしか行うことができませんでした。
戸籍などのデータは、当初各市町村役場が独自で管理していたものを法務省で一元管理することにより、広域交付を実現することができました。
この広域交付制度により、自身が現住している市町村の役場の窓口で、他の市町村役場に存在する戸籍の取得が可能になります。隣町で近いと言っても、それなりに時間がかかることから、最寄りの市町村役場で取得できるようになると利便性が上がります。

2.広域交付で請求できる方
①本人
➁配偶者
③直系尊属(自身の父母・祖父母)
④直系卑属(自身の子供や孫)
となっています。自身の兄弟姉妹につきましては、対象外になっているので注意が必要です。
注意事項として、戸籍証明書等を請求できる対象者は、市町村の戸籍担当窓口に行って請求する必要があります。近くの役場で取得できるので、今まであった「郵送請求」はできなくなります。「代理人による請求」もできなくなります。また、窓口に訪れた対象者の方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
3.広域交付で取得できる戸籍の種類
取得できる戸籍として、コンピュータ化されている戸籍・除籍証明情報が対象となります。コンピュータ化されていない戸籍、除籍証明書は対象外となります。また、一部事項証明書、故人事項証明書は請求できなくなっています。
4.まとめ
令和6年3月1日から本籍地が遠くにある場合でも、近くの市町村役場の窓口で戸籍証明書の取得が可能になります。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍は取得できません。
本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)の戸籍証明書等が取得できます。広域交付制度を利用する場合、最寄りの役場の窓口に行く必要があります。
今後の予定として、
①マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
例えば、児童扶養手当認定手続において、申請書と併せて申請人等のマイナンバーを申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍関係情報(マイナンバーの提示を受けた者に関する親子関係、婚姻関係等の情報)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となります。
➁戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されます。
利便性が上がると不安になるのがセキュリティーの問題ですが、法務省で一元管理されていますので、一極集中でセキュリティーを施せばかなり堅牢なシステムができると思います。この辺りは、法務省に期待ですね。


最新のブログ記事
【第3回】バブル期の持ち家信仰と個人債務の拡大
1980年代後半、日本は未曾有の好景気「バブル経済」に突入し、人々の間には「持ち家こそが成功の証」という信仰が広がりました。この背景には、土地神話や住宅ローンの普及、税制優遇などがありましたが、無理なローンを組んで購入した住宅は、後に多くの家庭に経済的負担を残す結果となりました。本記事では、バブル期の持ち家信仰がいかにして個人債務を拡大させ、現在の相続や空き家問題の伏線となったのかを掘り下げます。
【第3回】財産の“棚卸し”をしよう──遺言書に書くべきもの・書かない方がいいもの
遺言書を作成するうえで最も重要なのが、財産の内容を正確に把握することです。不動産や預貯金だけでなく、相続トラブルの原因となる「意外な財産」も棚卸しが必要です。この記事では、書くべき財産と書かない方がいいケース、注意点を具体例とともに解説します。
【第2回】農地改革・財閥解体と財産分散の加速
戦後の日本社会において、財産のあり方は劇的に変化しました。GHQの主導による農地改革や財閥解体は、富の集中を排し、個々人への分散を意図した施策でしたが、その結果として、かつての地主層や資産家層は急速に衰退していきました。本記事では、これらの政策がもたらした財産構造の変化と、現代の相続問題への影響について掘り下げます。