相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年8月21日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
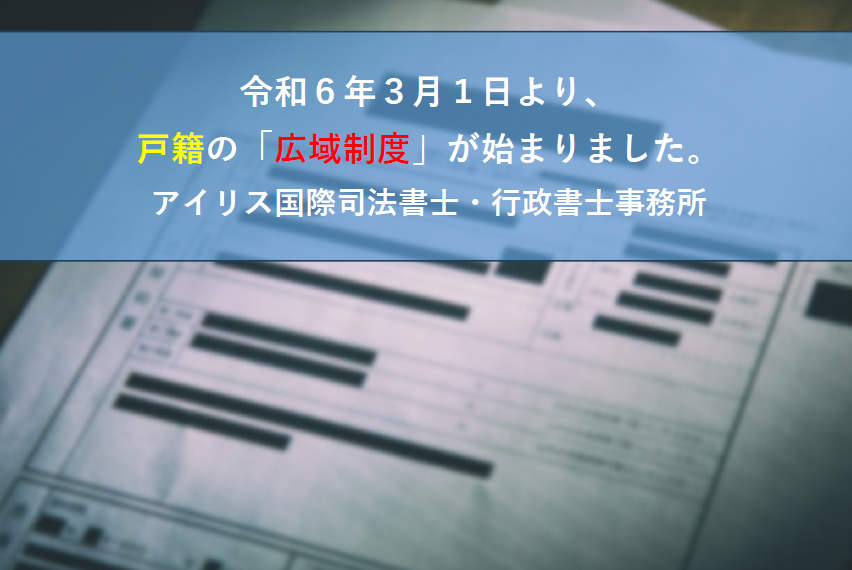
従来は本籍地の市区町村でしか戸籍謄本等を取得できませんでしたが、広域交付制度の導入により、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本等を取得できるようになっています。広域制度について解説したいと思います。
目次
1.広域制度とは
2.広域制度を利用できる対象者
3.弁護士、司法書士などの「職務上請求」は広域制度で使えるか?
4.まとめ
1.広域制度とは
広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口において、戸籍証明書や除籍証明書を請求できる制度です。事例として、高松市役所で、徳島市役所に本籍地のある戸籍を取得できるという制度です。
2024年3月1日以降、改正戸籍法の施行によって新たに広域交付制度が導入されます(改正戸籍法120条の2、120条の3)。
これが実現できた背景として、以前から法務省一元管理化に向けた取り組みをしており、各自治体の戸籍のデータを法務省でデータベース化することにより、各自治体から法務省データベースにアクセスすることにより、本籍地以外の自治体の窓口でも、戸籍を取得できるようになりました。
データ化された戸籍を取り扱うことから、データ化されていない戸籍に関しましては、広域制度の対象外となります。広域制度で取り扱うことのできる文書は、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が対象となります。
2.広域制度を利用できる対象者
広域交付制度を利用して戸籍謄本類を請求できるのは、以下のいずれかに該当する人です。
①本人
➁配偶者
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)
なお、広域交付制度を利用した請求は、代理人によって行うことは認められていません。上記のいずれかに該当する人が、必ずご自身が市区町村役場の窓口に行って手続きを行う必要があります。
3.弁護士、司法書士などの「職務上請求」は広域制度で使えるか?
「2.広域制度を利用できる対象者」として、司法書士、弁護士等は含まれておりません。つまり、弁護士や司法書士などに認められている「職務上請求」については、広域交付制度の利用は認められていません。そのため、相続人の調査などをご依頼される場合の弁護士、司法書士等による職務上請求は、通常の戸籍請求手続となり、本籍地が最寄りの市町村役場に無い場合には、郵送請求となります。
4.まとめ
相続が発生した場合、被相続人の戸籍等の文書が、すべてデータ化されている場合には、この広域制度で、最寄りの市町村役場で相続に必要な戸籍類を取得することが可能です。この点ではめりとは大きいと考えます。
しかし、一部データ化できていない戸籍類がある場合には、通常の取得方法になります。ご本人で取得する場合及び、弁護士、司法書士等に依頼する場合には、郵送による手続きで取得することになります。
詳しくは、最寄りの市町村役場の窓口、又は専門家にお問い合わせください。


令和6年8月21日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
ランサムウェアは、コンピュータシステムを人質に取り、復旧のための身代金を要求するサイバー攻撃です。最近では、その手口が高度化・多様化し、企業や個人に対する脅威が増しています。以下に、最近のランサムウェアの事例と、それに対する対策方法をまとめます。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書き残す形式の遺言書で、作成や変更が比較的容易であるため、多くの人に利用されています。しかし、その一方で法的効力を持たせるためには一定の要件を満たす必要があります。以下に、自筆証書遺言を作成する際に気を付けるべきポイントを詳しく説明します。
不動産は、生前対策として非常に有効な手段です。相続税の負担を軽減し、遺産分割をスムーズに行うために不動産を活用することは、多くのメリットがあります。以下に、不動産を利用した生前対策のメリットを詳しく説明します。