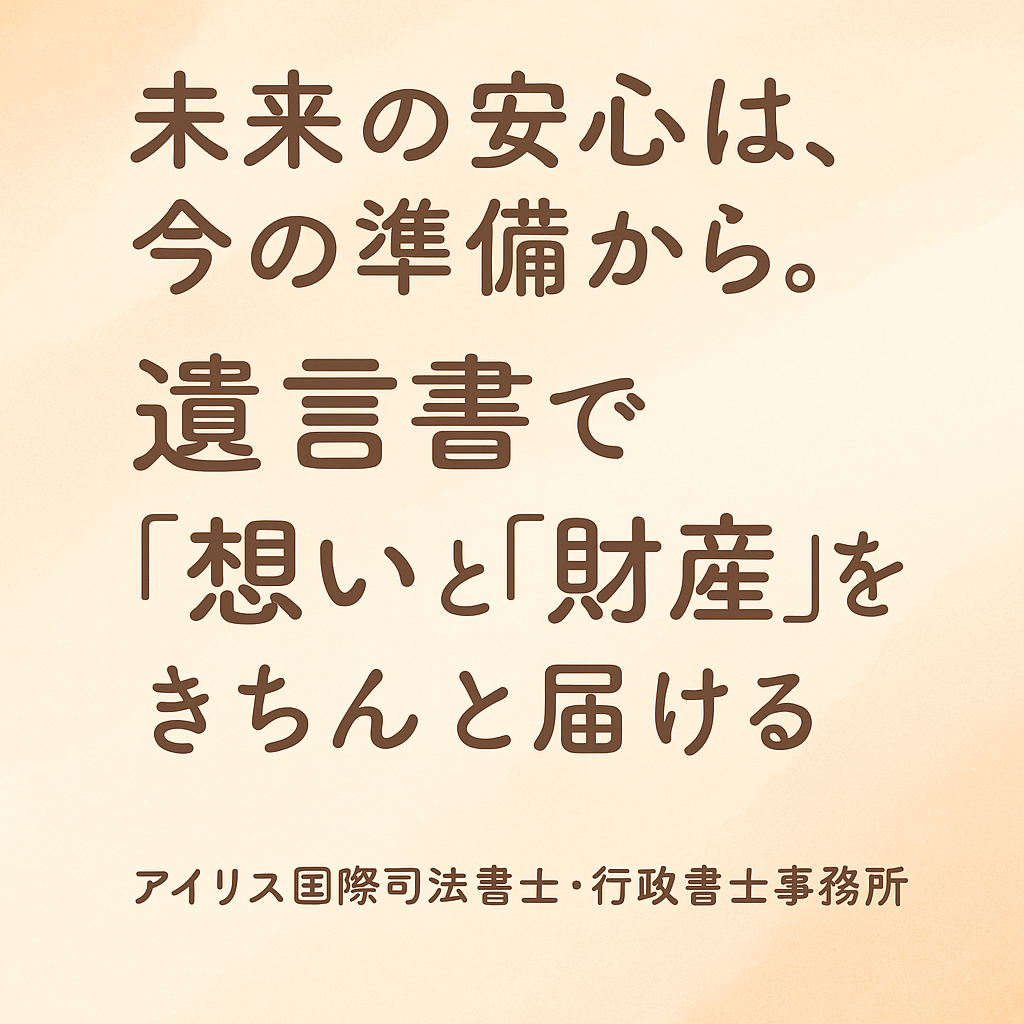香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
代位登記について

「代位登記」は他の人が変わって申請する登記のことですが、一定の要件が必要です。それでは、代位登記等について解説します。
目次
1.代位登記とは
2.代位登記ができる要件
3.実際の申請書記載
4.まとめ
1.代位登記とは

代位登記とは、債権者、自己の債権を保全するために、民法423条の規定により、債務者の有する「登記申請権」を代位行使して登記㋓㋔申請することを言います。
「民法423条(債権者代位権の要件)
第1項 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」
規定の表現は、債権者、債務者となっており、良くイメージできない方もいるかもしれませんので具体的に言いますと、
(事例1)AからBに売買によりBに余裕権が移転し、その後、Bがその所有権をCに売ったとします。この場合の住所は、A→Bの所有権移転をした後に、B→Cへの所有権移転登記をすることになります。しかし、Bが所有権移転登記を請求しない場合、Cは既に所有権を持っているのに、待つことしかできない状態になってしまいます。A→Bの登記請求権は、Bが持つ権利です。それをC(債権者)が、B(債務者)のもつAへの所有権移転請求権を代位行使するができます。
2.代位登記ができる要件
民法の規定では、「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるとき」とあります。上記事例ですと、CはBに請求はできますが、Bの持つ請求権は直接行使できません。こうなると、CはBに対する請求権(被保全債権)を保全(履行してもらうようにすること)する必要がある訳です。この「請求権の保全」が、要件になります。
(いくつか事例を示します)
①賃借権について登記する旨の特約がない場合、被保全債権となるべき賃借権設定登記請求権を有しないため、所有権移転登記の代位はできない。
➁表題部所有者A、Aの債権者(当該不動産を買った人)Bがいる場合、BはAに代位して、Aの所有権保存登記を代位できる。被保全債権はBからAへの所有権移転登記請求権。
などが挙げられます。

3.実際の申請書記載
(事例1)の申請書
登記の目的 所有権移転登記
原 因 年月日売買(A→Bの売買が発生した年月日)
権 利 者 (被代位者)B
代 位 者 C
代位原因 年月日売買の所有権移転登記請求権
義 務 者 A
添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 住所証明情報
代位原因証明情報 代理権限証明情報
となります。通常の申請書と異なる部分は、「被代位者・代位者」「代位原因」の記載と、添付書類に、「代位原因証明情報」があることです。事例のような売買の場合は契約書などがこれに当たります。
この「代位原因証明情報」を添付しなくてもいいときがあります。
それが、すでに登記簿上にある抵当権の抵当権者が請求権を代位行使する場合です。この場合でも、添付情報欄に「代位原因証明情報は、年月日受付〇号をもって本物件に抵当権設定登記済につき添付省略」の記載は必要です。
4.まとめ
今回は、代位による登記のお話をしてきました。代位するには、要件が必要です。その要件は、「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるとき」です。迷惑をかけられて登記ができない方の請求権を保全するために必要であるならば、代位による登記も可能となります。
前に、離婚調停書正本(確定証明書付)を添付して、所有権移転登記を単独で申請する場合をご紹介しました。その際に、名義人の住所が変更になっているときも、住所変更登記を代位によりすることが可能です。ただし、登記原因証明情報(住民票)の添付は必要となります。
代位の要件を充たしているかどうかにつきましては、専門家にご相談ください。



最新のブログ記事
【第3回】バブル期の持ち家信仰と個人債務の拡大
1980年代後半、日本は未曾有の好景気「バブル経済」に突入し、人々の間には「持ち家こそが成功の証」という信仰が広がりました。この背景には、土地神話や住宅ローンの普及、税制優遇などがありましたが、無理なローンを組んで購入した住宅は、後に多くの家庭に経済的負担を残す結果となりました。本記事では、バブル期の持ち家信仰がいかにして個人債務を拡大させ、現在の相続や空き家問題の伏線となったのかを掘り下げます。
【第3回】財産の“棚卸し”をしよう──遺言書に書くべきもの・書かない方がいいもの
遺言書を作成するうえで最も重要なのが、財産の内容を正確に把握することです。不動産や預貯金だけでなく、相続トラブルの原因となる「意外な財産」も棚卸しが必要です。この記事では、書くべき財産と書かない方がいいケース、注意点を具体例とともに解説します。
【第2回】農地改革・財閥解体と財産分散の加速
戦後の日本社会において、財産のあり方は劇的に変化しました。GHQの主導による農地改革や財閥解体は、富の集中を排し、個々人への分散を意図した施策でしたが、その結果として、かつての地主層や資産家層は急速に衰退していきました。本記事では、これらの政策がもたらした財産構造の変化と、現代の相続問題への影響について掘り下げます。