【2026年版】相続登記義務化で何が変わる?三豊市の事情と相続全体の流れ
結論からお伝えします。
相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から
「最初に整理すべきもの」へと変わりました。
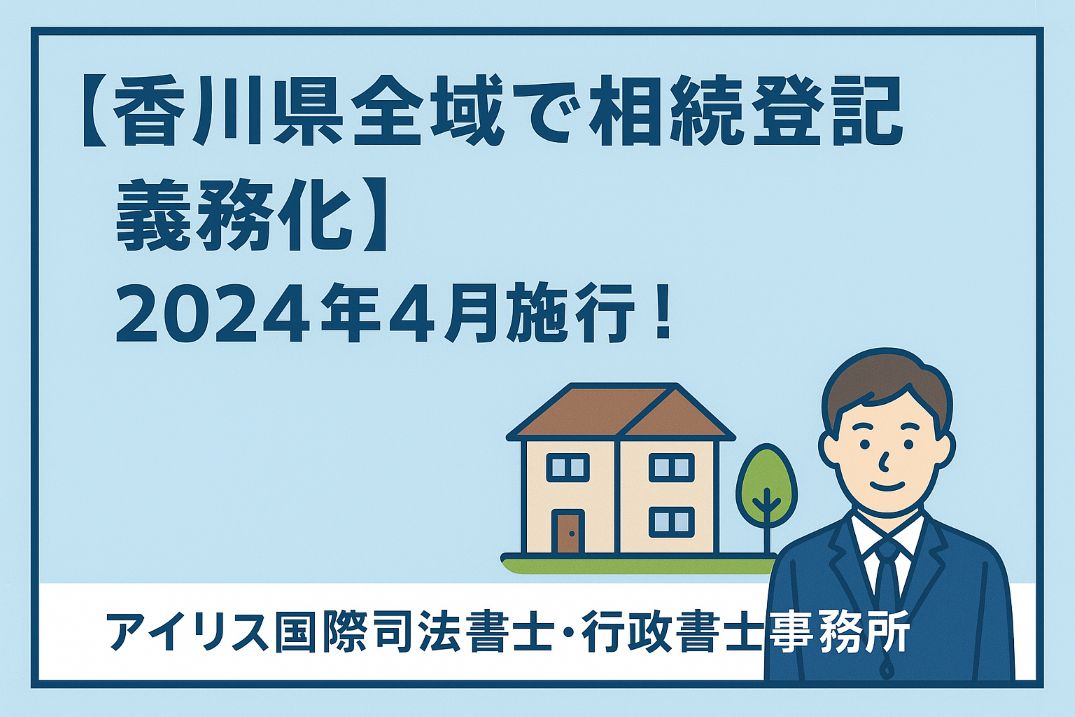
2024年4月1日より相続登記の義務化が全国で始まりました。香川県に不動産をお持ちの方、相続により土地や建物を取得した方は要注意です。義務を怠ると10万円以下の過料の罰則も。この記事では、香川県全域の方へ向けて相続登記義務化の概要や罰則、スムーズな手続き方法を司法書士が分かりやすく解説します。
目次
1. 相続登記義務化とは?

これまで相続登記は義務ではなく、「必要な時に行えばよい」という認識の方が多くいました。しかし、登記がされないまま相続が繰り返されると、所有者不明の土地が増え、公共事業や地域の発展に支障が出る問題が全国的に深刻化しました。
こうした背景から、2024年4月1日より相続登記が義務化されました。
法律によると、相続や遺贈で不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければならないとされています。
2. 香川県全域で影響を受ける不動産のケース

香川県では、以下のような不動産が多く見られ、相続登記義務化の影響を強く受けます。
香川県は高齢化が進み、空き家や農地が相続されても放置されるケースが少なくありません。これまでは「いずれ使うかもしれない」「売れないからそのままに」と考える方も多くいましたが、今後は義務化により放置は法律違反となる可能性があります。
3. 相続登記を怠った場合の罰則(過料10万円以下)

相続登記義務化の最も重要なポイントが、罰則の導入です。
義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ここで注意したいのは、過料は「刑罰」ではなく「行政上の制裁」である点です。前科がつくことはありませんが、経済的な負担に加えて、手続きを怠ったことが公的に記録されるため、不動産の売却や利用の際に不利になる可能性もあります。
特に香川県では、相続人が県外に住んでいるケースが多く、連絡不足から「誰も登記をしていなかった」という事態が少なくありません。こうした場合でも、罰則の対象となるため注意が必要です。
4. 手続きの流れと必要書類
相続登記を行うためには、まず相続人を確定し、必要な書類を集める必要があります。
手続きの基本的な流れ
主な必要書類
香川県では高松地方法務局が管轄ですが、管轄支局が地域ごとに分かれているため、事前に確認が必要です。
5. 香川県で多い具体的な事例
香川県全域で実際に多く見られる事例を紹介します。
このようなケースは香川県で特に頻発しており、早めに対応しておくことでトラブルを防げます。
6. 司法書士に依頼するメリット

相続登記は自分で行うことも可能ですが、戸籍の収集や書類作成は煩雑であり、専門知識を必要とします。
司法書士に依頼することで:
特に香川県では、離島や農村部など書類収集に手間がかかるケースが多いため、専門家に依頼するメリットは大きいといえます。
7. まとめ:香川県全域で安心して相続登記を進めるために
2024年4月から始まった相続登記義務化は、香川県全域の不動産所有者にとって無視できない制度です。
相続は「いつか」ではなく「今すぐ」取り組むべき課題です。

8. 無料相談のご案内
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ
香川県外にお住まいの方も、オンライン・Zoomでのご相談が可能です。お気軽にお問い合わせください。

結論からお伝えします。
相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から
「最初に整理すべきもの」へと変わりました。
結論からお伝えします。
高松市にある不動産を相続した場合、**相続登記は必ず向き合うべき「法律上の義務」**になりました。
「そのうちやろう」「今は困っていないから大丈夫」という考えは、2026年以降は通用しません。
結論から申し上げます。
相続登記の義務化に対応するためには、「正しい順番」で「必要最小限の手続き」を進めることが最も重要です。香川県で不動産を相続した場合も、相続を知ってから3年以内に対応しなければなりません。
結論:坂出市の相続登記は2024年4月1日から法律で義務化されています。
不動産を相続した場合、相続を知った日から原則3年以内に登記申請をしなければなりません。期限を過ぎた場合は過料(最大10万円)が科される可能性があります。
そして注意すべきは、「昔に相続したまま放置している不動産」もこの義務の対象になることです。