司法書士が教える宇多津町の生前対策|実務チェックリストと成功事例
宇多津町の生前対策は
①不動産の名義確認 ②遺言書作成から始めるのが最優先です。
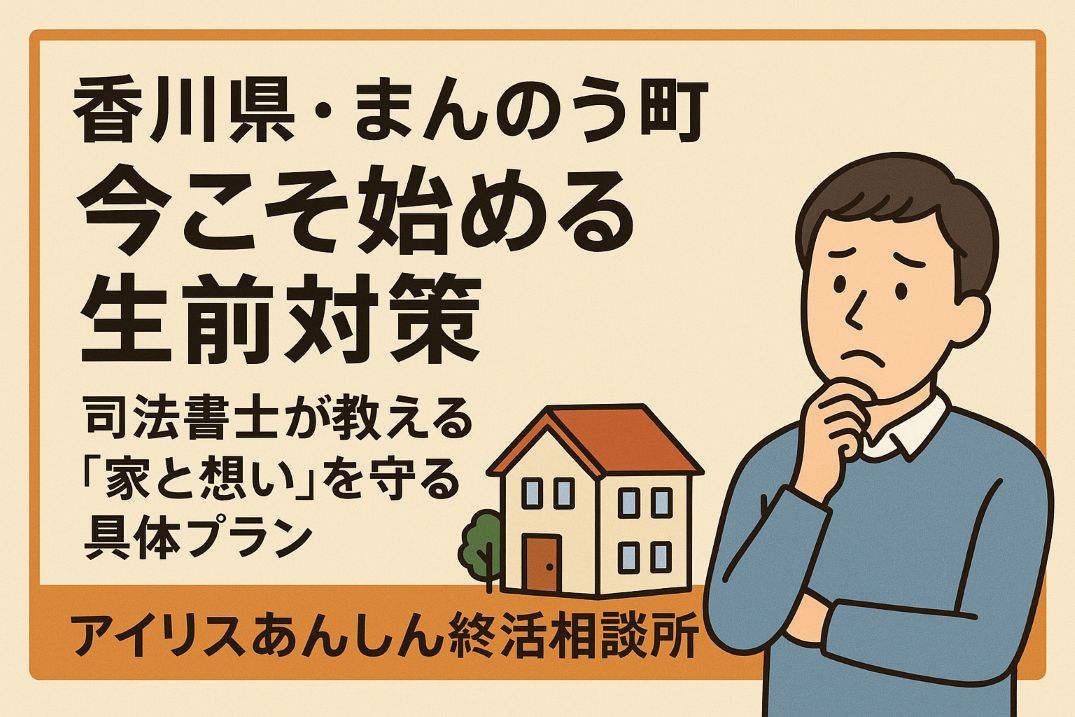
まんのう町では65歳以上の高齢者が人口の3割超を占め、空き家や相続登記の未処理が地域課題になっています。将来のトラブルを未然に防ぐためには、早めの「見える化」と「家族の合意」、そして法的な手続きの形に残すことが大切です。司法書士の視点から、まんのう町の現状を踏まえた実践的な生前対策をわかりやすく解説します。
目次
1. 現状分析:まんのう町の人口・高齢化・不動産事情(要点)

解説:これらの事情は、「名義未整理の土地・空き家が残る」「県外在住の相続人が手続きできない」等の具体的なトラブルを生みやすく、単なる情報提供ではなく"実効性ある対策設計"が求められます。(まんのう町HPより引用)
2. まずやるべき「生前対策3ステップ」

ステップA:財産を"見える化"する(必須)
やること(チェックリスト):
なぜ必要か:まんのう町では「登記が古い」「共有名義が放置されている」ケースが多く、一覧化だけで早期にリスクが見える化します。
ステップB:家族で"想い"と方針を共有する(合意形成)
やること:
なぜ重要か:多くの相続トラブルは「話していなかった」ことで発生します。話し合いの場を作り、状況の共有することで後の揉め事を大幅に減らせます。
ステップC:法的に"形"に残す(遺言・信託・後見)
やることと選び方の目安:
ポイント:制度を組み合わせる(例:家族信託+遺言)ことで「生前の管理」と「死後の承継」を一本の流れで設計できます。実行は司法書士と税理士の連携が安心です。
3. よく使われる制度と具体的な使い分け(遺言/信託/任意後見)

【遺言】――長所・短所と留意点
【家族信託】――実務での典型用途
【任意後見】――いつ・誰に使うか
(実務ポイント)これらは単独で使うより併用が現場では有効です。例えば、元気なうちに家族信託で管理を始め、判断能力低下時に任意後見を発効させる、といった流れが実践されています。
4. まんのう町でよくある相談ケース(リアル事例と解説)
事例A:実家は残したいが子が県外にいるケース
問題点:子が頻繁に帰省できず管理ができない → 空き家化・固定資産税負担増
解決策:家族信託で管理を委託し、賃貸収入を介護費に充てる設計。遺言で受益者を指定しておく。
事例B:共有名義の農地が複数世代に分散しているケース
問題点:名義が古く、相続人が増えるほど分割困難。
解決策:事前に売却・分割方針を整理し、遺言で処分方法を明記。可能ならば生前贈与で整理(税務面は税理士と要協議)。
事例C:判断能力が心配な一人暮らし高齢者
問題点:銀行口座の凍結、入院時の財産管理ができない。
解決策:任意後見契約+死後事務委任契約で、介護・費用支出・葬儀手続きまで含めたワンストップ設計を構築。
これらの事例は、まんのう町の実態(高齢化・空き家率の上昇)と直接結び付きます。早めの相談で負担を大幅に軽減できます。
5. FAQ

Q1. まんのう町で相続登記はいつまでにやる必要がありますか?
A1. 相続発生から原則3年以内に登記する義務があります(正当な理由がない場合は過料の可能性)。司法書士が登記手続きを代行します。
Q2. 空き家の相続を避けたいが、どう始めればいい?
A2. まずは登記簿確認→家族会議→遺言・信託などの順で進めると対応が容易です。放置はコスト増につながります。
Q3. 家族信託はどのくらい費用がかかりますか?
A3. 事案により大きく異なりますが、契約書作成や登記を含めて**数十万円〜**が一般的な目安です(詳細は見積りを)。
Q4. 子が県外でも手続きできますか?
A4. はい。郵送・オンライン面談・委任状による手続きで対応可能です。司法書士が代理で登記を行えます。勿論アイリスでもお手続き可能です。
Q5. まず何を相談すれば良い?
A5. 「財産の一覧(不動産登記簿・通帳・保険)」「家族構成」「希望(残したい想い)」をお持ちいただければ、初回相談で現状整理が可能です。
6. 専門家に相談する流れと費用の目安(実務フロー)

ステップ1(無料相談):現状ヒアリング(30〜60分)→現状分析と必要書類の案内
ステップ2(現状整理):登記簿・契約書類の取得(司法書士が代行可)
ステップ3(対策設計):遺言・信託・任意後見の設計(税理士と連携)
ステップ4(契約・手続):公正証書作成、信託契約書作成、登記申請等
費用の目安:遺言作成:6万円〜/家族信託:20万円〜(案件により増減)/登記手続:実費+報酬(要見積)
(注)正確な金額は資産構成・登記の複雑さにより変動します。初回面談で見積りを提示します。
7. まとめ
まんのう町では高齢化と空き家増加が進んでおり、相続登記義務化の下で「見える化→共有→法的整理」の順で早めに着手することが地域の安心につながります。まずは財産一覧を作ることから始めましょう。

(無料相談)
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ
香川県外からのオンライン相談(Zoom)にも対応しています。

宇多津町の生前対策は
①不動産の名義確認 ②遺言書作成から始めるのが最優先です。
生前対策は「余裕があればやる準備」ではありません。
今や"法的義務とリスク管理"の問題です。
認知症対策について相談を受ける中で、私が最も強くお伝えしていることがあります。
丸亀市で生前対策を始めるなら、
「不動産」「認知症」「空き家」の3点を最優先で整理することが成功の鍵です。