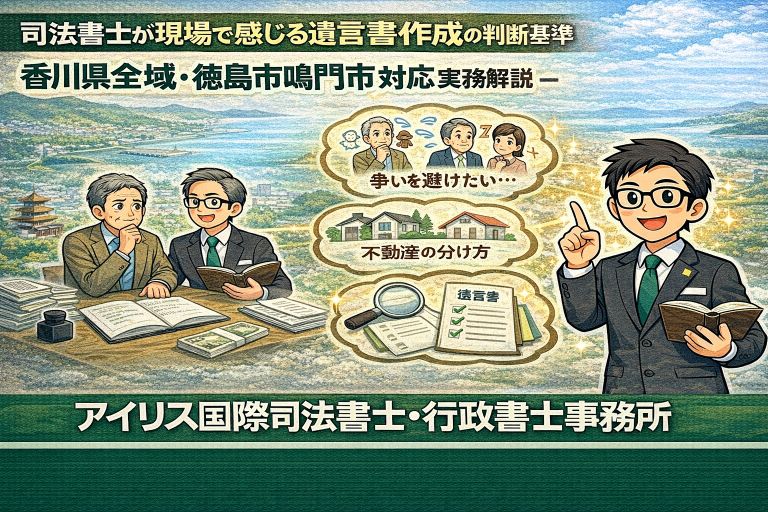遺言書の必要性は家庭の事情だけで決まるものではありません。
地域の不動産事情、家族構成、人口構造によって相続トラブルの発生パターンは明確に変わります。
【第2回】遺言書を作る前に──“自分らしい”最期を考える準備ステップ
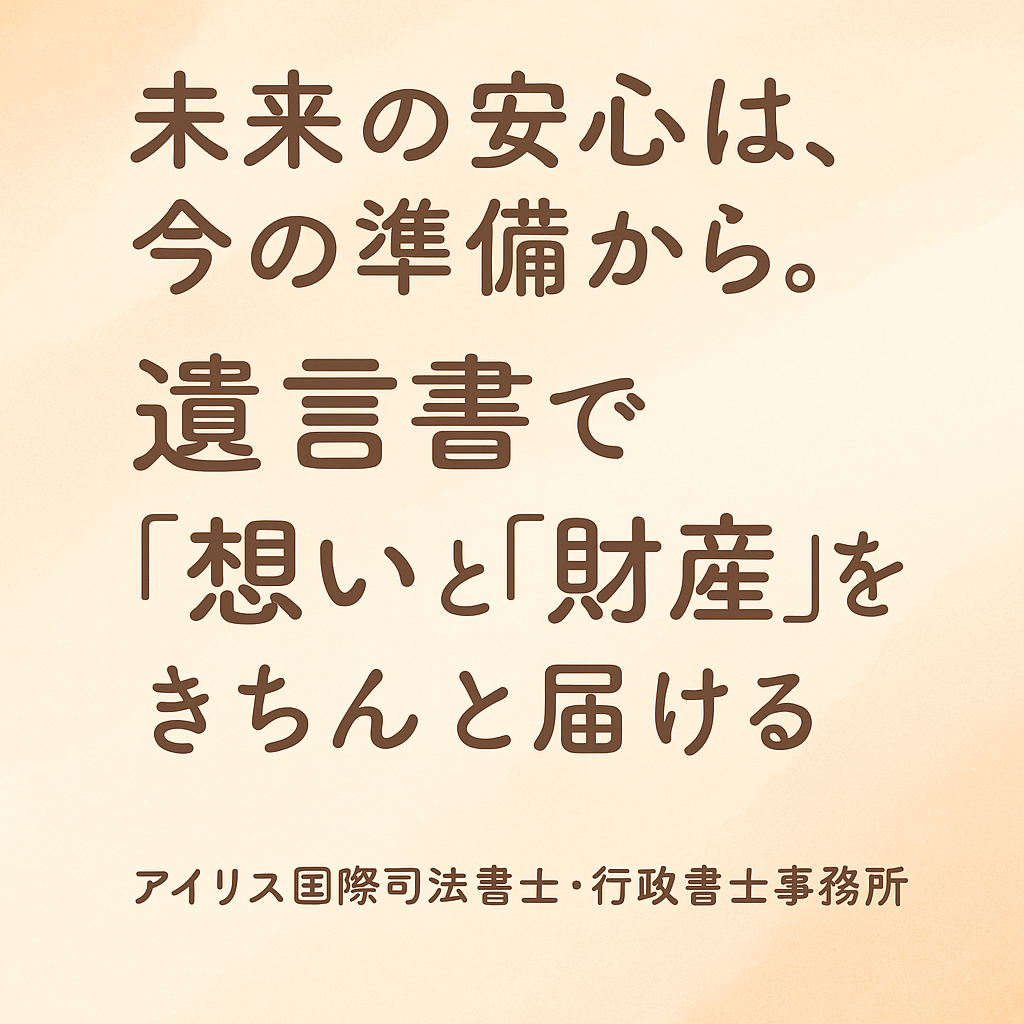
「遺言書を作ろう」と思ったとき、何から始めればよいのでしょうか。実は、いきなり文案を考えるよりも大切なのは、"自分らしい"最期のあり方を見つめることです。本記事ではエンディングノートの活用や心の整理、セミナー参加のすすめなど、遺言作成のための準備ステップをご紹介します。
📚目次
- 遺言書作成の"前段階"がとても大切
- ステップ①:エンディングノートを書いてみよう
- ステップ②:感情を整理し、想いを明確にする
- ステップ③:財産と人間関係を"棚卸し"する
- ステップ④:信頼できる人と一度話してみる
- ステップ⑤:セミナーや相談会への参加も有効
- おわりに──遺言書は"人生の集大成"
1. 遺言書作成の"前段階"がとても大切

「遺言書を作りたい」という相談をいただくことがありますが、いざ書こうとすると、手が止まる方が多いのも事実です。
それは、"誰に何を残すか"という具体的な判断の前に、自分の人生や家族との関係をどう整理するかという課題があるからです。
この記事では、「遺言書を書く前にやっておきたい5つの準備ステップ」を解説します。感情面と実務面の両方から備えることで、後悔のない遺言作成につなげましょう。
2. ステップ①:エンディングノートを書いてみよう

最も手軽で有効な準備が「エンディングノート」の作成です。
エンディングノートとは、法的効力はありませんが、自分の希望や情報を自由に記録できるノートで、以下のような内容を記します。
- これまでの人生の振り返り
- 家族へのメッセージ
- 延命治療の希望
- 葬儀やお墓に関する希望
- 財産や保険の一覧
- ペットや趣味の品についての希望
これらを自分の言葉でまとめることで、**「自分は何を大切に思っているか」「誰に何を託したいか」**が自然と見えてきます。
3. ステップ②:感情を整理し、想いを明確にする

遺言書は"感情の文書"でもあります。
たとえば、長年介護してくれた娘に感謝を伝えたい、遠く離れていても気にかけてくれる孫に思いを残したい――そうした気持ちは、財産の配分以上に大切です。
書き出してみると、これまで心の中にあった未整理の感情が整理され、「本当に遺したいもの」が明確になります。
結果として、相続のトラブルを防ぎ、**"家族を思う遺言書"**につながるのです。
4. ステップ③:財産と人間関係を"棚卸し"する
次に重要なのが、財産と人間関係の整理です。
財産の棚卸しでは、以下のような項目を書き出しておきましょう。
- 銀行口座の情報(銀行名・支店・口座番号)
- 所有している土地建物の所在地・評価額
- 株式・投資信託などの金融商品
- 生命保険の加入内容
- 借金や連帯保証などの負債
- デジタル資産(ネット銀行、仮想通貨など)
人間関係の棚卸しでは、法定相続人だけでなく、以下の人についても検討します。
- 特に世話になった親族や友人
- 相続人ではないが、財産を遺したい人
- 疎遠・不仲な相続人がいるかどうか
棚卸しによって「どの財産を誰にどう渡すか」が現実的に見えてきます。
5. ステップ④:信頼できる人と一度話してみる

遺言書を作ることは一人でもできますが、信頼できる専門家や身近な人との対話を通して、自分の考えを深めることも非常に有益です。
たとえば、
- 家族にあらかじめ希望を伝えておく
- 司法書士や弁護士に相談してみる
- 相続経験のある知人に話を聞いてみる
といった方法があります。
対話を通して、自分では気づかなかった視点や、法的な注意点が浮かび上がることもあります。
6. ステップ⑤:セミナーや相談会への参加も有効
最近では、自治体や司法書士事務所が開催する相続・遺言に関するセミナーも増えています。
参加することで、同じような悩みを持つ人の声を聞けたり、知識が整理できたりと、気づきが多く得られます。
また、専門家と出会うきっかけにもなり、「いざという時、誰に頼ればいいか」が明確になることも大きなメリットです。
※当事務所「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」でも無料相談会を開催しております。気軽にご参加ください。予約☎087-873-2653
7. おわりに──遺言書は"人生の集大成"
遺言書は、単なる「お金の分配表」ではありません。
**人生の歩みを振り返り、誰にどんな想いを遺すかを形にする、大切な"人生の集大成"**です。
その準備段階から真剣に取り組むことで、形式にとらわれない「本当の意味での遺言」が完成します。
次回は、具体的にどんな財産をどのようにリストアップすれば良いか、「財産の棚卸し」の実践編をご紹介します。

最新のブログ記事
司法書士が現場で感じる遺言書作成の判断基準|香川県全域・徳島市鳴門市対応実務解説
遺言書を作るべきかどうかの判断は、形式論ではなく個別事情の整理によって決まります。相続相談の現場では、資産額よりも不動産の性質や相続人構成が難易度を左右するケースが多く見られます。本記事では香川県17市町および徳島北部を念頭に、実務経験を基に遺言書作成判断の視点を整理します。
【香川県全域と徳島市、鳴門市の生前対策】保険金と遺言書を上手に組み合わせる家族思いの方法
「生命保険があれば遺言書はいらない」と思っていませんか?実は、保険金と遺言書を上手に組み合わせることで、ご家族の生活をより確実に守ることができます。香川県高松市の司法書士が、保険金と遺言書の関係について、わかりやすく解説します。
【香川県全域と徳島市、鳴門市の生前対策】不動産の名義変更が義務に!遺言書で準備すれば安心
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産の名義変更を怠ると過料のリスクが。この記事では、遺言書を使って事前にできる安心の備えについて、やさしい言葉で司法書士が解説します。